「デジタル全体主義」VS「デジタル資本主義」:新しい地政学に向けて
「デジタル全体主義」VS「デジタル資本主義」:新しい地政学に向けて
塩原 俊彦
はじめに
「境界」を探る研究は空間そのものの「裂け目」にも関心を向けるべきである(1)。筆者はすでに『境界研究』において、拙稿「サイバー空間と国家主権」を公表した (2)。パソコンやインターネットなどの新しい技術によって「リアル空間」に生じた裂け目たる「サイバー空間」に注目したことになる(3)。その後の急速な時代の変化のなかで、サイバー空間とリアル空間が融合する時代に突入した。両空間の融合が新たな裂け目としてまったく新しい考察対象になりつつあると考えられる。これが本稿の出発点である。
このサイバー空間とリアル空間の融合は、これまでリアル空間だけにかかわる空間と時間が人類を包摂してきた時代や、それにサイバー空間が補完的に付加された時代と異なって、新しい位相を人類にもたらそうとしているかにみえる。サイバー空間とリアル空間の境界そのものが曖昧になるなかで、ソーシャルな現象(個人と個人、個人と組織を結びつける現象)そのものを大きく変貌させつつあるのではないかとの見方が可能になる。これまでの民主主義が後退し、国家主権も衰退し、新たな環境が人類を覆おうとしているのではないか。そこではこれまでの地政学とは異なる新しい地政学が求められるようになるのではないか。
こうした問題意識から、筆者は2019年8月、『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法的規制のゆくえ』を社会評論社から上梓した。第五世代移動通信システム(5G)、人工知能(AI)、ブロックチェーン(Blockchain)、Internet of Things(IoT)の技術に支えられた新しい外部環境の実態を分析したのである。本稿では、この考察をもとに集中化システムに基づくデジタル経済を基盤とする「デジタル全体主義」なる概念(中国モデルと言えよう)と分散化システムの全面化したデジタル経済の広がる「デジタル資本主義」との攻防について分析する。拙著の執筆とともに生まれた問題意識である以上、本稿に記述の一部は拙著と重複せざるをえいないことをあらかじめ付記しておきたい。
ジョン・アグニューは『境界研究』に「グローバル化時代の地政学」という論考を寄せている(4)。これはグローバル化時代をリアル空間における相互依存性の進展として理解しており、全体としてサイバー空間への関心は薄い。それでも結語部分では、「明らかだと思われることは、20世紀初めに繰り返されてきたような、限定された領域に基づいて競争し合うという見地から地政学を捉えてしまうと、それ以降、生起してきたことをほとんど、あるいはまったく捉えることができないということである」と指摘している(5)。この言説を21世紀のいまに適用すると、「限定された領域に基づいて競争し合うという見地」はまったく現実を反映していないことになる。サイバー空間とリアル空間の融合する現在、新しい地政学がまさに必要なのだ。こうした問題意識にたって、終章で新しい地政学について考えたい。
1.「デジタル全体主義」をめぐって
まずは「全体主義」について考えてみよう。全体主義といえば、ヒトラーのナチ支配やソ連のことだと思っている人が多いかもしれない。だが本当は、米国も日本も中国も全体主義国家と言えなくはない。全体主義はトータリタリアニズム(totalitarianism)と呼ばれ、「個人は国家・社会・民族などを構成する部分であるとし、個人の自由や権利より国家全体の利益が優先する思想、また、その体制」(『広辞苑』)を意味している。つまり、個人より国家全体の利益を優先する程度次第で全体主義の程度が異なるだけであり、日本や米国が全体主義ではないなどとそもそも断言することなどできない。
エミル・レーデラーはその著書『大衆の国家』のなかで、「全体主義国家は大衆の国家である」と指摘している(6)。大衆の存在自体が全体主義国家につながりかねないというわけである。シグマンド・ノイマンは『大衆国家と独裁』のなかでは、大衆操作のために藝術が活用されてきたことに注意喚起している(7)。全体主義の国家体制を厳密に定義づけるために、カール・フリードリヒらはつぎの六つの指標から全体主義化の程度を考察している(8)。①単一のイデオロギー、②一人の人間により指導される単一の大衆政党、③テロル的警察統制のシステム、④マスコミの独占、⑤武器の独占、⑥中央指令経済――というのがそれである。これは裏を返せば、全体主義国家の程度には差があり、日欧米の先進国であっても全体主義的傾向がまったくないなどとは決して言えないのである。
よく現在の中国やロシアを「国家資本主義」と呼ぶ者がいる(9)。だが、義務教育を通じて国家に都合のいい労働者を育成してきた以上、英国もフランスも日本も国家資本主義的な側面をもっている。あるいは、国家主導で特定産業の保護育成をはかっているのだから、国家資本主義でないとは言えない。これと同じように、欧米先進国であっても、決して全体主義的側面がないとは言えない。その証拠に国家の安全保障を理由に、個人の自由や権利を制限する数々の措置を国家は個人に強いている。近年になって、知らず知らずのうちに全体主義の傾向が世界的に強まっているような気がしてならない。それは、ロシア革命がもたらしたソ連という全体主義国家の再来という悪夢を想起させる。
(1) 全体主義国家=中国
したがって、中国もまた全体主義国家と呼ぶことができる。ただ、その国家主導の統治の度合いは欧米諸国に比べてずっと高い。ここでは、デジタル経済面で全体主義的傾向を強める中国の実態について論じてみたい。
すでに紹介したように、中国は社会信用体系の構築に取り組んでいる。社会の持続的発展のために「信義誠実の欠如」という問題を改善する目的で信用情報システムを整備し、さまざまな信用データベース化が計画されている。中国共産党政治局の「中央全面深化改革委員会」がこれを中央集権的に指導するという中央集権的な方法を前提に、「政務」、「ビジネス」、「社会」、「司法」の4分野での信用システム構築が目標とされた。個人と企業の信用評価システムが必要となり、大量の情報データが蓄積されディープ・ラーニングを通じたアルゴリズムやAIの開発に向けた体制が整えられている。つまり、デジタル経済の発展と全体主義が強く結びつけられていることになる。
2018年前半の情報では、包括的な社会信用体系はまだ中国には存在しない。それでも地方や特定の産業向けに実験的な信用システムが構築されている。社会信用体系の基礎的構成要素は情報の収集に基づくデータベースであり、地域別、部門別、国家レベルでのデータベースの創出・相互統合がめざされている。その対象は個人だけでなく、法人、政府機関におよぶ。さまざまな分野のデータが銀行融資などのビジネス上の信用だけでなく、医療、政府調達、安全保障などの社会信用体系上の格付につながっている。
2015年と2016年に中央政府は社会信用実験を43市で実行するように促した(10)。江蘇省北西部の宿遷では、各成人住民に「信頼価値」として1000ポイントがあたえられることになり、献血のような良い行いにはポイントが加算される一方で、交通違反などではポイントが削減されることになった。毎月ポイントのスコアが再計算されて、モデル市民のAAAから信用価値なしのDまで8段階のランキングに住民が識別される。すでに中国全体で1200万人強がブラックリストに収載されており、航空券の取得が拒否されるなどの措置がとられている。
個人に関するすべての情報は人物調査書類にこれまでも蓄積されてきた。それは、教育履歴、その評価、軍人としての地位、学校・大学・雇用主からの評価情報、政治的見解に関する情報、宗教への姿勢などからなる。この情報は主として国営企業や特殊国家機関に蓄積され、当該者のボスや公的管轄機関の公務員が利用できたが、個人データの電子化および警察のデータベース化によって、個人に「タグ」をつけ、「テロリスト・その支持者」、「暴力的」、「ギャングメンバー」、「麻薬常習者」などの明確なグループ分けに加えて、チベットや新疆ウイグル自治区の独立支持者、金融詐欺の組織者・被害者、退役軍人などの区別も可能となった。国へのなんらかの不満分子、外国人と関係をもつ人物などについても注意が払われるようになっている。
中国共産党が推進する社会信用体系は、実は共産党が破壊した伝統的な支配秩序を「道具主義的な権力」に強制的に服従させるようにするための手段ではないか。家父長制に基づく家族、宗教、政治的自由が破壊され、多くの中国人はよく知る人だけを信じるようになり、信頼の紐帯は弛緩し、ばらばらにほどけてしまっている。その証拠に、中国ではクレジットカードの普及が遅れ、それがかえってキャッシュレス決済としてのスマートフォンの活用を急速に普及させたと考えられる(11)。
中国共産党はビッグデータを取り込んだアルゴリズムに基づくAIを信じ込ませることで人々を支配しようとしているのだ。しかも、そのとき習近平を頂点とする中国共産党は人々を道具とみなし、自らの統治に利用している。
(2) 「上」からのブロックチェーン」
注目されるのは、すでに指摘したように、中国政府はブロックチェーンでも「上から」の集権的なやり方で全体主義を強化しようとしていることだ。ブロックチェーンには、二つの形態がある。一つは、パブリック型であり、そのブロックチェーンへの入退出が自由で、ブロックチェーンの所有者がいない形態である。台帳上のだれもが同じ台帳のコピーへのアクセス権をもち、利用者と同じ数の台帳コピーがあることになる。このパブリック型ブロックチェーンに近いのはビットコインかもしれない。ただし、ビットコインの直接参加者(台帳保有者)には限界があるために「取引所」を通じてビットコインを売買しているようにみせかけているだけなので、本当はパブリック型とは言えない面もある。
ルールの執行とその作成をだれが行うかに注目すると、ビットコインの場合、コンピューターのネットワークであるビットコイン・ネットワークによって執行されるルールはビットコイン・プロトコルであり、そのプロトコルの最初のヴァージョンはサトシ・ナカモトによって、その後のヴァージョンは核となるチームによって作成された。そのチームは専制的な性格をもっているわけではないが、ルールであるプロトコルの作成は総意としての合意形成に基づいており、人的な側面、すなわち「人的統治」という面を伴っている。ゆえにビットコインは分散型をイメージしたパブリック型とは異なっている。
もう一つはプライベート型であり、許可された利用者にだけブロックチェーンへのアクセス権を供与するブロックチェーンの所有者ないし運営者がいる形態だ。許可された利用者だけが台帳コピーをもつことができる。ただ混合型として、パブリック型の一つないし複数のノードが権威をもつようになって運営者のような役割を果たす事態も考えられる。
いずれにしても、ブロックチェーンを利用すれば、その利用者すべての関係が分散化システムに組み入れられるわけではなく、プライベート型では、ブロックチェーン内に所有者ないし運営者という「上位者」がいることを忘れてはならない。パブリック型であっても、プライベート型であっても、いずれにおいてもブロックチェーン内の統治という問題が残されている点が重要なのだ。
ブロックチェーンは必ずしも分散化されておらず、集中化されているという議論も可能だ。「ビットコインよりも小さなブロックチェーンはすべて本質的に、そのオペレーターのコントロール下にある集中化されたデータベースである」という指摘もある(12)。そのビットコインの場合でも、仲介者である「取引所」の一部(Binance、OKExなど)が上位者であるかのように振舞っているという現実がある(13)。
中国政府はブロックチェーンもまた中央集権的に管理しようとしている。つまり、それだけ中国のデジタル経済の発展は政府主導で行われている。さらに、監視システムを国内に整備することで、ジョージ・オーウェルの小説『1984年』に登場する「ビッグブラザー」のような集権的な統治が進んでいる。まさに、全体主義的な国家による監視の目が国民を抑圧している。そうした監視システムの輸出についてはすでにのべたが、ここでは国内の状況について簡単に説明したい。
中国では、社会信用体系整備の一環として主要都市での監視体制の強化が進んでいる。それは、通りや広場、交差点、駅、病院、公園、ショッピングセンター、公務員施設などの人の集まる場所とその周辺を死角なしで360度を監視できるようにする計画だ。中国には老子の「天網恢恢疎にして漏らさず」(天の網は広大で目があらいようだが、悪人は漏らさずにこれを捕らえる)で有名な「天網工程」(Skynet)という監視システムがすでに稼働している。中国メディア(観察者網)によれば、天網システムが2018年3月段階で、16の省・市・自治区において2000万台以上の高解像度カメラを通じて運用されている。都市部中心に設置され、顔認証できるAIと組み合わせて人々を監視している。農村部については、「雪亮工程」(Sharp Eyes)という監視システムが部分的に広がっている。テレビなどの家電やスマートフォンなどから個人情報を収集し、県・郷・村を監視するもので、「雪亮」は広東省の家電メーカー、美電貝爾が開発したとされる。こうした状況があるからこそ、いまの中国は「デジタル全体主義」に傾いているとみなすことができる。
2.「デジタル資本主義」をめぐって
(1) ポスト産業資本主義の諸説
この「デジタル全体主義」に対抗して、欧米先進国では「デジタル資本主義」が発展しようとしているかにみえる。ここではまず、ポスト産業資本主義をめぐる議論について簡単に解説しよう。たとえば時代が貨幣や資本や強い牽引力をもっていた資本主義から「データ資本主義」(Data Capitalism)という、情報データが強い牽引力を有する時代に移りつつあるとする主張がある。筆者がはじめてデータ資本主義という言葉を見たのは、オックスフォード大学のビクター・マイヤー=ショーンベルガー教授とトーマス・ランゲの共著『ビッグデータ時代の資本主義の再発明』を読んだときだ(14)。この本以前にも、たとえば2017年のサラ・ウェストの論文「データ資本主義:監視とプライヴァーの論理の再定義」があった(15)。前述の本には、データ資本主義自体についての説明がない。そこでここでは、ウェストの論文を参考にデータ資本主義について考えてみたい。ウェストはデータ資本主義を、「情報時代の権力再配分を可能にするデータ商品化を備えたシステム」と定義している。コミュニケーションや情報は歴史的に権力の鍵を握る源泉だが、データ資本主義は結果として非対称な権力配分につながり、データを有意味にする能力やデータアクセス権をもつ主体に有利に働くようになる。といっても、この程度の説明では、データ資本主義の内容がはっきりしない。
今度は、「データ資本」なるものを分析した、2106年にMITなどが公表した「データ資本の隆盛」という論文をみてみよう(16)。その論文では、データ資本はすべてのデジタルデータを包含していると指摘している。たとえば、GPS装置に記録されたトラックの動き、ソーシャルメディアに記録された「お気に入り」や「シェア」、さらに取引での購入・返却・再注文などのデータである。データ資本は財・サービスの生産に必要な記録済みの情報であり、建築物や設備のような物的資産と同じ長期的な価値をもっている。データ資本は過去十年ほどの間に創出されたすべてのオンライン消費者サービスにとって、もっとも重要な資産の一つなのだ。論文では、データは新しいサービスを創出する「原料」とされている。このため、Google、Amazon、Netflix、Uberといった会社は情報を蓄積し、データとして分析したり、保管したりしてきたわけである。データには、①非競争的(複数の同時的利用が可能)、②代替不能(情報を別の情報に代替させることはできない)、③事後的価値入手(利用後はじめてその価値を知る)――といった特徴がある。加えて、ネットワーク利用者が増えれば増えるほど、ネットワーク自体の価値が高まるという「ネットワーク効果(外部性)」をデータ利用者は得られる。いわば、データは「尽きることのない資源」ということになる。こうした特徴をもつデータからなるデータ資本は人間の意思決定のアルゴリズムの適用範囲を広げ、さまざまの意思決定に人工知能(AI)を活用することを可能にする。
しかし、これだけではデータ資本主義の隆盛の意味が腑に落ちない。そこで、この言葉を政治学者ジョディ・ディーンのいう「コミュニケーション資本主義」(communicative capitalism)の延長線上で理解してみよう(17)。彼女は、論文のなかで「コミュニケーション資本主義」の別名として、知識経済、情報社会、認知資本主義をあげている。コミュニケーション資本主義はコミュニケーションにスポットを当てながら資本主義の変化を問おうとしている。同じように、データ資本主義もデータに注目しながら、資本主義の変化を論じようとしていることになる。コミュニケーション資本主義は後期資本主義の形態で、そこでは民主主義の中核と喧伝されている価値(アクセス、中に含められること、議論、参加)がグローバルにネットワーク化されたコミュニケーション技術(拡大、強化、相互連結)を通して実現されるようになる。つまり、この概念は民主主義と資本主義の不可思議な結合をイメージしている。電子化されたコミュニケーションの速さ、同時性、相互連結は集中した富を生み出すが、そこではだれがメッセージを送ったか、あるいは、その中身といった使用価値よりも、メッセージが流通するデータの流れの一部であり、その流通に寄与することが重要になる。メッセージのいわば交換価値の重要性が高まるのだ。この流通重視のコミュニケーション資本主義はインターネットを通じて世界中に拡散する。具体的には、フェイスブック、ツイッター、アマゾン、アップルにしてもネットワーク効果(外部化)を受けて巨大化しその影響力を増している。こうした変化こそ資本主義全体のあり方に影響をおよぼしているとみなして、ディーンはコミュニケーション資本主義を提唱したのだろう。
(2)「監視資本主義」
データ資本主義やコミュニケーション資本主義という見方はともに「情報」が新しい資本主義を牽引する立場に立っている。他方で、ハーバード大学ビジネススクールのショシャナ・ズボフ名誉教授はポスト産業資本主義時代を「監視資本主義」(Surveillance Capitalism)と名づけている。彼女は「監視」という言葉を使って、人間の自由意志を統計上の逸脱・乖離に矮小化することで利益追求を行う「ビッグアザー」に焦点をあてることで人間の内部に向かう資本主義に注目している。この場合でも、監視は情報を介して行われるものであり、その意味では情報に力点を置いている点では、前述した二つの見解と変わらない。
ここではまず、「ソーシャル物理学」なる分野を切り拓いてきたアレックス・ペントランドMIT教授のいう世界が実現に向かっているかのような幻想が真実味を増していると指摘しておきたい(18)。このソーシャル物理学はウェアラブル端末の装着による人間行動のビッグデータ化とその分析などを通じて、すべての人間行動を高度に予測可能にするという「神話」に変換しようとしている。彼は、ソーシャルな現象は実際には個人間の数十億の小さな取引の総計にすぎないとみなし、ビッグデータこそ数百万の人と人の交換ネットワークを通じて、すべて複雑性のなかにあるソーシャルなものを考察することを可能にすると主張している。いわば、「神の目」をもってソーシャルな問題を解決しようというのだ。
問題は、その「神の目」をだれがもつかにある。オーウェルの小説『1984年』に登場する「ビッグブラザー」は「神の目」をもつ存在であったが、ズボフは「ビッグデータ」および「ビッグマス」(Big Math、数学に基づく統計)からなる「ビッグアザー」(Big Other)が「神の目」をもつ存在として登場すると主張している(19)。このビッグアザーのもとでは、人間の自由意志は統計上の一時的な逸脱・乖離として矮小化されてしまう。家の内部にまで監視装置(グーグルホームやアマゾンエコーなど)を張り巡らせ、ベッドでのささやきさえも聞き取ることができるようになり、外出時にはアップルウォッチで心臓の鼓動さえ測定できる。そしてビッグアザーは利益追求を求めて行動する。利益につながるように人間行動を誘導するのだ。そうなると法の支配(rule of law)や民主的な政治といったものが変質してしまう。ビッグアザーが秘密裏に管理する運営体制や新しい形態の主権へと変貌を遂げるのだ。
いわゆる商人資本主義はリアル空間の差異を利用して利潤を得る方法を見出した。産業資本はリアル空間における時間の差異を活用して労働力の商品化によって利潤獲得を可能とした。いずれの資本主義もいわば人間を含む自然を支配する方向にあった。産業資本主義下では、人間の身体の限界を克服するマシーン開発に重点が置かれてきたが、監視資本主義になると、個人や集団などの行動を修正するマシーンが人間そのものを支配する方向に向かう。サイバー空間とリアル空間の融合はこんな事態を実際につくり出しつつある。
監視資本主義は産業資本主義の変容したものだから、両者を比較することで監視資本主義の本質がみえてくる。産業資本主義は、①手工業の、標準化・合理化・部品交換可能性に基づく大量生産への転換、②可動式組み立てライン、③工場環境に集中した大勢の賃金稼得者、④専門化された経営上のヒエラルキー、⑤管理上の権威づけ、⑥機能別専門化、⑦ホワイトカラーとブルーカラーの区別といった専門的分業化を特徴としている(20)。カール・マルクス流に言えば、「労働力の商品化」によって特徴づけられていることになる。
この産業資本主義は国家による「魂」のつくり替えという「全体主義」を一部の国にもたらす。ヒトラーやスターリンは秘密警察による虐殺、プロパガンダの洪水、階級や人種を名目とする残虐行為などを通じて全体主義を広げようとした。オーウェルの『1984年』は、こうした全体主義に対する批判として1949年に出版されたものである。このなかに登場する「ビッグブラザー」は単にあらゆる思考や感情を知っているところにその本質があるのではなく、むしろ容認できない内的経験を無効にし、それに取って代わることをねらった無慈悲な執拗さを本質としている(21)。そして、「独裁者=ビッグブラザー」が君臨するのだ。
ここでウンベルト・エーコの興味深い指摘を紹介しておこう(22)。
「オーウェルの「ビッグブラザー」は、大衆一人一人の行動を逐一監視するきわめて限られた特権階級が実現しているものだった。……(中略)……しかし、オーウェルの物語では、「ビッグブラザー」が「ヨシフおじさん」スターリンのアレゴリーだったのに対し、今日われわれを見つめている「ビッグブラザー」は顔を持たず、しかも一人の人間ではなく、グローバル経済の全体なのだ。それは、フーコーの「権力」と同じように、認識できる実体ではなく、ゲームを承認し合い、互いに支え合う一連の中心の総体なのだ。」
オーウェルのビッグブラザー自身は監視の対象になりえない。だが、エーコの指摘する顔を持たない「ビッグブラザー」は、ある場所では自身が監視しながらも別の場所では自身が監視対象となっている。これを、冒頭で紹介したズボフの監視資本主義では「ビッグアザー」と呼んでいるように思われる。偏在するデジタルな仕掛け(アルゴリズム)という媒介物を通じて実体のない総体の意志を強いるのだ。その仕掛けこそビッグアザーであり、人間行動を表示・監視・計算・修正する、五感によって知覚され、コンピューターによって結びつけられた「操り人形」なのだ。操り人形といってもこのビッグアザーには顔はなく、「権力に顔がなくなるとその権力は無数の力を持つ」という事態を引き起こす(23)。そして、このビッグアザーを中核に据えてその行動を予測して利益につなげるという「行動余剰」(behavioral surplus)が得られるようになる。たとえば、系列の店でなければ修理できないように顧客をロックインして儲けたり(ジョン・ディアのブランドで知られる農業機械メーカー、ディア・アンド・カンパニー)、古いバッテリーのiPhoneの動作を故意に遅くして買い替えを促したりする(2017年のアップルによる隠密裏の行為)方法がそれである。操り人形の行動を精緻化して儲ける仕組みを最優先させるのだ。
この行動余剰を得るには、人間の経験のすべての局面を行動データに「翻訳する」新しいマシーン過程が必要とされている(24)。そのためには、修正・予測・マネー化・コントロールに向けた行動の道具化という現象が起きる。いわば、この道具主義に基づく権力は人間の経験を計量可能な行動に矮小化し、そうした経験に対する「ラディカルな無関心」(radical indifference)を呼び起こす。わかりやすく言えば、この現象は交通信号機の普及によって、ドライバーが対向車のドライバーを見なくなったことに似ている。機械および機械的計算がすべてに優先し、人間には無関心になってしまうのだ。この無関心のために、数十億、数兆ものコンピューターの「目」や「耳」が行動余剰の広大な蓄えを観察・表示・データ化・道具化できているかぎり、ビッグアザーは人間の思考や感情を気にかけない。「ビッグアザーは合法的契約、法の支配、政治や社会信頼を新しい主権形態(a new form of sovereignty)やその私的に統治された、補強物からなる統治形態(regime of reinforcements)に代替させる」というズボフの指摘は重要である(25)。
ここまでの記述を全体主義と道具主義と対照しながら簡略化してみよう。全体主義はビッグブラザーのもと、恐怖や恣意的テロ、殺害、暴力を使って、大衆全体に働きかけ、全体としての所有を重視する一方で、個々人の孤立や原子化をはかり、国家への絶対忠誠・服従を迫る。これに対して、道具主義はビッグアザーのもと、コンピューターによる予測に基づく確実性を重視する一方で、ラディカルな無関心のもと個々人のラディカルな接続をはかり統計的な結果を志向する。結論部分でズボフはつぎのようにのべている(26)。
「3世紀以上もの間、産業文明は人間の向上のために自然をコントロールすることにねらいを定めてきた。マシーンは、我々がこの支配目的を達成できるようにするための動物の身体の拡張や限界克服の手段であった。……
現在、我々は私が情報文明と呼んだ新しい展開のはじまりにあるのだが、それは同じ危険な尊大さを繰り返している。その目標は現在、自然を支配することではなくむしろ人間を支配することである。焦点は、身体の限界を克服するマシーンから、市場を目的とするサービスにおいて個人・集団・全住民の行動を修正するマシーンに移った。」
ここまで説明してもなお、内容が判然としないかもしれない。ズボフの主張を大胆に要約すれば、グーグルやフェイスブックなどのテック・ジャイアンツ(巨大IT関連企業、後述)はデジタル化した情報に基づく行動予測に基づいて行動余剰を得ようとしており、それは自然に働きかけることで剰余価値を得ようとしてきた産業資本主義と異なり、人間自身を観察・表示・データ化・道具化の対象としてとらえ、人間を内部から道具化し、脱主体化しようとしているようにみえる。だからこそ、個人の主体性の一部を構成する自然権を放棄したところに誕生する国家主権そのものも揺らぐことになる。
問題は中国がこの行動余剰を国家自体の手中に収めようとしている点にある。こうなれば、「ビッグアザー=ビッグブラザー」となり、「デジタル全体主義」というかたちでの全体主義が再来しかねないことになる。現状において中国がAI、ブロックチェーン、5G、IoTなどの分野においても国家主導で世界をリードしつつある一方、グーグル、フェイスブック、アマゾンなどもまた最先端技術で主導的な役割を果たしている。ただし、後者は必ずしも米国政府と一体化しているわけではない。本稿ではこうした状況をズボフのいう「監視資本主義」に近い意味をもつ「デジタル資本主義」と呼ぶことにしよう。あくまでAI、5Gなどのデジタル経済を基礎とする新しい形態の資本主義だからである。
(3)「テック・ジャイアンツ」が主導する「デジタル資本主義」
米国のアマゾン、アップル、フェイスブック、グーグル、マイクロソフト、中国のアリババ、テンセント、バイドゥといった企業は「テック・ジャイアンツ」と呼ばれる巨大企業である。2019年3月11日時点の時価総額をみると、マイクロソフトは8780億ドル、グーグルを傘下にもつアルファベートは8320億ドル、アマゾンは8310億ドルだったのに対して、エクソン・モービルは3420億ドル、ロイヤル・ダッチ・シェルは2560億ドルにとどまっていた(27)。ただし、中国のテック・ジャイアンツは中国政府との関係が深い。中国国家情報法により、国営企業であろうとなかろうと企業や個人の諜報活動への支援・協力が義務づけられており、政府と企業が「一心同体」に近い。
これに対して、米国のテック・ジャイアンツは政府との距離が少なくとも中国のテック・ジャイアンツよりも離れている。とくに、エドワード・スノーデンが2013年に米国政府の諜報活動の実態を暴露して以降、テック・ジャイアンツの官民連携の実態が明らかにされた。ゆえに、テック・ジャイアンツは利用者の信頼を勝ち取るため、スマートフォンなどで暗号化を使った末端から末端までの暗号化(end-to-end encryption)を急ぐようになる。
他方で、テック・ジャイアンツは米国で長く保護されてきた歴史をもっている。ここで忘れてならないのは米国ではインターネット関連の会社がそのサービス上にアップロードされた中身に対する法的責任から守られてきたことだ。1996年制定のコミュニケーション品位法(Communications Decency Act)のセクション230で、「双方向のコンピューター・サービスのプロバイダーないし利用者は発行者ないし別の情報内容供給者によって供給された情報の話者とみなしてはならない」と規定されており、第三者である利用者が供給する情報を広めるだけの双方向のコンピューター・サービスを提供する者や利用者は法的責任を免れることができるとされてきたのだ。これは、言論の自由を守るためにインターネット上の訴訟からまだ成長途上にあったフェイスブック、グーグルなどを守ろうとしたものであった。その意味で、それらの会社は政府と「持ちつ持たれつの関係」であったとも言える。
それでも、2018年4月、米国の上院と下院は「性違法商人停止法」(Stop Enabling Sex Traffickers Act, SESTA)と「国家・犠牲者がオンライン性違法取引と闘うことを認める法」(Allow States and Victims to Fight Online Sex Trafficking Act, FOSTA)を合わせたFOSTA-SESTA Actを立法化し、セクション230を修正、性にかかわる違法取引を支援したり、促したりするプロバイダーの法的責任が問えるようになった(28)。
他方で、テック・ジャイアンツは世界的な規模で節税を積極化している。ゆえに各国は国際協調によるサイバー空間活動へ課税、いわゆる「デジタル・タックス」を導入しようとしている(29)。こうしてみると、米国のテック・ジャイアンツは政府との距離をむしろ広げつつあるように思える。それどころか、「テック・ジャイアンツを解体せよ」とのスローガンが民主党の次期大統領候補者の一人である、エリザベス・ウォーレンからあがっている。2020年の米大統領選の結果によっては、「米国政府VSテック・ジャイアンツ」という構図が生まれる(30)。2019年7月12日には、米連邦取引委員会は2016年の大統領選に関連してケンブリッジ・アナリティカに個人情報を遺漏させたフェイスブックに対する処分として約50億ドルの罰金を科すことを決めた。司法省の承認を経て、この巨額の罰金が実際に科される。
なお、EU委員会はテック・ジャイアンツに対しては、以前から厳しい姿勢で臨んでおり、簡単にテック・ジャイアンツが欧州市場を席捲できるわけではない。たとえば、EU委は2016年にアップルの2003~2014年のアイルランドでの脱税に対して130億ユーロ(146億ドル)の罰金を科した。グーグルに対しては、2015年に24億ユーロ(27億ドル)、2018年に43億ユーロ(51億ドル)、2019年に14.9億ユーロ(17億ドル)の罰金を科した。いずれも反トラスト規制に対する違反行為が問題視された。同じく、反トラスト規制違反として、2008年にはマイクロソフトが8.99億ユーロ(13.5億ドル)、2009年にはインテルが10.6億ユーロ(14.3億ドル)、2013年には再びマクロソフトが5.61億ユーロ(7.3億ドル)、2018年にはクアルコムが9.9億ユーロ(12億ドル)を支払った。
(4)「テック・ジャイアンツ」を有利にした法制度
重要なのは、デジタル技術による変革が産業革命をはるかに凌ぐという認識だろう(31)。その変革をリードしてきたのが米国であり、いま現在もテック・ジャイアンツの多くは米国を根拠地としている。その過程で、政府の保護があったことはすでに指摘したが、正確に言えば、新技術が生み出す新しい環境においてテック・ジャイアンツに有利な法的判断や法整備が進んだことがその発展を促したのである。米国議会では、テック・ジャイアンツに対抗する勢力と反対勢力が争いながら、そこでの帰趨が全世界に影響をおよぼすことになったのだ。覇権国米国でのテック・ジャイアンツに有利な法整備が世界中の多くの法律に波及し、それがテック・ジャイアンツの成長を促し、全世界への影響力の拡大につながったと考えることができる。気候変動対策は多国間協力を必要とするゆえに「グローバル・ガバナンス」の重要性を高めたが、テック・ジャイアンツ規制は先行した米国での法規制が全世界に広がるというかたちで進んだ。その意味で、デジタル資本主義は米国をモデルとしている。
米国モデルを支えているのは、技術進歩を追認する「コモンロー」の伝統である。新技術がもたらす新しい環境に対する法規制なしの発展が先行し、問題が生じれば裁判に問う繰り返しのなかで、法的規制が整備される。たとえば、グーグルは米法にある「フェアユース規定」(フェアユースと認められる著作物の利用に著作権といった権利がおよばないとする一般的権利制限条項)を利用して、全世界のサイトを無断に複製して検索エンジン・ビジネスをはじめ、異議があれば削除するというオプトアウト方式をとった。これに対して、日本では、他人のサイトを無断で複製すると権利侵害になるとして、承諾のあるサイトだけを拾うオプトイン方式を採用せざるをえなかった。いわば、「シヴィルロー」の伝統にしたがって慎重に対処したわけだが、結果として、グーグル検索の精度の高さや利便性が圧倒的な成功をおさめた。その結果、日本もグーグルの「やり口」を認めざるをえなくなる。
2000年代はじめまで、人類は本も音楽も映画も手でもてる物的対象として相互に影響し合う関係にあった(32)。映画を映画館やビデオで観たり、音楽をラジオやテレビで聴いたりする場合でも、著作権保持者は映画のリールやテープなどの触ることのできる有形のコピーを売却することでビジネスに従事していた。2003年にアップルがiTunes Music Storeをはじめると、有形のコピーから手に触ることのできない無形のデジタルコピーの販売がビジネス化され、著作権者に脅威をおよぼすようになる。いまでは、デジタルコピー、ダウンロード、クラウドといったかたちでのビジネスに代わって、毎月低料金で大量の本・音楽・映画にアクセスできるストリーミングサービスが急速に広がっている。
デジタル化という技術的変化の過程で、米国の法体系、立法、裁判所の判決は総じてテック・ジャイアンツに有利な結果をもたらした。とくに問題になったのがデジタル権管理(Digital Rights Management, DRM)である(33)。DRMは、消費者が著作権保持者、装置メーカー、小売業者、その他の仲介者によってなされる、本、映画、音楽、その他のデジタルコンテンツを利用できるかどうかや、どのようにどこでいつコントロールするかをデザインする技術範囲を意味する婉曲表現だ。前記のiTunesサービスを開始する際、アップルは使用ルールのなかでDRMによる制約を説明し、①利用者は非商業目的の個人向け利用だけの権限をあたえられている、②利用者はいかなるときでもiTunesが権限をあたえた五つの装置においてiTunes生産物を利用する権限をあたえられている、③利用者は7回までオーディオ・プレイ・リストを聴く権限をあたえられている――などを規定している。
この規制は法律に基づいているわけではない。つまり、法律制定に関する過程を経てつくられたものではない。これはエンド・ユーザー・ライセンス協定(end user license agreement, EULA)であり、小売業者や著作権者に有利になるように個人の権限を制限しようとしている。DRMを行う側は、利用者がデジタル製品を貸したり、修理したり、再販したりするのを厳しく制限し、コピーによる著作権侵害といった損失を防ごうとしているのだ。
たとえば、アナログ時代のビデオ・カセット・レコーダー(VCR)は著作権者である映画制作会社のユニバーサルやディズニーをVCR禁止法案制定に突き動かしたが、失敗し、1984年にVCRメーカーの一つ、ソニーへの訴訟に発展する。しかし、米最高裁判所はVCRのデザインと利用に法的規制を課しただけで、VCRの販売自体は認められた。1996年にDVDが導入されるようになると、コンテント・スクランブル・システム(CSS)と呼ばれるDRMシステムが登場する。DVDのコンテンツを暗号化することによって、DVDを楽しむためには、権限をあたえられた装置だけが利用可能となる秘密鍵が必要となったのだ。こうしてCSSは著作権者の権限を強めることになった。しかし、ライセンスを受けたDVDの秘密鍵が見つかると、1999年にCSSは解かれてしまう。こうした混乱の過程で、1992年にオーディオ・ホーム・レコーディング法(AHRA)が制定される。デジタル・オーディオ・テープ(DAT)の発明がデジタルコピーにつながったため、DATのプレーヤーメーカーに著作権侵害の免責を認める代わりにすべてのDATプレーヤーにDRMのためにシリアル・コピー・マネジメント・システム(SCMS)を装填することを求める規定が盛り込まれた。SCMSは追加コピーが可能かどうかを指示する、DAT記録にあるデータを暗号化するシステムで、レコード会社はたとえばコピーをいっさい禁止できる。
より重要な意義をもっているのは、1998年制定のデジタル・ミレニアム・著作権法(Digital Millennium Copyright Act, DMCA)である。1996年12月成立の世界知的所有権機関(WIPO)の著作権条約などに米国内法を適合するために著作権法改正が行われた結果だ。追加された重要な規定として、著作権で保護されたものへのアクセスを制限するあらゆる技術的措置を回避する(迂回・無力化・除去する)ことを不法とし、DRMを破ること自体が処罰の対象となったことで、著作権者の立場が強化された(34)。また、検索エンジンやインターネットサービス供給者(ISP)のような仲介者の責任などが明確化されたことも、テック・ジャイアンツを利するものとなった。たとえば、DMCAによってDVDのコンテンツの暗号を解読するDeCSSは禁止されたし、権限のない装置では楽しむことのできないiTunesの音楽は事実上、いわばアップルの「独占販売価格」を可能にし、その巨大化を促した。
忘れてはならないことはこのDNCAの立法趣旨が日本をはじめとする多くの国々で採用されたことである。覇権国たるアメリカのデジタル規制が世界の雛形となり、それがテック・ジャイアンツの世界的隆盛につながるのだ。ほかにも、2014年8月、11万4000件もの請願への対応策として当時のバラク・オバマ大統領はUnlocking Consumer Choice and Wireless Competition Actに署名した。DMCAが禁止していた、ISP変更時に携帯電話のソフトウェア向けコピー保護メカニズムを回避することを合法とするもので、携帯電話支払い後にISPを変更しやすくなる。この変更も、日本の携帯電話販売方式の見直しにつながっている。
その後、IoTにおいても、DMCAに保護されながら、デジタル技術がますます利用されるようになる。たとえば自動車メーカーはデジタルに基づくコントロール・ユニット・コードをDRMのもとで利用し、通告や承諾なしに遠隔操作によっていつでもデジタル情報をアップデートしたり削除したりすることが可能となる。IoTはいわば、テック・ジャイアンツと既存の大規模メーカーとの競争を促す。
問題は、DRMを利用者に縛るライセンスが決して契約ではないのではないかという点である。ライセンスは「許可の純粋な譲渡」(pure grants of permission)とみなすべきものではないか(35)。なぜなら現実には、だれもEULAにしっかりと目を通さないのであり、その内容も一般人には理解しにくいからである。米国の裁判所の判例をみると、依然としてライセンスを契約とみなし、テック・ジャイアンツに有利な判決が出るケースが多い。だからこそ、米国のテック・ジャイアンツは利用者の権利を侵害することで利益を得やすいのだ。
こうしたテック・ジャイアンツに都合のいい米国の制度は決してそのまま世界全体に受けいれられているわけではない(36)。こうした制度がどうなるかがデジタル資本主義の帰趨を決める要因の一つになるだろう。
3. 地政学の新展開
(1)「信頼」の変遷
「デジタル全体主義」と「デジタル資本主義」の将来を考えるために、ここでは両者を支えるデジタル経済の基盤となる「信頼関係」の変遷について人類史の立場から論じたい。すでに拙著『サイバー空間における覇権争奪』のなかで、「信頼」が「神信頼」から「人間信頼」、さらに「国家信頼」へと変化してきたことを論じた(37)。デジタル経済のもとでは、「ネットワーク信頼」や「マシーン信頼」が支配的になるのではないかとの自説も展開した。とはいえ、信頼そのものについて深く探究したわけではない(38)。ここでは紙幅の関係から、このネットワーク信頼やマシーン信頼を中心に検討したい。
(A) 神信頼から人間信頼へ:アイディール思考からイメージ思考へ
フランシス・フクヤマは、信頼が個々人のアイデンティティ(自己認識)と深くかかわっている点に注目して、アイデンティティを感じるには、①他者に認証されるという渇望、②内側の自部と外側の自分を区別して外部社会に対して内部の自分を位置づけること、③尊厳――が必要であるとしている(39)。これらの条件によって個々人がなににどの程度の信頼をいだくかが決まってくるのではないか。
筆者は拙著『サイバー空間における覇権争奪』の終章の註(18)において、あえて長大な注釈を書いた(40)。自然、神、人間の関係が哲学的にどう位置づけられてきたかを論じたのである。この考察からわかるように、人類は長く神によって認証されることを渇望し、神の決めた統治システムのなかで自らの尊厳を感じようとしてきた。だが、「内側の自部と外側の自分を区別して外部社会に対して内部の自分を位置づける」ことには熱心ではなかった。すべてを神に委ねてきたからである。ゆえに「神信頼」の支配的な時代には、他者に対する信頼よりも神と人間との間の信頼関係が優先された。だからこそ、神の「スチュアード」たる教会のような機関が信頼を集め、統治機関としての役割を果たすことができたのだ。もちろん、一神教、多神教の差もあれば、天命に支配された中国のようなケースもあったから、一般論を展開するのは困難だが、ここではこうした大雑把な議論にとどめることで先を急ごう。
フクヤマは、人間の内と外に区別を見出し、主体としての内部に重きを置く見方を可能にした西側初の思想家の一人がマルティン・ルターであるとしている(41)。これは実は、ダニエル・ボースティンがその著書『イメージ』のなかで、「アイディール思考」から「イメージ思考」への変化が「グラフィック革命」によって促進されたと主張したことに関係している(42)。アイディールは無矛盾のつくりごとではない状態を意味する。人間は自らの見方や考えを神に仮託して神のつくり出した秩序らしきものに従属させることで、神の命じる秩序を完全であるかのように受けいれていた時代の思想こそ、アイディール思考であり、そこでは信用できるかどうかは問題にされていなかった。アイディールは無矛盾の完全な状態としてすでにあるものであり、キリスト教徒にとって受けいれるべきものとしてあったのだ。
そのアイディール思考を覆したのが「イメージ思考」である。イメージはあらゆる対象の外部形態の人為の模倣ないし代理物であり、イメージは人間によって生み出される。そのとき、人間は外部を模倣し、内部にイメージをつくりあげ、外部にそのイメージを転写する。まさにイメージは、人間の内部と外部の区別が見出される契機として重要な役割を果たしたのだ。イメージは模倣や代理物である以上、その真偽が問題にされるようにもなる。ゆえに、信じるかどうかという場面に人間は数多く出会うようになる。ここに、「神信頼」の支配的な時代にはなかった、新しい信頼を構成する要素が発現するのである。それが、前述したアイデンティティを感じるための②の条件ということになる。それによって、現在にまで通じるアイデンティティを感じる3条件がはじめて整う。それは、「人間信頼」という、神ではない人間を他者として強く意識する視角を研ぎすませるのだ。
(B) 人間信頼から国家信頼へ:文化の複雑化
人間の内部と外部の区別をもっとも明確に示したものは写真術であろう。絵画は人間の内部のイメージを外部に転写し、外部に似せて描き出すことはできたが、人間の目は光を介して網膜に映し出される像を脳が認知する仕組みのなかで、絵を「本物」と感じることはできなかった。しかし、写真術によって本物を見出す感覚を得ることが可能になったことで、人間の内部と外部に差があることをまさに目の当たりにするのである。本稿の註(3)に記述したように、19世紀の写真術は対象を視角的に固定し客体化するもので、それは見る側と見られる側を主体と客体に峻別することを前提にしている。ここに、「リアル空間」がはじめて登場するのだ。このリアル空間は人間の内部と外部の区別を前提に、よりリアルに見えるものを信頼する傾向を育む。いわば、人間の五感のなかで、目が特権化するのだが、だからこそその目に訴えることになる「グラフィック」の役割が高まり、それがイメージ思考をさらに深化させたのだ(その後の映像技術やサイバー空間への経緯については註(3)参照)。
こうした技術的変化は人間の統治を円滑化する方法に大きな影響をおよぼした。アントニオ・グラムシは、社会が「支配」ないし「力」および「ヘゲモニー」の組み合わせを通じてその安定性を維持していると考えたことを思い出そう。このとき、ヘゲモニーは「知的・道徳的指導権」への合意と定義された。社会秩序は社会的境界線とルールを維持するために暴力的に権力や支配を執行する機関・集団(警察、軍隊、自警集団など)と、ヘゲモニーの創出を通じた支配的秩序ないしイデオロギー的支配(市場資本主義、ファシズム、共産主義など)への合意を説く機関(宗教、学校、マスメディアなど)によってつくり出され、また再生産される。前者は近代国家の合法的暴力装置となり、後者は義務教育やマスメディアを通じた文化による支配につながっている。ミッシェル・フーコー流に言い換えれば、国家の主権化は、規律を特徴づけている権力の手続き、すなわち処刑としった暴力に基づく「人間の身体の解剖学的政治学」(解剖-政治学)と、人間の繁殖・誕生、死亡率、健康水準などに介入し管理する、「人口の生に基づく政治学」(生-政治学)から構成される。いずれの場合でも、二つをともに支配下に置く主権国家の登場こそ、人間信頼を新たな局面に向かわせる。
主権国家の誕生については拙著ですでに論じたことがある(43)。そのためここでは、トマス・ホッブズの社会契約論だけを確認しておきたい。人間には神のつくったままの自然状態において、自然権、生存権、幸福追求権があり、それらを無制限に主張しかねない。万人の万人のための戦争になりかねない。これを避けるには、人間の自由意志に基づいて、自ら自然権を放棄したり制限したりすることが必要になる。この人間間の契約を守るには、統一された合議体が不可欠となる――という論理展開をたどるのがホッブズの社会契約論だ。ホッブズは、自分たちの人格を担わせ、その合議体による行為を自らの意志として認めることによって、群衆が一人格に統一されたかにみえるようにすることで平和と安全を維持できると主張する。この統一された人格こそ、「コモンウェルス」と呼ばれる。その人格を担う者は主権者と呼ばれ、主権者権力をもつとされる(44)。ここに、彼は怪物リヴァイアサン(Leviathan)、すなわち「可死の神」(deus mortalis, mortal God)をみている。神はふつう、永遠で不死を特徴とするが、「巨大な権力」の象徴としてのリヴァイアサンは国家の魂の部分であり、国家自体は保護を実現する機械と化す。その意味で、それは朽ちる可能性を排除できない。ゆえに、国家は神のようでいながら、神と異なり、死ぬのである。
つまり、人間の自然権の譲渡先として現出したのが主権国家ということになる。しかも、その国家は「可死の神」として神のような存在となる。それだけ人間は国家を信頼していることになるのだが、国家はそのように人間を信じ込ませるメカニズムを構築する。それが義務教育であったり、生-政治学に基づく「生-権力」の行使であったりするのだ。それは、国家語の制定を基礎とし、その国家語を通じて国家が歴史を教育し、国家への信頼を醸成する。国家は家族、会社、学校などの集団をも国家統治に利用し、きわめて複雑な制度でがんじがらめの近代国家をつくり出す。その結果、各国の文化はアイディール思考が支配的であった時代に比べて差別化される。とくに、国家語は「ネーション」という概念と結びついて、各国ごとに普遍性を帯びているかのような誤解を生み出す。それが、文化の複雑化と他文化への不寛容となって、国家間の対立につながるのだ。
他方で、国家を担う代理人を選挙で選ぶというのが民主主義であり、その民主主義に基づく統治もまた人間信頼の方向性を国家に向かわせる。代理人になるために、選挙で勝利するには、イメージ思考をするようになった人々をうまく説得して一定の考え方に誘導することが求められるようになる。つまり、情報操作によってイメージという、曖昧なものの見方に働きかけて、統治者の有利になるような仕組みをつくり出すことが全体の円滑な統治に不可欠になったわけである。そのために、重要な役割を果たすようになったのがマスメディアだ。グラフィック革命によって誕生した新聞やラジオ・テレビなどである。そこには国家とマスメディアとの共謀関係が存在し、「合意のでっち上げ」という現象が生ずる(45)。
こうして人間信頼は再び神のような存在として登場した国家への信頼へと傾く。それを可能にしたのは、アイデンティティを感じるための②の条件であった。他者に認証されるという渇望も尊厳も、人間が外部に向けて心を開いたり、信頼を寄せたりする大前提だが、「内側の自部と外側の自分を区別して外部社会に対して内部の自分を位置づける」には、外部環境に左右されざるをえない。その外部環境が国家によって牛耳られ、国家に有利なように条件づけられてしまうと、もはや国家を信じることが当然視されるようになる。ここに、国家信頼の強制という作用が働いているのだが、その国家信頼の強制に気づくことができるのは、国家によって尊厳を傷つけられていると感じることができるような「サバルタン」と呼ばれる、社会・政治・経済・地理的に阻害された従属者だけであったのかもしれない(46)。
ここで、ニクラス・ルーマンが「人格的信頼」と「システム信頼」を区別したことを思い出そう(47)。とくに、注目されるのは人に対する信頼以外に、システムに対する信頼を想定したことだ。このシステム信頼は「象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディア」(Symbolically Generalized Communication Media, SGCM)に対する信頼を意味している。具体的なSGCMとして、経済システムにおける「貨幣」、科学システムにおける「真理」、政治システムにおける「権力」が想定されている。貨幣、真理、権力はシステムを支える仲介役を果たすメディアとして機能することになる。このとき、システム信頼は「内側の自部と外側の自分を区別して外部社会に対して内部の自分を位置づける」というアイデンティティの条件に即して、国家によって整備された外部環境を前提に構築される。貨幣は国家鋳造を前提に中央銀行によって管理され、真理は国家語を通じて各国のアカデミーや審議会などで統制され、権力は各国の民主的制度などによって規制される。このとき、国家は「無意識」のレベルにおいて神のようにふるまい、信頼を得ているのだ。これは、いわば「信仰のレベルが百パーセント無意識のレベルに移行している」ことを意味している(48)。ゆえに、国家信頼は無意識のレベルで息づいているとみなすことができる。
(C) 国家信頼からマシーン信頼・ネットワーク信頼へ:文化の溶解
デジタル経済を支える先端技術の一つ、ブロックチェーンがこれまでの信頼関係とは違う信頼関係を醸成するところから論じたい。ペンシルヴァニア大学のケヴィン・ウェアバック著『ブロックチェーンと信頼の新しいアーキテクチャ』によれば、一般に信頼は、①仲間同士のネットワーク、②社会契約のような意思決定メカニズム(近代思想家のホッブズが『リヴァイアサン』において主張したように、人間には神のつくったままの自然状態において、自然権、生存権、幸福追求権があり、万人の万人のための戦争になりかねないが、これを避けるには、人間の自由意志(ここでは意志と意思を区別しない)に基づいて、自ら自然権を放棄したり制限したりすることが必要で、この人間間の契約を守るには、統一された合議体が不可欠となるという社会契約論に基づく)、③仲介者――という三つによって構築されてきた(49)。しかし、ブロックチェーンはこれらを必要としていない。ブロックチェーンに参加する者を仲間として信頼しているわけではまったくないのだ。ブロックチェーンを支えているのはネットワーク自体にすぎない。取引を有効にしているのは、暗号化された取引が数学的に証明できることを暗号とアルゴリズムが支えているからなのだ。これらに対する信頼だけがブロックチェーンの生命線なのである。
これが意味しているのは、政府への信頼が崩れつつあり仲間や仲介者への信頼感も薄れつつある世界だからこそ、ブロックチェーンが新たな信頼醸成システムとして急速に広がる可能性を秘めているということである。だが、それはマシーンに裏づけられたネットワークへの絶対的信頼を招来し、人間同士の関係によからぬ影響をあたえる可能性を秘めている。ブロックチェーンもアルゴリズムというソフトウェアへの信頼をもとにしており、そのアルゴリズム作成のためのマシンラーニングは人間が解釈したり検査したりしがたい抽象的で統計的な相関に基づいている。ゆえにブロックチェーンを礼賛するのは危険なのだ。
もう一つの危険性はブロックチェーンを政府が推進し、分散型システムとしてではなく、「脱仲介者化」のために活用可能である点にある。中国政府はすでに指摘したように、こうしたやり方でブロックチェーンを積極的に利用し、政府が直接国民を統治することで中国共産党の独裁体制の堅持をはかろうとしている。前述したルーマンのいうSGCM(経済システムにおける「貨幣」、科学システムにおける「真理」、政治システムにおける「権力」)はあくまで仲介役を果たすメディアにすぎないから、脱仲介者化をブロックチェーンが果たす以上、ブロックチェーンの利用が広がれば、SGCMへの信頼を意味するシステム信頼もまた揺らぐことになるだろう(50)。
中国共産党の思惑がどうあろうと、技術変化は既存の制度を破壊する力をもっている。人々を結びつける紐帯はいま、家庭、学校、会社、国家からネットワークだけに限定されつつある。スマートフォンでつながっているだけで、それが個々人の存在確認につながっている。しかも、ITの発達で、もはや「マス」を前提とする大量生産ではなく、個々人の特性・嗜好に合わせた「少量多品種」どころか「個別生産」さえ可能な時代になりつつある。ネットワークにアクセスしているだけで、それが逆に個々人の個別化・断片化を促すのだ。この変化は一人ひとりの人間への尊重、人権に普遍性を見出そうとする視線を刺激する。性差別やLGBT差別へのまなざしはその反作用として個々人の大切さを訴える。個々人の大切さは、統計による標準化を通じた普遍化に傾く。この普遍化と個別化の相互作用は、いわば、一人ひとりの人間を聖なる地位に置く。そして、それが家庭、学校、会社、国家における紐帯を緩める。ひきこもり、各種いじめ、貧富の格差の増加はこの変化に対応している。これらを裏で支えているのがネットワークであり、それへの依存がネットワーク信頼を余儀なくさせるのである(51)。「内側の自部と外側の自分を区別して外部社会に対して内部の自分を位置づける」というアイデンティティの条件の重要性が薄れるために、ネットワークにすがって自分のアイデンティティを感じるしかなくなると考えることができる(52)。このとき、「内側の自部と外側の自分を区別して外部社会に対して内部の自分を位置づける」というアイデンティティの条件の重要性が薄れる以上、無意識のレベルで神の地位にあった国家への信頼は確実に揺らいでいる。つまり、ルーマンのいうシステム信頼はもはやその信頼性に疑問符が投げかけられていることになる。
ここでの話はヘゲモニーを「知的・道徳的指導権」への合意と定義したグラムシの思想に関連している。伝統が培った生活慣習を「歴史的堆積物」と呼び滓(おり)とみなしたうえで、彼はそれが簡単に溶け出すことを予測していた。政治・経済・地理的に阻害された従属者、「サバルタン」がサバルタンでなくなると、これまでの文化の古い鎖を溶解してしまうのだ。その結果日本でも米国でも、あるいは中国でも古い文化は着実に廃れている。
(D) マシーン信頼・ネットワーク信頼
ネットワーク信頼は同時に、そのノード(結節点)たる「マシーン信頼」に支えられている。マシーン信頼はAIの進歩を前提としている。AIそのものは計算手順である一定のアルゴリズムにしたがって動く。そうであるならば、そのアルゴリズム自体は何で成り立っているかというと、それは確率的因果論に基づく統計に基づいて設計されている。これはフォン・クリースによって発明された適合的因果構成論の現代版を意味している。佐藤俊樹によれば、適合的因果とは、「ある一定の原因的契機が、ある結果の可能性を増大させること、この契機が存在する場合、その結果はそれがないときよりもはるかに多様な状況において実現されること」を意味している(53)。このアプローチは統計的に因果関係の推論の是非をより信頼できるかたちで提供してくれるので、因果関係の特定に役立つ。
しかし、だからといってあくまで有限の観察から因果を推定するしかない以上、たとえビッグデータに基づく確率的因果論がはじき出す数値であっても、それが観察者による事後的な独断的判断となる可能性を排除していない。つまり、大いに疑わしいのだ(54)。
独断的判断は人種的偏見だけでなく、さまざまな差別意識に基づいている。リスク区分という考え方によって、同じ人間でありながらリスク評価基準の吟味なしにさまざまなリスクが独り歩きするようになっている。たとえば、男女に平均寿命の差がある以上、長生きする女性の年金保険料を男性より引き上げるべきだとか、黒人居住区の犯罪発生率が高い以上、そこに住む黒人の損害保険料を高くすべきだといった議論が可能となる。しかし、保険はもともと互いに保険に入ることでリスクを分かち合い、お互いの結束を強め、相互扶助の精神に基づいてリスク自体を減らすという効果をもつものとして構想された。リスクを安易に切り分けて、そこに統計を持ち込んで「公正」を理由にアルゴリズムを作成すると、AIが歪んだ結果を人間に強いることになりかねない。
独断的判断が紛れ込む余地は数値化自体に起因している。感情さえ数値化し、デジタル化してデータの収集・保管・分析を迅速かつ効率的に行うことが当たり前になりつつある。病院、学校などの運営・管理にもこうした数値が客観性を装う道具として政府などの統治機関によって利用されている。根拠のある数値でなくても、それが比較のための道具として広範に利用されるようになると、人々はその数値や数値に基づく分析結果を信じるようになってしまう。こうした素地があったからこそ、数値化と統計をもとに作成されたアルゴリズムに基づくAIが客観性をもつかのように誤解されてしまいがちなのだ。そして、その誤解に気づかれないままにマシーン信頼が確固たるものになりつつあるというのが現状である。
これまでは国家信頼のもとでこそ、統治機関としての国家がアルゴリズムを利用することがかろうじて可能であったと言える。しかし、国家信頼は大きく揺らいでいる。そこでも、グラムシの主張が関係している。彼が注目されているのは、グラムシを源流とする「左翼思想」が米保守主義の代替として登場した「オルタナ右翼」(Alt Right)に取り入れられ、トランプ政権誕生の原動力となったためである(55)。グラムシは常識と翻訳されることの多い“common sense”(イタリア語で“senso comune”)にスポットを当てた。このとき彼が力点を置いたのは“common”の側であり、そこで重要なのは集団的で社会の有力な要素となった意見の総体であり、ラディカルな変革をもたらしうる政治運動を動員する「知恵」なのだ(56)。とくに、サバルタンのような人々に働きかけ、彼らにとっての「真実」をグラムシのいう“common sense”として提示し際限なく繰り返すことで、彼らに“common sense”として受け入れてもらえれば、彼らの支持は絶大となる。このとき、真実に基づく論拠はいらない。
このやり方こそ、トランプの手法なのである。問題はその彼が大統領に就任したことで国家自らが信頼を損ねる行為を繰り返していることだ。弱体化しつつあるとはいえ、覇権を握る米国がこのあり様なために国家信頼は急速に衰えている。トランプのやり方を模倣する政治家が増殖する一方で、国家信頼を支えてきたマスメディアは「フェイクニュース」と揶揄されて力を失いつつある。そこに、ネットワーク信頼やマシーン信頼が入り込む。
国家信頼の衰退は「内側の自部と外側の自分を区別して外部社会に対して内部の自分を位置づけること」というアイデンティティを感じる条件を多いに毀損する。その結果、内部集団と外部集団との信頼関係も崩れる。それが、肌の色、宗教、国籍、性別などの差の違いを際立たせ、いわゆるナショナリズムやレイシズムを刺激するようになる。すでに指摘したように、これはルーマンのいうシステム信頼への疑問を深めることにもつながる。無意識のレベルにあっても、国家を信じることがなくなるのである。むしろ、人権のようなより普遍的な価値観が国家を超えた価値として無意識レベルの「信仰対象」となるのだ。
これまで支配的だった国家信頼が後退するにつれて、統計に全面的に支えられたマシーン信頼が支配的となる時代が訪れるだろう。統計への信頼が揺らぐのではなく、その信頼が「国家」から「マシーン」に移行するのだ。マシーンは統計という国家よりもより普遍的な価値をもつものとして無意識のレベルで優勢になるのである。
そのマシーンを主導的に操るのがテック・ジャイアンツということになる。そこで重要なのは、テック・ジャイアンツの急成長が前述したDMCAで規定したDRM保護に起因していることだ。そのDRMは顧客や利用者を信頼していない(57)。だからこそ、DRMによって「購入」したはずのものであっても、監視の対象とされ、貸し出しや再販・修正などが禁止されたりしている。つまり、テック・ジャイアンツは利用者や消費者への不信に基づいて急成長したと考えることができる。逆に言えば、利用者や消費者にとってテック・ジャイアンツは必ずしも十分に信頼するに足りない。個人のプライバシー侵害やディスインフォメーションをめぐる一連の事件によって、その信頼は地に堕ちたとさえ言えるかもしれない。それでも、マシーンやそれらをつなぐネットワーク自体への信頼は残存している。だからこそ、その利用者は拡大しつづけているのである。ただし、マシーンが人間のために働く一方で、人間がマシーンのために働く二極化は避けられないのではないかという根源的な問いが待ち受けている。
(2) 新しい地政学の視角
(A) 国家信頼の脆弱性
すでに世界全体の統治を意味する「グローバル・ガバナンス」の重要性は広く知られている。しかし、主権国家の集団を基本とする国際連合のような国際機関はあくまで国家信頼を前提にする組織にすぎない。その際、民主国家はその構成員らによって合意された信頼のもとに運営されてきた点が重要だ。重要なことは、これをブルース・シュナイアーらは「共通政治知識」(common political knowledge)と呼んで、それが民主国家を支えていると指摘している(58)。これに対して、権威主義的で独裁的な国家では、「異議申し立て可能政治知識」(contested political knowledge)という、その構成員が不同意であるにもかかわらず、恐怖や脅迫で上から押しつけられた「知恵」のようなものが広がっているとみなす。問題は、後者からの前者への「意図的で不正確な情報」を意味するディスインフォメーション(意図的で不正確な情報)による攻撃と、前者から後者へのディスインフォメーション工作を比べると、信頼に基づく共通政治意識が受ける打撃がずっと大きいという点である(59)。
これは、コンピューターそのものの国民への浸透度が低い北朝鮮、中国、ロシアのような国へのディスインフォメーション工作の効果がそれらの国々による米国へのディスインフォメーション効果に比べてずっと低いことに似ている。信頼関係が醸成されていない、「異議申し立て可能政治知識」が広範囲にくすぶっている国にディスインフォメーションを仕掛けても、その情報自体が疑われ、胡散臭く感じられてしまうのだ。これに対して、共通政治知識を基盤とする国では、ディスインフォメーションによってその信頼関係が崩れやすい。しかも、いまのトランプ政権のように、民主国家がその国内でディスインフォメーション工作を行うようになると、ますます国内の共通政治知識が毀損され、分断や亀裂を深めることになる。このため、米国における国家信頼の毀損による痛手は中国よりもずっと大きい。
それでも、中国への国家信頼は強固なものとは言えない。政府が推進する社会信用体系の構築は中央集権化を促す側面とともにマシーン信頼をより強固にする。いつまでも国家信頼が揺らがないと考えるのはあまりに短絡的ではないか。無意識のレベルで神とふるまうことで、貨幣、真理、権力などの社会システムを支えてきた国家はもはやその信頼を統計というより普遍的な価値規準にその首座を奪われつつあるのではないか。
ここまで説明してきた歴史認識に立つと、紹介したアグニューの結論部分に倣って言えば、「明らかだと思われることは、限定された領域に基づいて競争し合うという見地から地政学を捉えてしまうと、生起してきたことをほとんど、あるいはまったく捉えることできない」と言えそうだ。サイバー空間がリアル空間にどんどん融合するにつれて、領土といった物理的空間のもつ意義が低下する(宇宙については上昇する)(60)。国家信頼の低下、マシーン信頼やネットワーク信頼の向上はテック・ビジネスの世界全体への影響力を拡大する。
(B)「テック・ジャイアンツ」の動向
ITの技術発展が世界におよぼす影響は甚大だ。そうした観点から、ITが個人、会社、産業、国家といった「ソーシャル」な関係全体におよぼす影響にまで目を向けなければ、地球全体の覇権をめぐる地政学的な分析は「現実」を反映できないのではないか。これまでの地政学は国家に重点を置いてきたが、いま必要なのはITで主導権をどんな主体がもつかに関する考察である。テック・ジャイアンツの動向、それらの間の競争、それらと国家との関係といった視角こそ、新しい地政学には必要となるだろう。
現在、「テック・ジャイアンツ」間の激しい競争が展開されている。米国のグーグル、アマゾン、フェイスブック、アップル、マイクロソフトなどだけでなく、中国のアリババ、テンセント、バイドゥなども世界中で競争関係にある。最近では、動画コミュニティ・アプリ、ティクトック(TikTok)を中国外で、抖音 (Douyin)を中国国内で運営するバイトダンス(ByteDance)が急拡大をみせている。
グーグルと言えば、検索エンジンサービスから成長した会社で、広告収入が収益源だが、すでにアマゾンが急追している。2015年、製品を探している人の約54%がグーグル、46%がアマゾンのサイトからスタートしていたが、2018年までにその割合は逆転したとみられている(61)。アマゾンは商品販売サイトを運営している以上、広告分野での収益拡大をはかっているのだ。これに対して、グーグルは2019年5月14日に開催されたマーケティング会議で小売販売に力を入れることを明らかにした。
グーグルはアマゾンのマーケットプレイスに似た「グーグル・エクスプレス」というサイトを運営している。その支払いは「グーグル・ペイ」を通じてできる。アマゾンはクレジットカード決済を中心に発展してきたために、「アマゾン・ペイ」はあってもアマゾンのアカウントに登録されているクレジットカード情報を使用して、アマゾン・ペイに対応している他のサイトで商品やサービスの支払いができる程度だ。アマゾンは2018年にオンラインで2770億ドルもの商品を販売したが、これに比べると、グーグル・エクスプレスの売り上げは微々たるものにすぎない。広告については、アマゾンは年間108億ドルを売り上げたが、世界の広告市場はこれまでグーグルとフェイスブックが席捲してきた。一方、グーグル・クラウドはクラウド・コンピューティングの分野でもアマゾン・ウェブ・サービスに挑戦しようとしている。他方で、グーグル傘下にあるユーチューブに対抗して、アマゾンはツイッチ(Twitch)を2014年に買収し、オンライン・ビデオ分野で競合関係にある。
最近注目されているのは、フェイスブックが推進する「リブラ」(Libra)と呼ばれる暗号通貨プロジェクトである。同社は2019年4月中旬、スイスに暗号通貨、リブラを登録した。フェイスブック利用者のフェイスブック上および他のウェブサービス経由での決済のために暗号通貨だ。同社子会社、Calibraは2020年はじめにもリブラの運用を開始する。リブラはマスターカードやウーバーを含む大企業や金融会社、27社に支援されており、世界の主要通貨を混合した金融準備金によって裏づけられている。これまでクレジットカード会社が担ってきた決済サービスなどを大きく侵食する可能性がある。アップル・ペイ、グーグル・ペイ、アマゾン・ペイなどへの宣戦布告でもある。
アップルが進めている独自の認証機能、Sign In with Appleはフェイスブックやグーグルに打撃を与えるだろう。2019年秋以降、同サービスがはじめれば、供与してほしいサービスごとに新たにユーザー名やパスワードを設定する必要はなくなり、すべて単一のアップルのアカウントですませることができる。ゆえに、サービスごとにクレジット番号のような重要情報を入力することもない。これは、これまで電子メールなどでユーザーとつながってきた企業とユーザーとの直接的関係を分断することを意味し、アップルはユーザーと企業との仲介者となることでアップル自体の影響力を強めることになる。ただ、広告業で儲けてきたグーグルやフェイスブックは企業が望まないであろう、独自認証への移行を進めるとは考えにくい。その意味で、アップルのこの独自認証戦略はグーグルやフェイスブックとの競争に重大な影響をおよぼすはずだ。加えてアップルは2019年3月25日、新しいビデオサービス(アップルTVプラス)を秋に100カ国以上ではじめるほか、アップル・ニュース・プラスで300もの雑誌情報の提供や、クレジットカードサービスも開始すると発表した。
フェイスブックはこの中国のテンセントが運営するウィチャットのビジネスモデルを模倣して、フェイスブックの運営するワッツアップ(WhatsApp)経由での電子決済(WhatsApp Pay)をインドで試験中だ。アマゾンもアマゾンペイ(Amazon Pay)をインドで広めようとしている。フェイスブックには暗号通貨発行によってそれに基づく決済とする計画もある。同社が導入を計画する暗号通貨、Libraは各国為替レートに固定したレートで利用するもので、ブロックチェーン技術のためのソフトウェアやインフラの開発のための一歩でもある。
今後、ますます需要が高まるとみられるのが、「ヴァーチャル・アシスタント」と呼ばれる、秘書のようにさまざまな機能を果たすサービスである。その分野では、アマゾンのアレクサ、グーグルのグーグル・アシスタント、アップルのシリ、マイクロソフトのコルタナ、サムソンのBixbyなどが競争を展開している。フェイスブックも巻き返しをねらっている。
興味深いのは、光ファイバー網へのテック・ジャイアンツの投資である。グーグルは2018年10月、フランスの通信会社オレンジとともに、2020年の完成をめざして米仏を結ぶ全長6600キロメートルの海底ケーブル「デュナン」(赤十字の創設者アンリ・デュナンにちなんで名づけられた)を大西洋に敷設する計画を発表した(62)。同年1月には、グーグルはロサンゼルスとチリを結ぶキュリー(グーグル単独、2019年4月、敷設完成)、ニューヨークとデンマーク・アイルランドを結ぶHavfrue(デンマーク語で人魚を意味し、フェイスブックなどと共同で)、香港とグアムを結ぶHK-G(NECとRTI Connectivityと共同)の三つの海底ケーブル建設を発表した。このように、グーグルを中心に米国のテック・ジャイアンツは虎視眈々と海底ケーブルによる影響力拡大を進めている。
これに対して、中国電信(China Telecom)、中国移動通信(China Mobile)、中国聯通(China Unicom)の3社が2016~2020年に出資する海底ケーブルは13万8000キロメートルで、グーグルとフェイスブックに迫っている。2018年にアフリカと年米をはじめて結んだセイル(Sail)には、聯通が出資している。忘れてならないのは、ファーウェイ・テクノロジーズ(華為技術、以下、ファーウェイ)も米国のグーグルなどと同じように海底ケーブル事業に乗り出している点である。ファーウェイ・マリン・ネットワークスがそれである。ファーウェイとグローバル・マリン・システムズの合弁会社だ。
留意すべきは、テック・ジャイアンツと米国政府や中国政府の関係だ。米国の場合、エドワード・スノーデンによる米諜報機関による盗聴・傍受の暴露で、テック・ジャイアンツと政府機関との「癒着」が明らかにされて以降、両者の関係は距離を置くようになっている(63)。こうした「現実」を丁寧に分析するなかで、新しい地政学が展開可能となるのではないか。
(C) 信頼の行方
新しい地政学は、人間の信頼がどこに向かうかに大いに影響される。だからこそ本稿では、神信頼から人間信頼、国家信頼、マシーン信頼やネットワーク信頼について考察した。ITによって、サイバー空間とリアル空間の融合が急速に進むいま、人間は個人、国家、産業、文化などの多方面にわたる変革を迫られている。そうであるなら、地政学もまた領土いった物理的環境だけでなく、サイバー空間をも含めた外部環境の変化に目を向けなければならない。そこで重要なのは信頼の方向性である。
すでに論じたように、マシーン信頼ないしネットワーク信頼は一人ひとりの人間への尊重、人権に普遍性を見出そうとする視線を刺激する一方で、一人ひとりの違いを訴える。この普遍化と個別化の相互作用を可能にするのがマシーンであり、それをつなぐネットワークなのだ。その意味で、この二つへの信頼は国家信頼を構築するうえで重要な役割を担ってきた「内側の自部と外側の自分を区別して外部社会に対して内部の自分を位置づける」というアイデンティティの条件はその重要性を失いつつある。人間は外部の共同体を家庭、学校、会社、国家などに重層化し、それらに帰属する自己をアイデンティティとして感じているわけだが、それらの共同体それぞれが問題をかかえていることがそれらへの信頼を毀損する。家庭は離婚の増加や貧富の格差の増大、学校は学力偏重や標準化の徹底、会社は利益優先や従業員監視強化(ウェアラブル端末で歩数、カロリー消費、レム睡眠サイクル、心臓の健康状態をはかり、会社は従業員を監視可能になりつつある)、国家は「生-権力」の濫用や超国家企業の節税・脱税といった問題から、それぞれの構成員からの信頼を失いつつある、少なくとも無意識のレベルにおいては。
こうした変化が国家信頼を毀損するなかで、自らのアイデンティティをしっかりと感じる手段としてネットワークにつながることの重要性が増すのである。ネットワークにつながることで、「他者に認証されるという渇望」も「尊厳」もなんとか感じることができるからである。いや、尊厳については人間がノード(結び目)としてつながっているだけに、その尊厳の大切さに敏感になる。ネットワークを構成するノードは基本的にだれもが同じという、人間としての尊厳の普遍性を感じさせるから、ネットワークにしがみついくことで差別から逃れることができると誤解するのである。とくに、サバルタンのような人々にとっては、ネットワークだけが頼りであり、信頼せざるをえないものになる(64)。
「内側の自部と外側の自分を区別して外部社会に対して内部の自分を位置づける」というアイデンティティを感じるための条件が軽視されるようになると、この条件を使って国家信頼の醸成へとつなげてきた国家はその信頼を喪失するばかりか、その権力すらも失いかねない。だからこそ、中国のような国は「デジタル全体主義」によってあくまで国家最優先の体制を維持しようとしている。他方で、「デジタル資本主義」のもとでは、テック・ジャイアンツの主導によるマシーン信頼やネットワーク信頼が広がりをみせている。
重要なのは、こうした歴史的位相を踏まえたうえで、世界全体が向かおうとしている覇権の行方を考察することである。国家といった古い地政学的考察の対象だけでなく、テック・ジャイアンツのような超国家企業の動向を研究することが大切なのである。加えて、信頼やそれを支える文化のような心理的対象にも十分な注意を払う必要がある。こうした課題を見据えたうえで、「新しい地政学」の構築につなげたいと願っている。
「古い地政学」は領土主権、国家主権、ネーションを基盤とするネーション・ステートを前提に、せいぜい陸・海・空・宇宙をその射程にとらえてきたにすぎない。なかでも核兵器をめぐる政治課題とエネルギー資源にかかわる経済課題に重点が置かれてきたと言えよう。これに対して新しい地政学の地平は、以下の五つの覇権争奪の議論のうえに拓かれるだろう。①これまでの核兵器中心の武力による覇権、②貨幣・資本をめぐる金融覇権、③エネルギー資源に基づく経済覇権、④ソフトパワーと呼ばれる文化に関連する覇権、⑤サイバー空間とリアル空間の融合にかかわる覇権――がそれである(65)。①と②と③は主権国家や国家信頼に深くかかわっており、④や⑤は主としてテック・ジャイアンツやネットワーク信頼ないしマシーン信頼に関係している。当面の覇権争奪は「デジタル全体主義」と「デジタル資本主義」の対峙というかたちで具体化する可能性が高い。いずれも「デジタル」がキーワードであり、最先端技術の支配力・伝播力が⑤の帰趨を決するだろう。いずれにしても、技術力がますますその重要性を高めるはずだ。国家は技術力強化担当機関を設置し中長期戦略を練る必要が生まれるだろう。企業レベルでも同じ対応が迫られている。その精緻な議論については、改めて議論することにしよう。
(1) ギリシャの都市国家は公的領域と私的領域をその設計思想によって区別してきたことが知られている。家屋のなかに両者の「閾(しきい)」が内在することで両者の分断を避けてきたのである。具体的には紀元前5世紀に活躍したミレトスのヒッポダモスこそ歴史上はじめての都市計画者の一人であり、アリストテレスの「政治学」に従って都市計画に従事したとされている(詳しくは山本理顕, 『権力の空間/空間の権力:個人と国家の〈あいだ〉を設計せよ』[講談社選書メチエ, 2015]を参照)。これこそまさに境界であり、裂け目に転化する契機となった。空間にはギリシャ語のasylonに由来する「聖域」(asylum)という裂け目があったことがその後のヨーロッパの歴史に大きな影響を与えてきた(John Griffuths Pedley, Sanctuaries and the Sacred in the Ancient Greek World, [New York: Cambridge University Press, 2005], p. 97)。あるいは、イタリアの哲学者、ジョルジョ・アガンベンは、内戦、蜂起といった緊急事態を意味する例外状態は、「究極においては、アノミーとノモス、生と法、権威と権限とがどちらともつかない決定不能性の状態にある閾を設けることによって、法的-政治的な機械の二つの側面を分節すると同時にともに保持するための装置」として機能しているのだ」と指摘している(Giorgio Agamben, Stato di eccezione=上村忠男・中村勝己訳,『例外状態』[未来社, 2007], 174頁)。裂け目の分析はきわめて重要なのである。
(2) 塩原俊彦, 「サイバー空間と国家主権」『境界研究』, No. 5, 2015。
(3) サイバー空間については、註(2)の拙稿を参照。リアル空間は「目の特権化」によってもたらされた19世紀の写真術の広がり後に読まれた空間にすぎない(東浩紀, 『サイバースペースはなぜそう呼ばれるか+』[河出文庫, 2011], 97-99頁)。19世紀の写真術は対象を視角的に固定し客体化するもので、それは見る側と見られる側を主体と客体に峻別することを前提にしている。18世紀末に気球が発明され、都市を鳥瞰することが可能となり、その経験は18世紀末に生まれ19世紀中を通して都市で人気を博したパノラマという見世物へとつながったと考えられる(多木浩二, 『眼の隠喩:視線の現象学』[青土社, 1992], 125頁)。それが写真の発明を促したのだ。19世紀末に登場した映像技術は見る側と見られる側の峻別をもはや維持しない。なぜなら映画を見ることはスクリーンを流れるイメージを眺めるだけでなく、そのイメージを構成する視線そのものである、カメラの位置と構図の時間的推移にもつきしたがう経験を意味するからである。これは写真的視線の主体が想像的同一化しか知らないのに対して、映画的視線の主体が想像的同一化と象徴的同一化の間を往復するという人間的主体化を大いに促すものであったことを示唆している。だが、サイバー空間という仮想現実がシュミラークルされている場所を提供できる技術が生まれると、人間はコンピューター上に映し出されるインターフェイスを額面通りの価値で受け取るようになる。つまり、コンピューターのモニターという、スクリーンの背後に関心をもつことなくスクリーンをイメージ(仮想現実を構成するテクストの文字列)とシンボル(現実の表象)の二重化したものを感じるようになるのだ。ラカン派の世界では、人間は現前するイメージを不在のシンボルによって、見えるものの世界を見えないものの世界によって、すなわち知覚される経験的現実を近くされない超越論的観念によって乗り越え、近代的主体になるとみなしてきた。しかしもはやサイバー空間の世界では、知覚される世界そのものが現実とも不在とも言い難い曖昧な状態に変えられてしまう。それは人間の主体化そのもののあり方を変容させようとしていることになる。こうした二つの空間の融合は人間の主体化をさらに困難にする。
(4) ジョン・アグニュー、「グローバル化時代の地政学」『境界研究』, No. 6, 2016。
(5) アグニュー, 2016, 17頁。
(6) Lederer, Emil, State of the Masses: The Threat of the Classless Society, (New York: W. W. Norton and Company), 1940=青井和夫・岩城完之訳, 『大衆の国家』3版, (創元新社, 1966), 41頁。
(7) Neumann, Sigmund, Permanent Revolution, The Total State in a World at War, (New York: Harper and Brothers, 1942)=岩永健吉郎, 岡義達, 高木誠訳,『大衆国家と独裁:恒久の革命』,(みすず書房, 1998).
(8) Friedrich, Carl, J. & Brzezinski, Zbigniew, K. (1965) Totalitarian Dictatorship and Autocracy, (Cambridge: Harvard University Press), pp. 9-10。
(9) たとえば加藤弘之, 第1章「経済システムとしての国家資本主義」, 第7章「国家資本主義はどこへ向かうか?」(『21世紀の中国 経済編 国家資本主義の光と影』加藤弘之ら編著, [朝日新聞出版, 2013])や “The rise of state capitalism,” The Economist, Jan. 21st, 2012。
(10) “China’s “social credit” scheme involves cajolery and sanctions,” The Economist, Mar. 30th, 2019。
(11) オンライン取引業者のアリババ(Alibaba)がアリペイ(Alipay)を使って電子決済するかたちでキャッシュレス化が進んだ。これに、無償でメッセージ交換ができるウィチャット(WeChat、テンセント[Tencent]が運営)が各利用者の銀行口座にアクセスできるようになったことで、スマートフォンを使ったウィチャット経由での電子決済(WeChat Pay)が広まったのである。
(12) Gilder, George, Life after Google: The Fall of Big Data and the Rise of the Blockchain Economy, (Washington, DC: Regnery Gateway, 2018), p. 154。
(13) ビットコインのような暗号通貨を創出するのに必要なASIC(特定用途向け集積回路)を開発・製造し、独占的な状況にある中国企業、ビットメイン(Bitmain)が結局はブロックチェーンに大きな影響力をもっているという不可思議な状況もある。ビットメインが2018年に暗号通貨、イーサリアムのアルゴリズムに特化したマイニング装置を発売したことから、イーサリアムへの中国企業の影響力拡大への懸念が高まった。ゆえにASICによるマイニングに対抗して、これまでのイーサリアムのプロトコル、「プルーフ・オブ・ワーク」(PoW)から「プログマティック・プルーフ・オブ・ワーク」(ProgPow)というルールに変更する動きが広がりつつある。中国側は「ProgPoWへの切り替えはAMDとエヌヴィディア(NVIDIA)という米国の2大チップメーカーが優位に立てるようにする策略だ」と反発している。
(14) Viktor Mayer-Schönberger & Thomas Ramge, Reinventing Capitalism in the Age of Big Data, (London: Basic Books, 2018)。
(15) Sarah Myers West, “Data Capitalism: Redefining the Logics of Surveillance and Privacy,” Business & Society, 2017。
(16) The Rise of Data Capital, MIT Technology Review Custom, produced in partnership with Oracle, 2016。
(17) Jodi Dean, “Communicative Capitalism and Class Struggle,” Journal for Digital Cultures, 2014。
(18) Alex Pentland, Social Physics: How Good Ideas Spread–the Lessons from a New Science, (Penguin: London, 2014)=小林啓倫理訳, 『ソーシャル物理学:「良いアイデアはいかに広がるか」の新しい科学』, (草思社, 2015)。
(19) Zuboff, 2019, p. 440。
(20) Zuboff, Ibid., pp. 347-348。
(21) Zuboff, Ibid., p. 372。
(22) Eco, Umberto, A passo di gambero. Guerre calde e populismo mediatico, (Milano, Libri S.pA., 2006) =リッカルド・アマデイ訳, 『歴史が後ずさりするとき:熱い戦争とメディア』, (岩波書店, 2013), 128頁。
(23) Eco, Ibid.=2013, 128-129頁。
(24) Zuboff, Ibid., p. 339。
(25) Zuboff, Ibid., p. 514。
(26) Zuboff, Ibid., p. 515。
(27) The Economist, Mar. 16th, 2019, p. 58。
(28) テック・ジャイアンツでるアップルの販売するアイフォン(iPhone)の所有者がその販売者であるアップルの独占的地位を利用した価格設定について訴えることができるかどうかを争う裁判でもこの問題が争点になった。アイフォンの所有者でユーザーであるグループは、アップルがその独占的地位を利用してユーザーがゲームソフトなどをアップ・ストアー(アプリケーションソフトのインターネット配信会社)を通じてしか買えないように強いる一方、他方で開発者からそこでの売上高に対する高い手数料(一つのアプリ販売につき30%のコミッション)を徴収しており、それがアプリ価格に転嫁されていると主張した。ただ、最初に論点となったのは、こうした訴えを提起する資格がユーザーたる消費者にあるかどうかであった。アップル側は、「ユーザーたる消費者はアプリをアップ・ストアーにおいて開発者から購入するのであり、アップルは仲介者にすぎないから訴訟対象になりえない」と主張した。2019年5月13日、米国の最高裁判所はアイフォンを反トランスと法違反で訴えていたユーザーグループによる原告資格を認める決定を5対4の僅差でくだし、今後、ユーザーたる消費者が直接、アップルによるアップ・ストアーでの独占的地位利用を裁判で争うことが可能となった。
(29) 詳しくは拙著(塩原,2019, 29-31頁)を参照。
(30) テック・ジャイアンツはロビイスト活動を活発化することで、反トラスト規制の強化に対抗しようとしている(ロビイストについては、拙著[塩原俊彦, 『民意と政治の断絶はなぜ起きた』, <ポプラ社, 2016>]に詳しい)。「ニューヨーク・タイムズ」電子版(2019年6月5日付)によると、アマゾン、アップル、フェイスブック、グーグルの2018年のロビイ活動費の総計は5500万ドルで、2016年の2740万ドルの約2倍に膨らんだ。2019年第一4半期の4社合計の登録ロビイスト数は238人で、そのうちの約75%は公務員であったり、選挙運動に従事したりしたことがある人物であるという。ただし、公平にみて、テック・ジャイアンツの政治的圧力が米国政府におよぼす影響力が支配的かどうかについては疑問符がついている(Tyler Cowen, Big Business: A Love Letter to an American Anti-Hero, [New York: St. Martin’s Press], 2019, p. 171)。企業は連邦政府に対するロビイングに年間約30億ドルも支払っているのであり、テック・ジャイアンツの拠出するロビイ活動費は決して多くはないからである。
(31) 中山信弘, 「著作権法の憂鬱」『パテント』, Vol. 66, No.1, 2013, 106頁。
(32) Aaron Perzanowski & Jason Schultz, The End of Ownership: Personal Property in the Digital Economy, (The MIT Press: Cambridge, Massachusetts, London, England, 2018 [paperback edition]), p. 35。
(33) Perzanowski & Schultz, Ibid., p. 121。
(34) 注目すべきは、1991年3月に採択され1998年4月に発効した「植物の新品種の保護に関する国際条約」(UPOV条約)の大幅改訂である。植物品種の保護を特許法ではなく、多国間の植物品種保護制度で行うとする動きが広がり、それが育成者(バイエル・モンサント、ダウ・デュポン[分割中]、ケムチャイナ[中国化工集団有限公司]など)の権利強化につながった。これは、ライセンスに基づくテック・ジャイアンツの急成長と類似した事例であり、両者のグローバル支配は比較研究すべき対象となっている。
(35) Perzanowski & Schultz, Ibid., p. 174。
(36) 1993年4月5日付EU指令「消費者契約における不正約定」において、消費者契約の特別の精査を要する法的約定が例示されている。つまり、消費者と商業者との権利・義務のアンバランスにつながる不正な約定を糺そうとしているのだが、そのなかにはデジタル財にかかわる多くのEULAの不正約定がある。このEU指令には法的拘束力はないが、EU加盟国は国家レベルでこの指令に従った国内法整備が求められている。もし米国政府が同じ契約形態を採用し、ライセンスを契約と同一視するのであれば、EULAにおけるとんでもない濫用の一部は回避されるかもしれない(Perzanowski & Schultz, Ibid., p. 176)。
(37) 詳しくは拙著(塩原,2019, 234-246頁)を参照。
(38) 信頼は “social capital”という概念に基づいていると経済学ではみなされることが多い。ジェームズ・コールマンの“Social Capital in the Creation of Human Capital,” American Journal of Sociology, 1998やロバート・プットナムの“The Prosperous Community: Social Capital and Public Life,” American Prospect, 1993などがその先駆的業績と言えるだろう。その後、サミュエル・ハンティントンの” “The Clash of Civilization?” Foreign Affairs, 1994によって文化の差の違いが重視されるようになり、フランシス・フクヤマは『信頼』(Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity, A Free Press Paperbacks Book, 1995)を著した。
(39) Francis Fukuyama, Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment, [New York: Farrar, Straus and Giroux, 2018], p. 37。
(40) 詳しくは拙著(塩原,2019, 251-256頁)を参照。
(41) Fukuyama, 2018, p. 26。フクヤマはそう考える理由を説明していないが、1517年10月末にカトリック教会の役割を問う「九五カ条の論題」で、ルターは神と信者の間に教会という外部があり、ローマ教皇によってドイツに派遣されたドミニコ修道会が贖宥状を出していたことを問題視したのだ。
(42) Daniel, Boorstin, The Image: A Guide to Pseudo-Events in America, (Harper & Row, 1961)。
(43) 詳しくは拙著(塩原俊彦,『官僚の世界史』, [社会評論社], 2019, 36-38頁)を参照。
(44) Thomas Hobbes, Leviathan, 1651=Hobbes’s Leviathan, reprinted from the edition of 1651, (Clarendon Press, 1909)=水田洋訳, 『リヴァイアサン』2, (岩波文庫, 1964), 34頁。
(45) 詳しくは拙著(塩原,2019, 256頁)を参照。
(46) 本来、「サバルタン」はインド近代史の研究から生み出された概念である。ガヤトリ・スピヴァクの「サバルタンは語りうるか」という論文を契機に一般的な文脈でも使われるようになる(Gayatri Chakravorty Spivak, “Can the Subaltern Speak?,” in Marxism and the Interpretation of Culture, Cary Nelson & Lawrence Grossberg [eds], [London: Macmillan, 1988], pp. 24-28=上村忠男訳, 『サバルタンは語ることができるか』, [みすず書房, 1998] )。同論文で考察対象となっているのは、ヒンドゥー教徒で、夫に先立たれた妻が夫の死体を焼く火葬の火のなかに身を投じて殉死する慣習にさらされていた女性である。インドを植民地化したイギリス当局は、この慣習を禁止したのだが、スピヴァクは、ヒンドゥー教のこの寡婦殉死の慣習とそれに対する禁止をめぐる言説の配置を主題化しながら、論文のタイトル、「サバルタンは自らについて語ることができるのか」と問う。ここで、大澤真幸の優れた分析を手掛かりにしよう(大澤真幸,『ナショナリズムの由来』, [講談社, 2007], pp. 482-484)。この慣習の禁止に対して、論理的に可能な言明は、つぎの二つ。①「白人(男性)が茶色の男たち(インド人男性)から茶色の女たち(インド人女性)を救った」という言明と、②「女たちは本当に死ぬことを欲していた」という言明である。①は「人権」のような普遍概念に基づいて、禁止を肯定する言明だ。それに対して、②は、ヒンドゥーの伝統の特殊性に立脚して、禁止を拒否し、慣習を肯定する言明である。スピヴァクは、古代以来のヒンドゥー法の言説の伝達過程を精神分析学的に解釈し直すことで、寡婦の自己犠牲についての規則は、女性を一人の夫にとっての客体として定義しているのであって、ヒンドゥー法の内にプログラムされてきた、主体の地位をめぐる一般的な(男女の)非対称性極端にまで推し進めた結果である、と結論する。
すると、これら二つの言明のどちらにおいても、ネイティヴの女性の言葉が現れないことになる。二つの命題によって、論理の空間は尽くされているようにみえる。また両者の帰属点によって、社会システム内の可能な立場も尽くされているようにみえる。つまり、二つの命題の和は、十分に包括的で普遍的なものにみえる。だが、それにもかかわらず、排除されている発話がある。それは、インド人女性、ネイティヴの女性の発話だ。スピヴァクは、①と②のどちらの発話のなかにも、インド人女性の言葉は現れてはいない、と指摘する。インド人女性は、①のように言われても、また②のように言われても、自らが疎外されていると感ずるだろう。ネイティヴの女性が、そこからみずからを語りうる空間が、初めから失われているのである。ネイティヴの女性の言葉が、誰にも聞き取られていないのだ、ともいえる。だから、スピヴァクは、サバルタンは語りえない、と結論する。こう説明したうえで、大澤は、「つまり、このインド人女性にその例を見ることができるように、資本主義的な世界システムの中で、主体的に語ることの可能性が、あるいは、語る主体として承認され、聞き取られる可能性が、奪われている者たちが出てくるのだ」と指摘している(同, p. 483)。スピヴァクらはそうした人々を「サバルタン」と呼んだのである。
(47) Niklas Luhmann, Vertrauen: Ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplextät, 2 aufl., (Ferdinand Enke Verlage, 1973)=大庭健・正村俊之訳,『信頼』, (勁草書房, 1990)。
(48) 大澤真幸,『社会学史』,(講談社, 2019), 174頁。ここでいう「無意識」は心の奥底にある本人も知らない意識を意味しているわけではない。自分のなかで展開しているという自覚を伴う意識的な思考と異なり、無意識的思考では自分の思考なのに自分の外で生起しているように感じられるのである(大澤, 2019, 220頁)。つまり、国家が考えているように感じてしまうようになるのだ。つまり、「国家=神」のような視角がいつの間にか刷り込まれるのである。もちろん、国家語教育をはじめとするさまざまな強制がこれを可能とするのだ。
(49) Kevin Werbach, The Blockchain and the New Architecture of Trust, (Cambridge, Massachusetts, London, England, The MIT Press), 2018, pp. 25-28。
(50) 貨幣については、24 億人とも27億人ともいわれる利用者をもつフェイスブックが推進する「リブラ」(Libra)と呼ばれる暗号通貨プロジェクトが注目されている。フェイスブック利用者のフェイスブック上および他のウェブサービス経由での決済のために暗号通貨を開発中である。同社子会社、Calibra は2020 年はじめにもリブラの運用を開始する。リブラはリブラ基金を構成するマスターカードやウーバーを含む大企業や金融会社、27 社に支援されており、世界の主要通貨を混合した金融準備金によって裏づけられている。これまでクレジットカード会社が担ってきた決済サービスなどを大きく侵食する可能性がある。それは、通貨発行権を独占してきた国家にとって、その独占権を奪い、シニョレッジと呼ばれる貨幣発行に伴って得る利益(たとえば、100ドル札をつくるコストは12.3セントにすぎず、1ドル札は4.9セントだから、胴元である中央銀行はシニョレッジを得られる)を失いかねないことを意味している。
(51) 「ゼロ・トラスト・ネットワーク」という考え方がある(Doug Barth, Evan Gilman, Zero Trust Networks, [O’Reilly Media, Inc., 2017])。「アクセス認証を信頼しない」という徹底した性悪説にたつことで、ネットワークのセキュリティを確保しようとする考え方だ。これはネットワーク自体を信頼しないのではなく、「あらゆるものが自由なインターネット上にある」とみなして、そのなかでの安全保障をいかに保つかを問う。ゆえにインターネットを支えるネットワークそのものを疑っているわけではない。これに対して、中国が2012年からはじめたとされる、「ゼロ・トラスト」と呼ばれる反腐敗のためのAIは、中国科学アカデミーと中国共産党によって開発されたものだ(Stephen Chen, “Is China’s corruption-busting AI system ‘Zero Trust’ being turned off for being too efficient?”, South China Morning Post, 4 Feb., 2019)。公務員の仕事や私生活を監視・評価・干渉するために、中央・地方政府の150を超すデータベースにアクセスできる。一部の地方で導入されただけだが、この場合の「ゼロ・トラスト」は公務員自体を信頼していないからこそ、公務員を徹底的に監視するという発想でつくられている。
(52) このネット上でアイデンティティをどう感じるかという問題は「ネット上の自分」と「現実の自分」の分離を引き起こしている。とくに、最新のデジタルツールを駆使した「盛る」という行為が日本の女子高生に広がっている(詳しくは久保友香, 『「盛り」の誕生:女の子とテクノロジーが生んだ日本の美意識』, [太田出版, 2019])。これは文化を構成する美意識の変化に深くかかわっている。
(53) 佐藤俊樹,『社会科学と因果分析:ウェーバーの方法論から知の現在へ』,(岩波書店, 2019), 116頁。
(54) 具体的な例を挙げてみよう。「ニューヨーク・タイムズ」電子版(2019年6月5日付)は、中国のオンライン小売業者、JD.comの創業者が米ミネソタ州で女子大学生をレイプしたという事件で、関連するビデオが流出し物議をかもしている話を紹介している。女子学生がエレベーターのボタンを自ら押し、自室に手招きしているような様子が映るビデオが本物であるとしても、それは女子学生によるハニートラップを示すのか、それともレイプへの過程を示すものなのか。結論はそう簡単には出ないはずだ。
(55) 「オルタナ右翼」はトランプ政権誕生前から英語圏のウェブサイト、Redditや画像掲示サイト、4chanなどのソーシャルメディア通じて多数の聴衆に情報発信する、既存政党に属さない独立系の人物を意味している(Angela Nagle, Kill All Normies: The online culture wars from Tumblr and 4chan to the alt-right and Trump, [Winchester, UK & Washington, USA: zero books, 2017], p. 42)。英語では“alt-right”と表記するが、白人至上主義者のリチャード・スペンサーが考案したとされている(Nagle, Ibid., p. 51)。反フェミニズム、反イスラーム化、反大量移民などを特徴とする。グラムシの思想を取り入れたフランスの“Nouvelle Droite”(New Right)運動が米国にも波及し、「ネオコン」(Neo-Conservatives)と呼ばれる人々やオルタナ右翼へとつながっている。
(56) 17世紀半ばの清教徒革命で議会軍の兵士が“common soldiers”(平の兵隊)と呼ばれるのを拒否し、“private soldiers”(兵卒)という名称を要求したことが知られている(Raymond Williams, Keywords: A Vocabulary of Culture and Society, Revised Version, [London, Harper Collins, 1976, 1983]=椎名美智・武田ちあき・越智博美・松井優子訳,『完訳 キーワード辞典』,[平凡社, 2002], 68頁)。つまり、これより以前の段階では、「コモン」という言葉に軽蔑的なニュアンスが含まれていたことに留意すべきだろう。
(57) Perzanowski & Schultz, Ibid., p. 137。
(58) Henry Farrell & Bruce Schneier, Common-knowledge Attacks on Democracy, The Berkman Klein Center for Internet & Society Research Publication Series, 2018, pp. 6-7。
(59) ディスインフォメーションについては、拙著(塩原, 2019, 125-128頁)を参照。
(60) ただし、サイバー戦争に備えてタリン・マニュアル(Tallinn Manual)、宇宙戦争に備えてウォーメラ・マニュアル(Woomera Manual)の策定が進んでいることに注意しなければならない。
(61) The Competitive State of eCommerce Marketplaces, Data Report Q2 2018, (Jumpshot, 2018), p. 17。
(62) 毎秒約250テラバイトの情報量を移送でき、それは2018年に開始されたスペインのビルバオと米ヴァージニアを結ぶ海底ケーブル「マレア」(Marea、フェイスブック、マイクロソフト、スペイン・テレフォニカが参加)の毎秒160テラバイトの輸送量を上回り56%も速いと、グーグルはみている。グーグルは海底ケーブルの設計・製造・敷設を請負業者の米SubComに委任している。
(63) スノーデンの暴露とその後の米国政府とテック・ジャイアンツの関係については、拙著(塩原, 2019, 74-84頁)を参照。
(64) いわゆる「ひきこもり」状態にある人間からネットワークを奪ってしまうと、もはやその人間は人間としての尊厳を感じることはできず、アイデンティティを確認できないだろう。この人間の尊厳への回帰は人間の数値化や物化への反作用であるとみなすべきだろう。本稿で指摘したように、統計こそマシーン信頼やネットワーク信頼を支えているのであり、それは感情さえ数値化することを前提にしている。その意味では、人間の尊厳を「ぶち壊している」のだが、だからこそ尊厳に回帰したい人間を増やすのだ。いまペットの世界では、「人間化」(humanisation)が進んでいる(The Economist, Jun. 22nd, 2019)。ペット名義のインスタグラムが無数に登場し、ペットとの結婚を望む人間すらいる。おそらくこうしたペットへの同化は奪われつつある人間の尊厳をペットへと仮託することで守ろうとする「あがき」なのではないか。いずれにしも、デジタル空間とリアル空間の融合する新時代は人間に本源的な変化を迫っているのだ。
5Gが広がると、特定の顧客やアプリケーション向けに複数のヴァーチャル・プライベート・ネットワーク(VPN)を顧客やアプリケーションごとに提供(カスタマイズ)できるようになる点を注意喚起しておきたい。これは、5Gがもたらす「ネットワークスライシング」(NS)によって実現できるのだが、このNSは、サーバーやルーターといった物理設備を仮想的に分割可能な資源として管理し、それら仮想資源を組み合わせた仮想網(スライス)を共有物理設備上に構成する技術を意味している。この技術を使えば、顧客やアプリケーションごとの価格決定にも利用できる。こうなると、ネットワークにつながっているすべてのノードがみな平等であるかのような感覚は失われてしまう。ゆえに、ネットワーク信頼が揺らぐことになるだろう。その場合でも、ノードたるマシーンへの信頼は変わらないはずだ。
(65) 筆者は意図的に、『核なき世界論』(東洋書店, 2010)で核兵器問題を、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局, 2007)でエネルギー問題を、『サイバー空間における覇権争奪』(社会評論社, 2019)でサイバー空間とリアル空間の融合問題を論じてきた。地政学上の最重要問題に取り組んできたのである。その意味で、これらの3部作は地政学研究における必読書であると自負している。





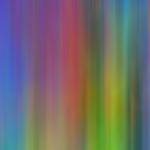



最近のコメント