優生学の伝播と気候変動
優生学の伝播と気候変動
優生学(eugenics)は、英国のフランシス・ガルトン卿によって創始され、その後、1930年代に米国のカリフォルニアで盛んに研究された。ここでは、飯田香穂里著「欧米における優生学とその影響」(『生命科学と社会 2009』第8章)を参考にした。
1859年にダーウィンの『種の起源』が出版され、その後、これに影響されたガルトンは “eugenics”という言葉をつくる。“eu”とは、「良い」を意味し、“genics”は「生まれてくる」を指していたから、「優生学」と日本語訳されるようになったのである。「生存に適していない」人間は生まれてこないほうがその人にとって、はるかに幸福ではないかとの見方から、生存に適していない人間の排除が肯定されるようになってしまう。
こんな考えであっても、地域によって一世を風靡し、1933年までにカリフォルニアでは、その他の米国の全州よりも多くの人々に強制的な不妊手術が施されていたほどだ。この不妊手術に実践的なノウハウを学んだのがドイツの国民社会主義ドイツ労働者党(ナチス)である。ドイツ本国では、エルンスト・ヘッケルが優生学を推進したが、米国で優生学を広めたチャールズ・ダベンポートの影響下におかれていたと考えるほうが正しい。
1907年、米国のインディアナ州で強制的に生殖能力を失わせる断種法が制定されたのを皮切りに、1935年までにほとんど州で断種法が施行されるまでに至る。1930年代末までに全国で3万人以上が強制断種されるに至る。これを模範にドイツでも1933年のヒットラー政権成立直後に断種法が制定された。181カ所に遺伝健康裁判所が設置され、最初の年だけで医師から8万5000件もの断種申請があった。うち5万6000件がただちに断種決定となったという。
優生学の隆盛を支えたのは、拡大する所得格差に基づく「社会的上下関係」と、「生物学的上下関係」を同等とみなす発想であった。欧米社会では、白人層が優位にたって女性よりも男性が力をもっていた。こうした社会階層に対応させて、白人男性が優れた遺伝形質を有するとみなしたのである。その根拠を「優生学」という「科学」に求めることで、科学のもつ「普遍性神話」に立脚して、強制的な断種が断行されたわけである。
その際、政治が強力にかかわった。ナチスによるユダヤ人迫害は政治的に歪められた情報をもとに優生学が彼らの排除に強くかかわったのであった。
生物に「有害遺伝子」が存在すること自体は否定できない。しかし、だからといって自然界で排除されながらも受け継がれてきた有害遺伝子を人為的に強制断種することは許されない。ゲノム編集といった遺伝子組み換えが比較的容易にできるようになった現在だからこそ、遺伝子への対応が再び注目されている。
気候変動問題の怖さ
こうした人類のたどってきた禍々しい歴史は、気候変動問題にも相通じているのではないか。筆者はずっとそう感じている。事実として、大きく気候が変動する時期を迎えているように思える。しかし、それが人為による温室効果ガスの増加によってもたらさていると断言できるわけではない。「科学的根拠」たる「エヴィデンス」に欠けているからだ。
にもかかわらず、政治的なキャンペーンの成果なのか、いまでは人為による温室効果ガスの排出量を減らすことが何よりも必要であるとの主張がまかり通っている。この現象は、「科学的」とよべるほどの普遍性をもたない主張に基づいて、平然と断種が強制されていた優生学の隆盛時代、すなわち暗黒時代の再来のように思えてくる。その一方で、CO2を出さない核発電所の優位が語られて、その大きなリスクに目を瞑っても仕方がないような論調が広がっている。これは、断種法で一部の少数者を迫害してもやむをえないとみなした暗黒時代と同じではないのか。
しかも、根拠があるとは言えない「人為気候変動説」を、スウェーデンの少女、グレタ・トゥーンベリのような人物に宣伝させている姿に胡散臭さを感じざるをえない。はっきり言えば、彼女は優生学がもたらした悲劇を知らないだろうし、人為気候変動説の危うさについて気づいていないのだ。
このサイトの「「システム2」思考の重要性の証」(https://www.21cryomakai.com/%E9%9B%91%E6%84%9F/821/)において、つぎのように指摘した。
*****************************
「大紀元時報」という中国のニュースを中心とするサイトは、2019年9月30日午前11時に「グレタさんを支える環境団体、中国政府の代理人の疑い 沖縄「ジュゴン裁判」も担当」という興味深い記事を配信した(https://www.epochtimes.jp/p/2019/09/47700.html)。詳しくはこの記事をぜひ読んでほしい。
要するに、国連総会の関連パネルで怒りのスピーチを披露した16歳の環境活動家グレタ・トゥーンベリの背後に全体主義の陰があると指摘した、「システム2」思考の重要性という前回の記事が正しいことがわかったのではないか。印象や感情に導かれやすい「システム1」の思考にとどまっていると、情報操作の罠にかかってしまいやすいのだ。
紹介した記事によれば、グレタの登壇を調整したのは、世界的な法律事務所ハウスフィールドLLP(Hausfeld LLP)および環境保護系の法律事務所アースジャスティス(Earthjustice)の公式代表という。子どもたちによる非難声明は、両所が準備した。とくに、アースジャスティスは中国政府に都合がよく、逆に米国に不都合な活動を米国内外で展開しているとみられている。
このアースジャスティスは日本にも関係している。記事によれば、日本の沖縄県で継続的に米軍の行動に反対する活動を行っている環境活動団体・生物多様性センター(CBD)は、米空軍海兵隊の普天間飛行場から名護市辺野古の移設には、絶滅危惧種の哺乳類ジュゴンの生態を侵害するとして、移設反対運動を展開しているのだが、2003年に米国で米軍による沖縄の基地移転を阻止するために起こした訴訟はCBDの代理としてアースジャスティスが起こしたものなのだ。2018年8月にサンフランシスコ連邦地方裁判所はCBDを敗訴としたが、CBDは控訴したという。
私が強調したいのは、グレタの話にしても、ジュゴンの話にしても、「システム1」の思考にとどまっていると、切迫するかにみえる環境問題の重大性もあって、その背後にある政治性が見落とされてしまいかねないのだ。「システム2」の思考までできれば、全体主義国家、中国の「野望」が透けて見えてくる。
*****************************
心配なファッションとしての環境保護運動
心配なのは、「システム2」レベルの思考ができない若者が人為気候変動説を安直に受けいれてしまっているのではないかということだ。その結果、「インスタ映え」だけを根拠に見た目のけばけばしい対象ばかりがもてはやされるのと同じように、2020年以降は、いよいよ日本でも「ヴィーガン」のような完全採食主義者がもてはやされるようになるのではないか。論座で、「牛肉と意識高い系」という記事を書いておいたから、そちらを参考にしてほしい(https://webronza.asahi.com/politics/articles/2019110500003.html?page=2)。

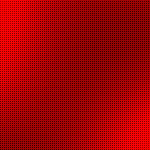






最近のコメント