「ニッポン不全」シリーズの宣伝
「ニッポン不全」シリーズの宣伝
今月末か、来月のはじめに、「論座」において、「ニッポン不全」シリーズがはじまる。毎月一度のペースで、さまざまの分野で「金属疲労」が広がり、機能不全に陥っている「ニッポン」には、「革命」のような荒療治が必要ではないかとの危機感を伝えてゆきたいと考えている。
「革命」について考える
近世と呼ばれる時代から近代という時代に移行する際、どこの国でも「革命」まがいの出来事が起きた。といっても、多くの人は「革命」についてじっくりと考えたことはないだろう。
わたしは、拙著『ロシア革命100年の教訓』(Kindle版)のなかで、まじめに考察したことがある。そこで、革命を論じた部分を紹介してみよう。
****************************************
そもそも革命とは
そもそも「革命」という言い方が気にかかる。この問題に真正面から取り組んだハンナ・アーレントの著作を参考にしながら革命について少し掘り下げてみたい。ここでは、松木智治の「ハンナ・アーレントにおける「はじまり」の概念(2)」という論文を補助線にアーレントの優れた視角を紹介したい。
まず、revolutionという英語に注目したい。地動説を説いたニコラウス・コペルニクスの主著『天球の回転について』はラテン語でDe Revolutionibus Orbium Coelestiumであることからわかるように、revolutionはもともと天文学上の用語であり、循環する周期的運動を表していた。ゆえに、この言葉は一年後に同じ場所に戻ってくる天体の回転というイメージを踏まえた「復古」という意味を強くもっていたと、アーレントは主張している。革命という言葉が復古的な意味合いで最初に政治上使用されたのは、クロムウェルによるピューリタン革命(一六四一~一六四九年)のときではなく、一六六〇年に君主政が復古したときであり、一六八八年の名誉革命でスチュアート家が追放され、王権がウィリアムとメアリーに移ったときにも革命が使われた。
革命はやがて、天体の回転というイメージが喚起するように、抵抗できず、抗いがたいという「不可抗力性の概念」をもつようになる。フランス革命は圧倒的な力で押し流されていく貧民の悲惨を伴っていたのである。
この復古と不可抗力という二つの意味合いが革命の前半と後半に対応関係をもっている。革命前半においては復古を求めるのであり、革命後半では、不可抗力に抗いながらも新しい「はじまり」を創設するための「権威」や「絶対者」が希求されることになる。これが一九一七年のロシア革命においては、二月革命、十月革命というかたちで革命の前半と後半として実践されたことになる。
二つの「自由」および「はじまり=原理」
アーレントにとっての革命は、この復古と不可抗力を背後にもった近代固有の現象であり、彼女にとって革命は、「自由」の観念と「はじまり」の経験とが同時に起きる(一致する)現象であるという。「自由」には、リバティー(liberty)とフリーダム(freedom)の二つがある。前者は「不正な拘束からの自由」といった「~の自由」という「解放の結果」を指している。日本語の「自由」は「自らに由る」に由来している以上、リバティー概念に近い。後者は「公的関係への参加、あるいは公的領域への加入」を意味している。いわば、「公的自由」を意味し、言論行為に代表される政治参加に不可分の概念ということになる。アーレントはとくに後者を重視していた。なぜなら、フリーダムこそ共和政を構成する精神であったからである。
他方で、「はじまり」の経験という厄介な概念をアーレントは提起している。「はじまり」とは、「自由の創設」を意味し、公的領域の創設に参加することを指している。ここで重要なことは、「はじまり」というラテン語“principium”が原理(principle)と分かちがたく関連している点だ。ギリシャ語の「はじまり」を表すアルケー(ἀρχή)は原理という意味ももっているが、公的領域の「はじまり」はやがて記憶や回想の対象となり、伝統や慣習、さらに宗教などに転化され、権威づくりに一役買う。「はじまり」と結びつくことで「原理」が形成されることになる。つまり、「はじまり=原理」なのである。ゆえに、「はじまり」はきわめて重要な意義を有している。
「はじまり=原理」と言葉
革命と呼ばれるには、この「はじまり=原理」を伴うことが不可欠の条件である。これが、いかに重要であるかは言語に明白に現れる。新しい原理は新しい言葉を生み出したり、意味の変容を引き起こしたりするのだ。本書では、この問題を詳述するだけの紙幅はないが、こうした言葉の変化に注目すれば、国家の興亡といった大きな変革の深度を計量化することも可能であると筆者は考えている。その典型が「ソヴィエト」という聞きなれない言葉だ。すでに説明したように、ロシア帝政時代にはせいぜい「相談」や「助言」を意味するだけであった「ソヴィエト」はいつの間にか「相談し助言し合う寄り合い」に転じ、さらに、一種の合議体や自治組織を意味するようになる。一説には、一九〇五年の「第一次革命」のときに生まれたもので、ロシアの総体主義の伝統に根ざしているという(Radzinsky, 1996=1996, 上, p. 146)。果ては国家の名前にも使われるまでになる。これは、言語の進化が「カンブリア爆発」という節足動物、軟体動物、棘皮動物の出現と同じように比較的短期間に劇的な変化として起きる証ともなっている(Mesoudi, 2011=2016, p. 181)。
どうしてこんな話を紹介したかというと、筆者の仲人、宮沢俊一が語った言葉が懐かしく思い出されるからである。彼は、ソ連崩壊後、ボリス・エリツィン大統領の時代になって、「新聞を読んでも意味がわからない」と言っていた。要するに、ソ連がなくなって、それまでのロシア語の言葉遣いが大幅に刷新され、ロシア語の新聞を読んでいても理解できないというのだ。筆者は彼ほどロシア語が堪能ではないから、そんな変化には気づかなかったが、たぶん多くのロシア人は新たな「はじまり=原理」の到来を感じていたに違いない。「同志」を意味する「タヴァーリシ」という言葉が死語と化したことは有名だが、ほかにも、「労働」を連想させる「トルードナ」(難しい)という言葉は極端に使用されなくなり、「スロージナ」という言葉がこれに代替した。このように、言語からロシア革命そのものを徹底的に計量的に洗い直すといった作業が求められていると指摘しておきたい。
職業的革命家の役割
ここで、革命が「自由」の観念と「はじまり」の経験が一致する現象であるとする、アーレントの革命論に寄り添うと、これまであまり語られてこなかったロシア革命の本質とその歪曲がはっきりとみえてくる。
革命の前半において、それまでの権力が倒れるとき、そこに権力の真空状態が生じる。それを埋めるものとして、歴史的事実として「評議会」なるものがいずれの革命でも自発的に発生してきた。問題は、この動きを「自由」の確立や「はじまり」の経験にどういかすかということであった。このとき、重要な役割を果たしたのが職業的革命家ということになる。
「職業的革命家の役割は、このように普通、革命をおこなうことにあるのではなく、革命が起こったあとで権力につくことにある」と、アーレントは『革命について』のなかで喝破している。いずれの革命においても現実に起きたのは、古い権力が解体し、暴力手段に対するコントロールが失われたことであった。その権力の真空地帯に新しい権力構造が形成されたわけだ。この際の権力闘争において職業的革命家は有利な立場にあった。なぜかというと、有名人であったからにすぎない。問題なのは、その理論ではなく、彼らの名前が公に知られているということであった。すでに投獄されたり、お尋ね者扱いされたりして、有名であった彼らは人々への絶大な影響力をもっていたのである。
やや脱線すると、現在の有名人も同じようなものだ。その能力とはまったく無関係に、性懲りもなくテレビに出たり、たくさんの本を書いたりして有名人となった連中は、その影響力においておぞましい力をもつ。彼らの化けの皮を剥ぐことも大切だが、有名人に騙されない見識を養うことも大切になる。ロシア革命に関連づけて紹介しておくと、バーナード・ショーという、脚本家、劇作家として有名な英国人が飢饉たけなわの一九三一年にソ連を訪問し、「飢饉の噂は作り話である」と語った。彼は社会主義者であり、優生学の信奉者でもあったのだが、有名人というだけではすまないほど、その責任は重大なのである。
自発的に発生した「評議会」
アーレントによれば、実際の歴史をみると、一七八九年のフランス革命後に生まれたパリのコミューン(一八七一年のパリ・コミューンとは別)、アメリカ革命時のニューイングランドに現れた郡区(タウンシップ)は評議会の実例である。一八七〇年にプロシア軍によってパリが包囲された際、自発的に評議会が組織され、小型の連邦体が創成され、翌年春、パリ・コミューン政府の核となった。これも評議会である。いずれの評議会も自発的に発生した統治機関(活動と秩序の機関)という特徴をもつ。
ロシアの場合、一九〇五年、血の日曜日事件後の自発的なストライキの波が、あらゆる革命的党派とは別に、急激にこれらストライキにかかわる人々の政治的リーダーシップを発展させた。それが労働者や兵士による評議会(「ソヴィエト」と呼ばれた)を組織するに至る。この経験があったために一九一七年の二月革命時、さまざまのソヴィエトが自発的に出現したのは当たり前のことと受け取られた。レーニンは十月革命時の十月二十五~二十六日の第二回全ロシア・ソヴィエト大会で、「全権力をソヴィエトに」(Вся власть Советам!)という、「四月テーゼ」で打ち出されていたスローガンを文書として採択し、「ソヴィエトの国」をつくると宣言したわけだ。この際、ソヴィエトは複数形をとっており、単一の全国ソヴィエトへの権力の集中が想定されていたわけではないことに留意しなければならない。
第一次世界大戦で敗れたドイツでは、軍隊の敗北後、兵士と労働者が公然と反乱を起こし、労働者(アルバイター・)兵士(ウント・ゾルダーテン)評議会(・レーテ)を構成した。彼らは、一九一九年春、ミュンヘンに短命に終わったバヴァリア・レーテ共和国を樹立した。一九五六年のハンガリー革命時には、ブダペストに居住区で地域的な評議会、カフェで芸術家の評議会、大学で学生・青年評議会、工場で労働者評議会など、各種評議会が自発的に生まれた。その後、上級評議会の創設へとつながり、地域的・地方的性格の上級評議会から全国を代表する会議の代議員を選出するに至る。これはロシアにおけるソヴィエトの創成と連帯に要した数週間に比べて数日という短期間に実現された。
潰された評議会
ここで示した評議会こそ、「自由」の観念と「はじまり」の経験が一致する場となったのだ。しかし、いずれも潰される。大雑把に言えば、市評議会のような性格をもったパリのコミューンは、当時、雨後の筍のように創成しつつあったクラブや協会とともに、これらを擁護するかのような態度をとったマクシミリアン・ロビスピエールが権力を握るやすぐに弾圧の憂き目にあった。これはそののち、ロシアのレーニンがソヴィエトを称揚しながら、権力奪取後にソヴィエトがボリシェヴィキによって凌駕されてしまったことに対応している。
ロシアが厄介だったのは、ソヴィエトを潰しておきながらそれを乗っ取ったボリシェヴィキがソヴィエトを僭称してソヴィエト社会主義共和国連邦(ソ連)なる国までつくってしまったことである(地名を無視したこの国名は地名を超えて広がる文化圏を企図している)。ソヴィエトとは名ばかりのボリシェヴィキによる国家の誕生で、ロシア革命の本質が隠され、一九九一年にソ連が崩壊するまで、その化けの皮をはがすのはなかなか難しかったのだ。
なお、ニューイングランドの郡区(タウンミーティングという直接的方法で自治を行う形態)を憲法に取り入れようとしたトーマス・ジェファーソンだったが、これに失敗したことで、この評議会はアメリカ全土に広がる機会を失した。
いずれにしても、革命の「はじまり」において重要な役割を果たした評議会が事実上、潰されたフランスやロシアでは、公的参加といったフリーダムや束縛からの自由(リバティー)が大幅に制限されたことになる。アメリカの場合、評議会が潰されたわけでないという点で相対的にはもっともフリーダムやリバティーが損なわれずに済んだと言えるかもしれない。
「革命」からみたロシア革命の本質
第一節の記述からわかるように、「革命」部分に注目すると、ロシア革命がその「はじまり」において、ソヴィエトという評議会を換骨奪胎した結果、「自由」を制限する方向に向かったことがわかる。フランス革命もよく似た結果をもたらした。フランスの場合、相次ぐ権力の転変のなかで「自由」を取り戻す方向に向かったのに対して、ロシアは政権を奪取した側が長くその権力を維持・強化する方向に向かってしまったという違いがある。
ここで、アーレントの叙述をもとに、レーニンが「十月革命の本質と目的」を一言でのべるように求められたとき、「電化・プラス・ソヴィエト」と答えたという話を紹介したい。これはアーレントの『革命について』に出てくる話だが、その出所ははっきりしない。
レフ・トロツキーが一九三六年に書いた『ソ連とは何か、そこに行こうとしているか』(邦訳『裏切られた革命』)には、つぎのような記述がある(邦訳一九九二年、八九頁)。
「かつてレーニンは「ソヴェト(マ マ)権力プラス電化」ということばで社会主義の特徴を示した。この辛辣な規定――その一面性は当時の宣伝上の目的から生じたものだが――は、ともかく、最小限の出発点として少なくとも資本主義の電化水準を想定していた。ところがソ連では今日なおひとりあたりの電力は先進諸国の三分の一である。その間にソヴェト組織が大衆から独立した機構に席をゆずりわたしたことを考えに入れるなら、コミンテルンとしては、社会主義とは官僚権力プラス三分の一の資本主義的電化のことだと宣言するほかない。」
どうやら「電化・プラス・ソヴィエト」のような言い回しをレーニンがしたのは事実であったらしい。ロシアのレーニン全集(第四二巻)には、一九二〇年十二月二十二日の全ロ中央執行委員会および内外政策人民委員(コミッサール)ソヴィエト報告のなかで、レーニンが「共産主義、これをソヴィエト権力プラス全国電化である」とのべたとされている。このときのソヴィエト権力は単数形で語られている。十月革命当初、複数のソヴィエトがそれぞれ権力を集中するという原則が早くもこの段階で崩れているように思われる。
いずれにしても、レーニンが電化とソヴィエトをきわめて重視していたのは事実であろう。なぜかと言えば、貧困を除去すること(電化)と政治的自由(ソヴィエト)の二つがレーニンの革命時の「はじまり」における最大関心事であったからである。形式的には、「電化とソヴィエトを二つながら促進することができるのはボリシェヴィキ党だけである」と、レーニンは決定した。ただ潜在的には、彼は、自由の新しい制度となりえたソヴィエトとともに、国の合理的、非イデオロギー的な経済発展の可能性を放棄したことになる。自由の新しい制度たるソヴィエトを党のために犠牲にしたのであり、電化は国力を集中すれば可能かもしれないが、それは貧民を解放することを意味しなかった。
これまで説明してきたように、「革命」部分に注意すればロシア革命が相対化される。だが、政権を握った勢力が国内はもとより海外にまで宣伝活動を繰り広げたため、その実態は長くベールに覆われてしまった。ソヴィエトへの弾圧についての歴史が軽視され、結果として、その弾圧を主導した秘密警察の広範囲にわたるロシア社会への影響拡大という側面があまり知られていないままになっている(この問題は第2章で検討する)。他方で、「初の社会主義革命」なるロシア革命の「原理」は、社会主義というイデオロギーと結びついて、ロシア革命の本質を理解する妨げとなってきた。政権を握った側の「歴史の捏造」とイデオロギーの強制がロシア革命への理解を歪めてきたのである。
****************************************
長い引用になったが、大切なことは21世紀のいま、ここで紹介したような「革命」が必要なのではないかという問題意識にある。
いまのニッポンのように、政治も経済も文化も行き詰まりつつある状況を本当の意味で変革するには、もはや「自由」の観念と「はじまり」の経験が一致する現象としての革命を実現するしかないという気になってくる。
「自由」の重要性
こうした想いを実践するにあたって、より重要なのは「自由」に対する見方であると思っている。なぜならこの「自由」こそ、カント的な倫理を理解するためのキーワードだからである。
いまのところ、「ニッポン不全4 無責任の連鎖(仮題)」において、このカントの倫理問題をとりあげる予定だ。ゆえに、ここでは、これ以上は論じない。「自由」の問題を正しく理解すれば、「革命」に暴力が伴う必然性もないことがわかるだろう。
ともかく、「ニッポン不全」に乞うご期待。
最後に、6月22、23日付の『日刊ゲンダイ』に、わたしのインタビュー記事が掲載されるので、関心のある方はご覧ください。






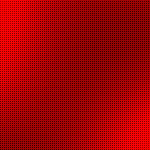


最近のコメント