スティグリッツ著『プログレッシブ・キャピタリズム』を読んで
スティグリッツ著『プログレッシブ・キャピタリズム』を読んで
ジョセフ・E・スティグリッツは2019年にPeople, Power, and Profitsを刊行し、2020年1月、その邦訳『プログレッシブ・キャピタリズム』(訳者は山田美明)が東洋経済新報社から上梓された。スティグリッツはスウェーデン中央銀行賞(ノーベル経済学賞)をとった経済学者だが、筆者にとっては世界銀行のチーフエコノミストを務めた信頼できる学者として私淑の対象となっている。
日頃、さまざまな情報に接して、さまざまなことを「論座」やこのサイトに公開している筆者が痛感しているのは、知識の断片化という問題である。少しばかりの意見を開陳することはできても、グランドデザインに基づいて長期的な視点から、ものごとを議論することが難しくなっているのだ。それは、情報技術(IT)の急速な発展によって、短期的な変化を知るだけで大変な労力がいることの裏返しでもある。
その意味で、彼の著作はグランドデザインについて考えるための視角を教えてくれており、大いに参考になった。若い人々も一読するだけの価値が十分にあると言えるだろう。ここでは、いつものように、この本で感じたことをいくつか書いてみたい。
国富について
41ページにつぎのような指摘がある。
「成長を万人にいきわたらせるためにはまず、国の富を真に生み出すものが何かを理解しなければならない。富を真に生み出すものとは、第一に、国民の生産力・創造力・活力、第二に、過去2世紀半の間に見られたような科学やテクノロジーの進歩、そして第三に、その同じ期間に見られたような経済・政治・社会組織の発展である。」
59ページではつぎのように書いている。
「すでに述べたように、国富を真に生み出すのは、第一に、基盤となる科学や知識、第二に、平和に共存し、公益のために協力し合えるような社会制度である。」
スティグリッツは国富を生み出すこれらの要素を発展させるために必要な政治および経済上の政策について論じていることになる。その意味で、一国経済を前提にして議論を展開していることになる。国家が嫌いな筆者とは立場が異なっているが、まあ、リアルポリティークの立場にたてば、スティグリッツの主張は十分に理解できる。
彼によれば、「経済は、何もかも自由市場に任せておくのがいちばんいいという理論」が過去40年にわたってアメリカを支配してきたとして、この誤りがさまざまな問題を米国に引き起こしていると指摘している。そしていまの状況について、つぎのようにのべている(66ページ)。
「所得階層の上位1パーセントにいる貪欲で近視眼的な人たちも、大多数のアメリカ人がグローバル化や金融化など、現在の経済のルールを支持していないことにようやく気づいたようだ。これは、上位1パーセントの人たちにとっては由々しき事態だ。このまま成り行きに任せておけば、多少なりとも道理をわきまえている有識者が、別の進路を選択するに違いない。そのため超富裕層は、ひたすら自分の利益を追求するため、三つの戦略を駆使するようになった。欺瞞、権利の剥奪、無力化の三つである。第一の欺瞞では、2017年の税制改革は富裕層をさらに豊かにするだけなのに一般的なアメリカ人の利益にもなると述べたり、中国との貿易戦争により脱工業化の流れを食い止められると主張したりする。第二の権利の剥奪では、進歩的な政策を支持しそうな有識者の選挙登録や投票を困難にするなど、その投票行動をさまざまな形で妨害する。第三の無力化では、政府の活動に十分な制約を設け、ほかの戦略が失敗して革新政権が誕生したとしても、政治や経済を改革できないようにする。偏った判事の使命によりイデオロギー的に偏った最高裁判所が課す制約が、その好例である。」
ものは考えよう
つくづくと考えてみて、たしかに「ものは考えよう」だと思ったのは、つぎの指摘である(67ページ)。
「アメリカが冷戦に勝利したのは、自由市場資本主義が優れていたからではなく、共産主義が失敗したからにほかならない。」
知らなかった指摘としては、「国際NGO団体のオックスファムは毎年、格差の広がりを示すデータとして、最上層の人々が何人集まれば、その合計資産が世界の下位50%の人々(およそ39億人)の総資産に匹敵するかを公表している。この数字は年々急速に低下しており、2017年にはたったの26人である。」
レント分析の重要性
若い人は「レント」と言われても、何もわからないかもしれない。そこで、スティグリッツのつぎの記述に注目してほしい(98ページ)。
「国民所得のパイは、労働所得、資本所得、その他に分類できる。このその他の大半を、経済学者は「レント(不労所得)」と呼ぶ。地代はその好例だが、天然資源から得られる利益、独占による利益、知的財産(特許権や著作権)から得られる利益も「レント」と考えられる。」
実は、筆者には、「ロシアのレントと課税をめぐる諸問題」という論文がある。法政大学イノベーション・マネジメント研究センターWorking Paper No. 8として2005年に公表されたものだ。当時はまだ、結構まじめに詳細に研究していたから、なかなかの力作なので、ロシアに関心がなくてもレントに関心をもっている方にぜひとも一読を勧めたい。レントについて本格的に論じた日本語論文は少ないからである。
市場支配力
スティグリッツは「市場支配力」が市場を歪めている点を問題視している。競争市場では、企業は同じものについて、顧客ごとに価格を変えることはできない(価格は限界生産費により決定される)のだが、アメリカのデジタル産業では、価格差別がありふれたものになっているとしている。つぎに、筆者も多少知っていた、市場支配力がどのように強めてきたかについての記述を紹介しよう(106~107ページ)。
「たとえばマイクロソフトは、新たな形態の参入障壁や、既存の競合企業を追い払うずる賢い方向を生み出す能力に長けていた。20世紀末の時代に、競争を制限しようとしたかつての大企業を手本に、そのような面で先進的なイノベーションを築き上げたのだ。その好例が、1990年代のインターネットプラウザーをめぐる闘いである。当時はこの分野で、ネットスケープが際立った活躍を見せていた。パソコンのオペレーティングシステム(OS)ではほぼ独占状態を築いていたマイクロソフトは、この新興企業に利益が侵害されるのを恐れ、同社を追い払おうと考えた。だがマイクロソフトが当時開発していたインターネットエクスプローラーには、ネットスケープほどの魅力がなく、その実力だけでネットスケープに勝てる見込みはない。そこでマイクロソフトは、パソコンのOS市場での市場支配力を利用して、アメリカのほとんどのパソコンにインターネットエクスプローラーを組み込んだ。OSと抱き合わせ、無料で提供したのだ。無料で提供されるブラウザーに対抗できるブラウザーなどあるだろうか? しかし、これだけでは不十分だったため、マイクロソフトはさらに、ネットスケープは相互運用性に問題があるというFUD(恐怖・不安・疑念)戦術を展開した。ネットスケープをインストールすればパソコンの機能が損なわれるおそれがあるとユーザーに警告したのだ。結局マイクロソフトは、そのほかさまざまな反競争的行為を通じてネットスケープを市場から追い出した。21世紀の初めには、ネットスケープを利用する人はほとんどいなくなっていた。こうして独占状態を確立すると、その反競争的行為が三つの大陸で規制機関により禁止されても、マイクロソフトの市場支配は続いた。ブラウザー市場に新規参入者(グーグルやファイアフォックスなど)が割り込んでくるのは、その後の話である。」
先行合併
市場支配力を強める方法の一つとして有名なのは、「先行合併」である。有名な話だが、一応紹介しておこう(125~126ページ)。
「たとえばフェイスブックは、2012年にインスタグラムを10億ドルで、2015年にワッツアップを190億ドル(ユーザー1人あたり40ドル以上に相当)で買収した。フェイスブックは、同様のプラットフォームを開発する技術的なノウハウを持っていた。持っていなかったとしても、ノウハウを持っているエンジニアを雇うことはできたはずだ。それでもわざわざ大金を払って買収に及んだのは、競争を未然に防ぐためだとしか考えられない。」
貿易協定で見過ごせないこと
筆者の知らなかった貿易協定のからくりについての記述も興味深い(140ページ)。
「さらには、貿易協定や税制により、企業にとって、海外への製造拠点を移したほうが都合がよくなると、本国の雇用が失われる。そうなるのは、本国よりも海外のほうが法人税が低い場合だけではない。貿易協定によりアメリカの企業は一般的に、本国より海外に拠点を置いたほうが資産を守ることができる。その協定に、規制の変更から企業を保護する規定があるからだ(アメリカ本国ではそのような保護は受けられない)。規制の変更により企業の現在または将来の収益に悪影響がある場合には、標準的な投資協定の規定に基づいて訴訟を起こすことができる。しかもその訴訟は、企業に有利な仲裁委員会により処理される。」
銀行の悪辣さ
全般に抑制した筆致でこの本を書いているスティグリッツだが、こと問題が金融になると、銀行を厳しく断罪する内容になっているのが興味深い。たとえば、2008年の金融危機に絡んで、つぎのような指摘がある(165ページ)。
「資産額でアメリカ第3位の銀行であるウェルズ・ファーゴは、当人の同意もなく個人口座を開設していた。複数の銀行が、外国為替市場や金利市場の操作に手を染めていた。信用格付会社や投資銀行の多くが、詐欺行為を大々的に行っていた。」
あるいはつぎのような指摘もある(166ページ)。
「「競争は負け犬がするものだ」と言ったピーター・ティール同様、ゴールドマン・サックスのCEOロイド・ブランクファインもこう述べている。誠実で信頼できるといった評判は、かつては銀行のもっとも重要な資産と見なされてきたが、いまではもう古くさい過去の遺物にすぎない、と。」
あるいは、「近視眼的な銀行家は、長期的な評判など意に介することなく目先の利益だけを追求し、投資家にうそをついたり(ゴールドマン・サックス)、一般預金者をだましたり(ウェルズ・ファーゴ)した」という指摘もある(167ページ)。
悪辣なのは銀行だけではない。たとえば、アップルも同じ穴のムジナと言えるだろう(171~172ページ)。
「銀行が租税回避を促進している具体的な事例を一つ紹介しよう。アップルは金融産業と手を組み、その創意工夫の才を、大衆に愛される製品を生み出すために使うだけでなく、租税を回避するためにも利用した。あるときアップルの一部の株主が、同社が多大内利益をあげていることを知り、ただちにその分け前を要求した。2017年以前の税法では、現金が海外にあるかぎり、税金を支払う必要なない。だがそれを本国アメリカに持ってくると、利益に対して法人税を支払わなければならない。そこでアップルは、金融市場に目を向け、そこで資金を借りて配当を支払うことで、あらゆる問題を解決した。つまり、利益を本国に戻さないようにして、支払うべき税金を回避すると同時に、株主が要求していた配当を提供したのである。」
銀行について、スティグリッツが辛辣なのはつぎの記述にもよく表れている(179ページ)。
「金銭欲があらゆる悪の根源というわけではないが、金融産業がアメリカの多くの病弊の根源であることは間違いない。金銭のことばかり考える銀行家に見られる近視眼的思考やモラルの崩壊が、経済や政治や社会に広まり、それらを毒している。その結果、アメリカ人はさまざまな点で変わった。実利的になり、利己的になり、近視眼的になった。」
ほかにもまだまだ紹介すべき記述が多くある。関心のある人はぜひともこの本を読んでほしい。グランドデザインのような視角がもてれば、枝葉末節な問題もその座標軸に沿って位置づけることができるようになる。こうすることで、日頃の断片的な知識をしっかりと価値づけることも可能になるはずだ。






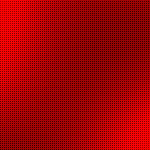


最近のコメント