「高貴な嘘」(noble lies)について考える
「高貴な嘘」(noble lies)について考える
塩原俊彦
みなさんは「高貴な嘘」(noble lies)についてご存じでしょうか。プラトンはRepublic(日本では『国家』と訳されることが多い)の第三巻のなかで、つぎのようにソクラテスに語らせています。
「われわれは適切に用いられるべき偽りのことを先ほど語っていたが、そうした作り話として何か気だかい性格のものを一つつくって、できれば支配者たち自身を、そうでなければ他の国民たちを、説得する工夫はないものだろうか?」(414b8-c2)
英語にすると、つぎのようになります。
Might we contrive one of those necessary lies of which we were just now speaking, so as by one noble lie to persuade first of all the rulers themselves, but if not that, the rest of the city?
この「気高い嘘」を統治に利用することをプラトンは肯定しています。国にいる者のすべては兄弟なのですが、神は、支配者として能力のある者には、その誕生に際して、金を混ぜ与えたと主張し、支配者たる哲人統治者によるnoble liesを許容しているのです。
もちろん、わたしはこのプラトンの主張に与しません。プラトンは「本当の偽り」と「言葉における偽り」を区別し、後者を人間にかかわる嘘として軽く扱っているのですが、神の存在が遠くなっている現在、嘘をこのようにみなす視角自体が間違っているようにみえます。
古典的名著『イメージ』
ここで「正しさ」を決める基準として、「本物かどうか」という基準を取り上げてみましょう。ここでは、少しだけ哲学的な話をしておきましょう。まず、古典的な名著とされている、1961年に初版が刊行されたダニエル・ボースティン著『イメージ』の話からはじめたいと思います。そのなかでは、「アイディール」(Ideal)から「イメージ」(Image)への思考の変化が強調されています。といっても、これだけでは、かれがなにをいっているのか、よくわからないでしょう。かれが〝Ideal〟と呼んでいるのは、〝Idea〟から派生した言葉です。
Idea(イデア)は望ましいなにものか、あるいは完全であるなにものかを意味し、人間の心のなかにだけ存在します。プラトンのイデア論では、現前にあるものは真の実在であるイデアの影(コピー)であるとみなされています。したがって、芸術作品はこのコピーのコピーにしかすぎないのです。こう考えると、普段、実在するものを真実であるかのようにみなしていること自体が虚偽(コピー)にすぎないことになるのです。したがって、プラトンのように考えると、目に見える世界はすべてコピーないしコピーのコピーにすぎず、目に見えるものに「真実」を見出すことを当然視している近代以降の常識がまったく通用しない世界が広がっていたことなります。
イデアはもともとギリシャ語ですが、これがキリスト教と結びつくことで、アイディールはヨーロッパでは、無矛盾のつくりごとではない状態として意識されるようになります。つまり、アイディールは伝統ないし歴史、あるいは神によってつくりだされたものということになります。この時代には、アイディールは完全なものであり、曖昧さをもたないものでした。わかりやすくいえば、人間は自らの見方や考えを神に仮託して、神のつくり出した秩序らしきものに従属させることで、神の命じる秩序を完全であるかのように受けいれていたわけです。そこでは、信用できるかどうかは問題にされませんでした。プラトンは「本当の偽り」を神に結びつけて、本当の偽りのないアイディールとしての神を強調したのです。
この神はキリスト教徒にもそのまま受けいれられます。アイディールは無矛盾の完全な状態としてすでにあるものであり、キリスト教徒にとって受けいれるべきものとしてあったのです。つまり、事実はまず神のもとにあり、その信憑性は問題にすべきものではありませんでした。そもそもフェイクかどうかは問うべきものではなかったわけです。
これは、正しさや真偽の問題が神に任されていた時代を意味しています。別言すると、神の意志である自然法が全面化していた時代のことです。
ところが、人間は〝Image〟というものをつかって、伝統・歴史・神から徐々に離れてゆくのです。このImageという英語は、ラテン語のimagoから派生しました。このラテン語の動詞形はimitariで、英語にすればimitateを意味しています。つまり、イメージは模倣するとか、模写するといったことに関連しています。いわば、イメージはあらゆる対象の外部形態の人為の模倣ないし代理物であるのです。模倣や代理物である以上、その真偽が問題にされるようになるわけです。そして、なりよりも大切なことは、イメージは人間が主体として生み出すものであり、人間の現実の世界にかかわる自然権(各人が固有の本性を維持するために自己の意志にしたがって自己の力を用いる自由)につながってゆくのです。
リスボン大地震
神の名のもとに、なにもかもを説明する、すなわち、完全なものたるアイディールから繙くという思考法が大きく揺らぐ事件がありました。それは1755年11月1日(諸聖人の日[万聖節])に起きたリスボン大地震です。5万人以上が死亡した地震と津波がカトリック教徒を襲ったことで、神によって人間の力の及ばない自然の猛威を説明することに対する疑問が広がったのです。天変地異に神の正義をみるのではなく、自然そのもののメカニズムにその原因をみようとする科学的思考が広がるきっかけになったと考えられています。それを実践したのが哲学者エマニエル・カントであり、かれはこの地震をめぐる書物さえ書いたのでした。興味深いのは、この地震と津波が人間の安全保障に対する問題を喚起し、これを神の正義の問題ではなく人間の問題としてみる視線を養ったことです。
つまり、神から距離を置いて、人間自身で考えることを重視するようになるのです。ただし、その際、人間の目で見えるものは現前するそのものではなく、光を介して網膜に映し出される像を脳が認知するだけですから、模倣・偽物にすぎないことがよく意識されていました。それでも、各人がそのイメージをもつことで、神の手から離れて、人間同士のイメージをもとに共通の感覚で理解を深められるようになったわけです。
ボースティンは「アイディール思考」から「イメージ思考」への変化が「グラフィック革命」によって促進されたと主張しています。グラフィックというのは、書かれたものや図や絵に示されたものを意味しています。この革命がはじまる前までの絵画は天地創造における神の仕業に帰せられる宗教色の強いもので、教会でしか目にしないようなものでした。しかし、グラフィック革命によってさまざまな絵画や情報が人々に入手可能となります。それを可能にしたのが製紙の技術であり、活版印刷術であったわけです。本を通じて、模写・模倣されたものが人気を集めるようになると、それが真実であるかのように擬制する事態になるわけです。ここに、真偽や信憑性を問う時代がはじまります。
民主主義とグラフィック革命
名著だけあって、ボースティンはなかなか興味深いことを指摘しています。
「18世紀と19世紀の民主主義革命と19世紀と20世紀のグラフィック革命はこの変化(「アイディール思考」から「イメージ思考」への変化:引用者註)に大いに寄与した」というのがそれです。なにがいいたいかというと、歴史的にみると、まず多くの人々による多数決に基づく民主主義の重要性の高まりがあって、それに呼応するかのように、グラフィック革命が起きて人間はますますイメージ思考を深めるようになったということです。人々が神の教えから距離を置きつつ、自らイメージして思考するようになるのです。
しかし、問題はその先にあります。民主主義の手続きを維持しつつ、人々が納得しながら全体の統治をうまく機能させるためには、一工夫が必要だからです。そもそも、人間は暴力によってのみ人々を統治できるわけではありません。人類は宗教を形成し、その宗教に導かれるようにして統治にいかしてきました。だからこそ、ローマ帝国はキリスト教を国教化して、統治に利用したのです。日本でも、聖武天皇の時代に仏教を統治に利用したのです。
加えて、「法の支配」(rule of law)も重要な統治方法の一つでした。皇帝や国王が死んでも、確固たるルールが堅持されなければ、かれらの死ぬたびに大きな混乱が生じてしまいます。これを避けるには、物理的に死ぬことのないルールとして、法が必要だったのです。
近代化によって、皇帝や国王に代わって、新しい国の統治方法が模索されるなかで、各人が民主的な選挙によって代理人を選び、その代理人が立法したり、行政を指導・監督したりする仕組みが生み出されました。とはいえ、選挙で勝利するには、選挙に勝つ必要があります。そのためには、イメージ思考をするようになった人々をうまく説得して一定の考え方に誘導することが求められるようになります。つまり、情報操作によってイメージという、曖昧なものの見方に働きかけて、統治者の有利になるような仕組みをつくり出すことが全体の円滑な統治に不可欠になったわけです。そのために、重要な役割を果たすようになったのがマスメディアです。グラフィック革命によって誕生した新聞やラジオ・テレビなどです。そこには国家とマスメディアとの共謀関係が存在し、「合意のでっち上げ」という現象が生じています。それは視覚に特権的な地位を与える時代でした。「見る」という行為は「必ず対象との間に距離が置かれていた」のですが、近年、脳と電子を直接結びつけることで人間の経験の直接性が問題化する時代が到来しています。そのため、本当は新しい秩序が必要な時代に入っています。これが最先端の話ということになります。
「標準」の決めにくさ
情報の正確さの話をわかりやすく理解するには、時計の正確さを考えればいいと思います。時計が正確かどうかの判断には、標準時との比較が使われます。つまり、「標準」になるものがあれば、比較対象となる時計の正確さをある程度判断することが可能となるのです。標準時でいえば、客観的時間をどう定めるかという議論があって、世界中の多くの国が認め合うことで成立しています。原理的にいえば、懐中時計や腕時計の普及で、時間がその持ち主によって異なるという主観的時間の広がりが困難をもたらしたために、客観的時間が必要になったわけです。
17世紀にゼンマイ時計による懐中時計の普及という形で、時間が共同体から労働を管理する個人である資本家の手に移ります。これは時間が共同体から個人の手に移ったことを意味し、さらに、組織の主体性も確立した結果、企業の工場においても、時計が重要な役割を果たすようになります。タイム・カード・システムまで生み出されます。あるいは、やがて正確に時間をはかることのできる時計によって、記述可能な仕事の役割ごとの労働者の最適配置、作業過程の分割や配列といった、「科学」に基づく管理(テイラーシステム)までもが可能になるのです。
これは、資本家が教会といった共同体に代わって、資本家個人のレベルで時間を自由に創出できることを意味しました。自己の内面に意識をつくり、意識によってとらえる時間と、機械を媒介にして固有の動きを示す時間とを分離してとらえることを促したことになります。後者は共同体から離れて、自由な時間を所有するという観念を広げたわけですが、その自分だけの時間が逆に、バラバラになってしまった人間に客観的な時間を必要とさせるようになるのです。労働時間を賃金支払いの規準とするようになった資本家が時間をごまかさないようにするためにも、時間を平等にするための「客観化」が必要になります。
産業化という企てを象徴する鉄道もまた、客観的な時間を必要としました。列車の出発時刻や到着時刻を正確に把握できなければ、鉄道の円滑な運行は不可能だからです。こうして秒針まで取り付けられた時計が出現するようになり、抽象的な量としての時間概念が細分化され、しかも支配的になります。その結果、世界経済という場においては、ますます客観的な時間が必要とされるようになるのです。ゆえに、1885年、国際子午線会議で、英国のグリニッジ子午線を基礎子午線とした国際標準時の制度が創設されたのです。
これと同じように、世界全体が納得するような正義の判断規準としての「標準」が創出できれば、情報の正確さの判断に役立つでしょう。しかし、宗教や慣習、文化の違いから、正義のための「標準」をつくり出すは難しい。それが現実なのです。したがって、そもそも「正確な情報」そのものがないのです。
「意図的」という重さ
したがって、ほとんどすべての情報は「不正確」と極言することさえできます。ただし、そうした不正確な情報を意図的に流すとなると、事態は重大になります。つまり、日常、人々は情報が正確であるかどうかを簡単に判断することはできませんが、それに乗じて、不正確な情報を意図的に流すというのは少なくとも信頼に基づく「仁」という論語の世界観に反しています。孫子の「詭道」に沿って、敵を騙したり欺いたりする行為に映ります。「意図的であるかどうか」がディスインフォメーションであるかどうかを決定づけるうえではきわめて重要なのです。孫子の詭道を前提とするような地域では、歴史的にみて早くからディスインフォメーション工作が行われていました。幸か不幸か、日本のように「和」に基づく信頼を重視してきた日本では、意図的で不正確な情報を流して混乱させる必要はあまりありませんでした。
たぶん、嘘は本来、「意図的」につくものなのかもしれません。無意識に嘘をつくことはないはずです。意識せずに嘘を言ったのであれば、それは無意識のなかにあった嘘を言葉にしたのでしょう。そう考えると、「意図的で不正確な情報」たるディスインフォメーションは「情報発信者が嘘と知りつつ発信する情報」、あるいは虚偽情報に基づくニュースを意味する「広義のフェイクニュース」と言い換えることができます。
深刻な「再現可能性」問題
わたしがnoble liesに関心をもった理由をのべましょう。みなさんは、2018年4月に米国のNational Association of Scholars(NAS)が公表した「近代科学の再現不可能性危機」(The Irreproducibility crisis of Modern Science)という報告書を知りませんか。その序文は、「あたなの前にある研究は科学における統計の利用と濫用の審問の記録である」と書かれています。NSAは1987年に「科学の政治化」への危機感から設立された団体です。実は、気候変動(日本では地球温暖化と誤って理解されています)や人工知能(AI)などの分野で統計がふんだんに使われており、そこに「政治」が絡まりやすいことを心ある米国の研究者はよく認識していました。
この報告書の結論部分には、つぎのような指摘があります。
「近代統計学に基づく研究の欠点はわれわれをあまり驚かせないだろう。いまだにそうした欠点は大きな害をなしているし、科学自体の権力や有望さにおける信頼を傷つけている。われわれが必要としているのは、新しいインセンティブであり、新しい制度的メカニズムであり、そして科学が間違いうるすべての方法に新たに気づくことである。」
「科学の真理の探究が必要としているのは、科学の専門家の活動を精査し、批判することであり、かれらとともに近代科学の実践改革に取り組むことである。」
そのうえで、あとがきとしてウィリアム・ハーパーはつぎのようにのべています。
「多くの科学者は自らを、多くのみじめさのなかにいる人々よりもずっと優れた哲人統治者(キング)であるとみなしている。みじめな人々は科学者がなぜ特別であるかや、みじめな人々がなぜ科学者に指示されたように投票すべきかを理解するのに困難な時代にある。2000年以上前、プラトンは哲人統治者というイデアを推し進めたが、同じく、「気高い嘘」という概念を称揚した。それは、懐疑的な住民が喜んで哲人統治者による支配を受けいれるように説得するためにデザインされたでっち上げである。われわれの現在の科学コミュニティはときとして統計学におけるより優れた訓練によってもとらえきれない問題を気高い嘘に訴えてきた。気高い嘘は再現不可能であり、科学の信用を損ねている。」
統計の問題は科学全体の問題
わたしからみると、日本の科学者はまったく不勉強と指摘しなければなりません。いま問題になっている統計の問題は実は科学全体の問題といってもいいくらい深刻な問題なのです。とくに、AIは統計そのものに基づいているといっても過言ではありません。ビッグデータの処理は統計学に基づいているからこそ、ブラックボックス化してしまうと言ってもいいのです。
具体例をあげましょう。2016年の米大統領選でドナルド・トランプを勝たせる要因の一つとなったとみられているのがケンブリッジ大学のアレクサンドル・コーガンとケンブリッジ・アナリティカによる情報操作でした。2013年、コーガンはFacebook利用者に質問するためのアプリ(「これがあなたのデジタル生活」)を開発し、30万人ほどがそれをダウンロードしました。かれらは総計で5000万人以上の友人をもっていました。コーガンはこれらのデータをケンブリッジ・アナリティカに提供し、同社はそのデータを利用して顧客であるトランプ陣営などの運動に活用したのです。Facebookが2018年4月4日に公表した数値によると、Facebookを通じてケンブリッジ・アナリティカが不適切に情報をシェアした可能性があるのは、米国が7063万2350人(全体の81.6%)、ついでフィリピンの117万5870人(同1.4%)、インドネシアの109万6666人(同1.3%)、英国の107万9031人(同1.2%)などとなっています。全体の総数は8700万人です。
コーガンは同じ時期にケンブリッジ大学に在籍していたマイケル・コジンスキーによる「サイコメトリクス」(心理統計学)の研究を知っていました。サイコメトリクスは、パターンの統計学上の分析データを使って、心理テストの回答者の人間像を類推する方法(プロファイリング)に関係しています。わかりやすくいえば、ネット上で「いいね」をクリックした人物像を類推できると言われています(統計を用いるわけですね)。この方法をコーガンは利用して、特定の政治的傾向をもつ人への情報操作に加担したわけです。
DARPAのあせり
日本の科学者のアホさに比べると、さすがに米国は違います。インターネットをはじめとする最新科学技術を発明してきた国防高等研究計画局(Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA)はSystematizing Confidence in Open Research and Evidence (SCORE)と呼ばれるプログラムを推進しています。再現可能性に対する責務を果たそうとしている非営利組織、Center for Open Science(COS)に760万ドルを拠出することをDARPAは約束しました。COSは社会科学にかかわる3万もの主張を総計しデータベース化して、このうち3000の主張について再現・反復を試みるとされています。
今後ますます統計処理に基づくAIのような最新技術の重要性が高まる以上、それが再現可能な真実と認定できるかを精緻に調べる必要があるわけです。
統計のインチキ
実は、統計がインチキであることを明確に主張したのは、フリードリヒ・ハイエクでした。かれは1945年の論文「社会における知識の利用」のなかで、興味深い指摘をしています。
かれは、政府という「中央当局」が利用する知識は「統計」という形をとることが多いことに注目します。ハイエクは、この統計が、ものごとの間の些細な相違点を取り除くことで、あるいは、ある決定のためにきわめて重要かもしれない場所、品質、その他の特性に関する相違項目をひとまとめにすることで得られることに注意を向けました。国は些細な違いに目を瞑り、だいたいこれくらいだろうという数字を紡ぎ出してよせ集め、それを根拠に上から政策決定をするのです。ただ、これでは時間や場所によって異なる特定の状況変化には対応できない。むしろ、それぞれの場所の近くにいる人々に多くを任せたほうが迅速で臨機応変は対応が可能となる。
だからこそハイエクは、「われわれは非中央集権化を必要としている。なぜならわれわれは、こうした状況においてはじめて時間と場所の特定状況についての知識が迅速に利用されると請け合うことができるからだ」と記述しています(Hayek, Friedrich [1945] “The Use of Knowledge in Society,” American Economic Review. XXXV, No. 4, p. 524)。彼の指摘するように、政府といった中央が情報を処理して「上」からなにかを決めること自体に本来的な限界があると指摘しなければならないのです。そして、そこに統計が利用されてきたし、今後、AIを通じてますます上からのデザイン性が強まることは確実です(偶有性[contingency]という概念こそきわめて重要なのですよ)。
GDPの不正を糺せ
このようにみてくると、統計学そのものに不信感をいだかざるをえません。それでいいのです。まさに、それがいま真剣にDARPAによって問われているわけですから。問題は、そうした疑問に真正面から取り組もうとしない日本の科学者や政治家にあります。いまが絶好のチャンスなのです。統計のそもそもの限界を知り、その利用に基づくAI信奉に一撃を加えるべきなのです。その意味で、DARPAの取り組みは重要です(こうした最先端の最重要な課題に気づいていない日本の学者、政治家、官僚、マスコミ人ははっきり言ってバカそのものですね)。お願いだから、もっと世界に目を見開いてほしいと思います。
心から科学への信頼性を取り戻したいのであれば、GDPの不正操作が内閣府によって行われた事実を徹底究明すべきでしょう。このサイトでは、この問題について何度か指摘しましたが、GDPも統計そのものであり、本来、あまり重きを置くべきものではありません。それでも、意図的に操作された数値をつくって日本国民ばかりか世界中の人々を騙してきたとすれば、Dishonest Abe政権はいますぐ退陣すべきでしょう。
わたしのみるところでは、Dishonest Abe、安倍晋三はnoble lieではなく、indecent lieをついているようにみえます。



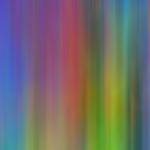


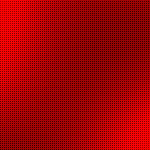


最近のコメント