21世紀の最大の問題について:肉体とデータの所有権について
21世紀の最大の問題について:肉体とデータの所有権について
塩原 俊彦
「21世紀の龍馬」という視点に立つとき、おそらくもっとも重要な問題となるのは肉体とデータの所有権をめぐる議論ではないか、そう最近、思うようになった。前者は医療の進歩にかかわる問題であり、後者はデータやメタデータの取り扱いに関連している。その意味で、資本主義の最後のフロンティアである医療と情報の問題に直結した問題とみなすことができる。そして、この二つの問題は、プライバシー問題に通底しており、人間の倫理に深く関係している。
所有権をめぐる一般論
所有権は一般に、占有権と処分権からなっている。この一般論に準拠すると、肉体には所有権は認められない。肉体に所有権を認めてしまえば、肉体全体を構成する人間自体の商品化、すなわち奴隷売買を認めることにつながる。肉体の一部についても、その所有権を認めると、臓器売買につながる。ゆえに、人間は肉体に対する自分自身の所有権を認めていない。
こう議論すると、違和感を覚える人が少なからずいるだろう。その違和感はただ、キリスト教徒にはあまり感じられないのではないか。なぜならキリスト教徒にとって、肉体は神が創造したものだからだ。
ジョン・ロックの所有論では、自分の身体が自分のものであると主張できるとは考えていなかった。彼は、人間は自分の肉体ではなく、人格に対してのみ所有権を認めているにすぎない。なぜなら、肉体を創造したのは神だからだ。
「所有」を考える
私は拙著『すべてを疑いなさい』などで「所有」について考えたことがある。『所有の歴史』を書いたジャック・アタリは、「最初の所有は生命であり、最初の欠如は死であった」と指摘している。それは「食人」において、人間の肉体の一部をモノとしていたことに関連しているが、それは「所有」の対象というよりも「占有」の対象であり、だだ「持つ」対象でしかなかったということを意味している。もちろん、人肉以外の食糧も「持つ」対象であった。自分の子供、自分のつくった物品もそうだ。その対象を用益したり使用したりすることと、手放したり売ったりすることとの間の差が不明瞭で、何でも可能であった時期ともいえる。
牧畜の段階になると、家畜は一般に氏族の「集団所有」の対象となった。といっても、この段階でも、家畜は「持つ」対象でしかなく、集団が「持つ」対象として家畜が存在しただけのことだ。個人が「持つ」対象は個人がつくりだしたものなどに限定されていた。
それでは、「私的所有」という見方はどのようにはじまったのか。それは、神のもとで人間がモノを支配し処分できる権利をどこまでどう認めるのかという問題に対する回答を迫った。アタリによれば、1270年ころ、トマス・アクイナスが『神学大全』のなかで、人間の権利として、①労働によって獲得されたものについて、②過度な重要視をしない――という条件のもとに、用益権と財を消費する権限を認めたことが「私的所有」につながったという。この二つの条件さえ満たしていれば、物財、生産用具、奴隷さえも「私有」できるようになった。
このとき、人間は「私的所有」する対象を使用するだけでなく、「自由」に処分できるという権限を含んでいたから、「私的所有」は個人の「自由」という問題にも明確な方向性を出した。言わば、商人の「自由」な活動を促したことになる。「私的所有」はそれまで曖昧だった「集団所有」や個人の「占有」をより明確にすることを意味し、その集団や個人からの「自由」を個人にもたらしたのだ。「自由」な売買が可能な財貨は「商品」となるから、「私的所有」は商品経済化を促したことになる。
「所有」の対象
もちろん、そのとき、何が「所有」の対象となるのかも問題になる。そこで最大の問題となったのが土地だ。土地は長く「占有」の対象であったが、土地を金銭で売買するという慣行はそう簡単に可能になったわけではない。土地を商品化するには、ジョン・ロックの主張が必要であったのだ。
すでにのべたように、人間は飢えをみたすために食糧を領有するようになる。人間は「働くがゆえに所有し、所有者であるためには働く人でなければならない」という見方が広まった結果、その労働によってもたらされた生産物を売買の対象とし、「所有」の対象が拡大したのである。さらに、ロックは「自然が置いたままの状態から物をひき離すたびごとに、人間は自分の労働を加え、自分に属する何かを合体させ、このことによりそれを領有する」とみなした。この結果、人間は「土地」という「自然が置いたままの状態」の「私的所有者」になりうると主張した。つまり、ロックは、「私的所有」の正統性を、食糧から身体へ、身体から精神へ、精神から労働へ、最後に労働から土地へと拡大させていったことになる、とアタリは指摘している。
さらに、「所有」は人間そのものではなく、人間の生み出す労働力を売買の対象とするようになる。産業資本主義と呼ばれる段階になると、「労働力の商品化」という事態が起こる。それだけではない。「情報の商品化」、「知識の商品化」へと「所有の対象は拡大してきたのだ。
「所有」の蓄積手段=「貨幣」
「私的所有」が認められるようになると、個々人の「所有」の安全性の確保やその「蓄積」や「相続」が問題にある。そこで、「貨幣」の重要性が増すのである。
「貨幣」には、「貨幣の前駆的形態」と呼ばれる時期があった。この「貨幣の前駆的形態」では、共同体と共同体との交換のなかから、「価値あるもの」が普遍的な信用に裏づけられた支払い手段として機能していた。等価交換を前提とする市場の形成期を迎えると、普遍的な信用に支えられた支払い手段としてだけでなく、購買手段としても機能するようになった「貨幣」が生まれる。だからこそ、大澤真幸は、「貨幣とは、市場において、他の任意の資源(の一定量)に対する交換手段として機能する普遍的(一般的)な媒体mediaのことである」と定義している。
「私的所有」の背後にある哲学
「私的所有」が可能になった背後には、デカルト的な二元論があったことを忘れてはならない。デカルト的な心身二元論をとれば、「デカルト的な私=魂は、物体のみの世界と一人向かい合い、世界内の「この」体を所有し、意のままに動かす主体となる」と大庭健が『所有という神話』で指摘しているように、自らの身体を意のままに動かす主体としての「私」という概念が成立しなければ、「私的所有」の「私的」という考え方そのものが成立しえないからだ。この意味で、「私的所有」というものは決して、単純なものではなく、「疑い」の目を向けるべきいかがわしさを伴っているのだ。
他者の承認
ここで重要なのは、そのとき認められるようになった「私的所有」が「他者」の承認を前提にしていたことだ。最初は、神ないしキリスト教会、あるいは王という「他者」によって「私的所有」が認められたことになる。しかし、ロックは「私的所有」を守る「他者」として、市民が社会契約を結び、共同で統治する民主政体を主張した。ここに、代議制民主主義という考え方が明確に打ち出されたことになる。したがって、「私的所有」の問題は民主主義の問題でもあるのだ。
ゆえに、現代を生きる私たちは「所有」を大庭健のように、つぎのように理解しなければならない。すなわち、ある人PさんがあるものXを「所有している」ということは、「どのようにXを用益あるいは処分するかを、Pさんが一人で排他的に決定することを、Xに関心をもつ他者たちが承認する」という風に。
繰り返しになるが、ここで重要なことは、「所有」が原理的に「他者」による承認を前提にしていることだ。簡単にいってしまえば、「資本制=ネーション=ステート」を前提にすると、「私的所有」とよばれるものは「ステート」ないし「国家」による承認を前提にしている。「私的所有」といえども、国家の枠内でしか対象の用益・処分を排他的に決定できないのだ。つまり、個人も法人も「私的所有」を神聖不可侵と主張することはできない。土地や地下資源などの天然資源は、生態系の一部だから、なおさら、その「所有」について「他者」による承認を受けなければならない。それは国家ないし自治体やコミュニティによる承認ということになるかもしれない。いずれにしても、地下資源や土地が純然たる私有対象であっても、国家規制や自治的規制の対象にならざるをえないのだ。
大庭はこうした規制を「公共的規制」とよび、つぎのように指摘している。
「こうした公共的規制は、厳格になればなるほど、伝統的な権利概念からすれば「所有権の侵害」と映ろう。しかし、これを「権利の侵害」ととる発想が、むしろ問題なのである。規制が強くなれば、所有者の宅地への関係は、用益・処分の排他的決定すなわち「所有」であるよりも、むしろ「共有地の一画の恒常的利用」と言うべきものに近づいてくる。そして、これは、所有権の神聖を旗印とした近代の閉塞状況において、一般的には歓迎すべきことである」
つぎに問題になるのは、その規制方法についてである。再生産すべき社会的資源が特定されている各システムにおいては、システムに参与した諸個人は、その資源の再生産への「貢献」に応じて、再生産された資源を用益する機会を分配されるべきだという、競争主義的な規範原理がある。そうすることで、システムの「効率」を高めることが可能となると考えるわけである。土地や地下資源などの天然資源に関連させて考えると、その資源の再生産に「貢献」したかどうかの「尺度」をどう決め、何の分配についていかなる差異を正当化しうるかが問われることになる。そこで、規制が問題化する。
天然資源には再生可能資源(renewable resources)と非再生可能資源(non-renewable resources)がある。前者は魚や森林、水などにかかわる資源であり、後者は石油、ガスに代表される鉱物資源をさす。土地の場合、その肥沃度はある程度、再生可能だが、一度、汚染されてしまった土地を元に戻すのは困難である。ここでは、基本的に再生産そのものが困難な天然資源についてのみ検討すると、経済システムにおいては、天然資源の再生産ではなく、生産・消費にかかわるなかで、利潤の増加が目標になっていることがわかる。もちろん、生態系システムにおいては、非再生可能資源の無尽蔵の費消は生態系を守るという目標からみると、避けるべき事態ということになる。
経済システムのうえでは、利潤増加という目標に向かってどれだけ「貢献」したのかをみる基準として、市場の「見えざる手」による測定が考えられている。ある天然資源への需要が大きく供給が少なければ、その天然資源を提供する行為の「社会的貢献度」はそれだけ大きいとみなすのである。しかし、この考え方はおかしい。第一に、大庭が指摘するように、「「需要が大きく供給が少ない」ものを提供するということは、それ自体として社会的「貢献」の多寡とは連動しない」といえる。たとえば、比較的安価な石炭への需要が大きくても、石炭の燃焼に伴う空気汚染を考えると、天然ガスを提供したほうが「社会的貢献」につながるのではないか。第二に、たとえ「需要が大きく供給が少ない」ものを提供する行為が貢献度の高い行為だとしても、その商品を生産し供給する過程は、同時に多くの廃棄物を撒き散らす過程でもある。第三に、市場を通じて需給関係を把握することができるということ自体が幻想にすぎない。石油価格の高騰がつづいているとしても、それは単に需給関係を反映したものとは言えない。国際的な低金利のなかで、投機資金が流入した結果とも言える。したがって、経済システムだけをみても、そこでの天然資源の生産・消費にかかわる「貢献」を評価する明確な基準を想定できるわけではない。
「貢献」を評価する明確な基準をもたないまま、天然資源の生産・消費に伴って利潤が増加したとして、そこには、①利潤はだれのものか、②利潤とは何か――という大きな疑問が生まれる。
第一の疑問について考えてみよう。すでに指摘したように、天然資源の所有者は排他的に天然資源の用益・処分を認められているわけではない。したがって、国家規制や自治的規制の対象になる。その規制は利潤の一部を徴収し、再分配するということであってもかまわない。問題はその徴収方法や徴収額ということになる。そして、その問題は天然資源の生産者にどの程度の利潤を認めるのかという問題、つまり生産者にとっての「利潤とは何か」という第二の疑問に関連することになる。しかし、「貢献」を評価する明確な基準がない以上、利潤とは何かを決めるのは難しい。
肉体やデータにどう応用するか
ここまでの記述を肉体やデータに対する所有権の問題にどう応用するか。それが「21世紀龍馬」に課せられた課題である。
近年、臓器の売買、精子や卵子の取引といったことまで、平然と行われる時代に入っている。まさに、「ボディショッピングの時代」に突入したのである。米国では、1987年の統一死体提供法によって、人間の臓器、死体の売買は禁じされている。にもかかわらず、「われわれは自分のからだから切り離された組織を所有していない」というアングロサクソン的価値観に基づくコモン・ローおよび英米法の体系を利用して、抜け穴を見つけ、事実上、「ボディショッピング」が隆盛しているのだ。『ボディショッピング』を書いたドナ・ディケンソンによれば、フランス、ベルギー、オランダなどの大陸法のもとでは、手術によって切除された組織は廃棄されたものとみなされているのだが、「いずれの法体系でも、組織の切除、あるいは提供についてインフォームド・コンセントが実施されれば、本人はその所有権を失うことになる」という。あとは、その断片を利用するのは早い者勝ちであり、そこには、他者を出し抜いて金銭的利益を得ようとする企てが渦巻いている。
データについて言えば、コンテンツたるデータの内容はともかく、コンテキストたるメタデータについては売買の対象となっている。しかし、本当にメタデータはそれを生み出した者の合意なしに勝手に売買してもいいのだろうか。位置情報というメタデータだけで、十分に個人が特定できると、最近、ニューヨーク・タイムズ紙がキャンペーンをはっている。もっとこの問題に敏感であってほしい。なにしろ、プライバシーが毀損されている可能性が高いのだから。
加えて、データを資産とみなせるかという問題もある。最近、コンテツとしてのデータは無形資産として価値をもつという見方が高まっているようにみえる。そうだとしても、その無形資産への処分権までが認められるかどうかには議論がある。一般に、所有権には占有権と処分権の二つがあり、この二つの権利を併せ持たなければ所有権があるとは言えない。無形資産たるデータがサイバー空間上にあるとき、その所有権までは従来、認められてこなかった。
2018年7月12日になって、ドイツの民事事件の最高裁にあたる連邦裁判所は興味深い判決をくだした。2012年に15歳で死亡した娘が自殺したのか、事故だったのかの究明を求める両親がFacebookに娘のアカウントの開示を請求すると、死後に閉鎖したアカウントであってもプライバシー保護の観点から開示できなとした。そこで、両親は娘のFacebookの内容の開示を求めて裁判を起こしたのだ。2015年の第一審では、両親はFacebookのアカウントのコンテンツは個人の日記ないし手紙と法的に同じようなものであり、相続のように死後、両親に戻されなければならないと主張した。一審は、娘とFacebook間の契約がアカウントに創出されたデジタルコンテツであっても相続法でカバーされることを認めた。さらに、両親は娘がいつだれとコミュニケーションをとったかを知る権利があるとした。両親側にサイバー空間上の無形資産の所有権を認めたと解釈できなくもない。
だが2017年の控訴審では、憲法たるドイツ基本法で通信のプライバシーが保障されていることを理由に両親の訴えを却下した。加えて、裁判官は娘とメッセージを交換した人々には個人的なデジタルコミュニケーションの保護を受ける資格があるとの会社側の言い分を支持した。これに対して、連邦裁判所は手紙や日記は相続人に渡されるものであり、デジタルコンテンツであっても差別する理由はないとして、逆転して両親の求めを認めた。
相続は、人の死亡によってその人に属していた財産上の権利義務を一定の身分関係にある者が受け継ぐことだから、Facebookのアカウントにあるデータに財産上の価値を認め、その無形資産へのなんらかの権利を明確に認めたことになる。その権利が所有権と呼べるものであるかは微妙だが、少なくともFacebookのアカウント保有者が自分のアカウントデータに多少とも権利を有することがはっきりしたことになる。
こんな事例を踏まえたうえで、データについても肉体についても所有権と絡めて真剣な検討が必要だ。そんなことを2018年の終わりに考えている。


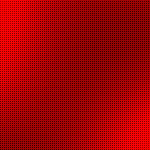






最近のコメント