ウクライナの中立性をどう担保するのか:ウクライナ憲法問題
巷間知られているように、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は2024年6月14日に外務省幹部に向けての講話のなかで、「我々はキエフにロシアとの交渉の禁止、つまり自ら課した禁止を解除するよう命令を下すだろう」としたうえで、具体的な和平条件を語った。
その条件を列挙すると、①ドネツク、ルハンスク、ザポリージャ、ヘルソン地域からの軍隊の完全撤退に同意し、このプロセスを実際に開始したならば、我々は遅滞なく交渉を開始する用意がある、②ウクライナの中立的な非同盟非核地位、非武装化、非ナチ化というのが我々の原則的な立場である、③ウクライナでロシア語を話す市民の権利、自由、利益は完全に確保されなければならない、④クリミア、セヴァストポリ、ドネツク人民共和国、ルハンスク人民共和国、ヘルソン地方、ザポリージャ地方の新たな領土的現実とロシア連邦の構成主体としての地位は承認されなければならない、⑤将来的には、これらすべての基本的かつ基本的な条項は、基本的な国際協定の形で確定されるべきである、⑥西側諸国の対ロ制裁の中止――となる。
中立性をめぐって
このなかで、もっとも重要とされているのがウクライナの中立性の確保だろう。そこで、今回はウクライナ戦争の停戦・和平に向けた交渉に際して、もっとも重要な課題となっているウクライナの中立性について論じたい。最近になって、中立性を確保するために、2019年2月7日付の憲法修正で第85条5項に「内政・外交政策の原則を決定し、ウクライナの欧州連合(EU)および北大西洋条約機構(NATO)への正式加盟を目指す戦略的方針を実施する」という規定の取り扱いが問題視されているからである。
ここではまず、マーク・ウェラーケンブリッジ大学国際法・国際憲法学教授の論文「ウクライナ和解の選択肢: 中立性と関連概念」をもとに、「中立」をどう確保するのかという問題について説明してみたい。
中立性をめぐって
ウクライナの中立性を確保する際、その選択肢は(1)永世中立、(2)NATO非加盟の特定義務、(3)非同盟の立場、(4)EU――という四つがある。それぞれについて、簡単に説明してみよう。
(1)永世中立
永世中立とは、国家が現在または将来の武力紛争(または伝統的には戦争)において、いずれの側にも加担しないことをあらかじめ誓約することである。これにはいくつかの要素がある。①中立国は他国が起こす武力行動に参加してはならない、②軍事支援、基地使用権、通信施設の燃料補給、その他の支援を提供してはならない、③中立国は防衛同盟に参加することはできない、④中立国はまた、外国や同盟国に軍事基地やその他の施設を提供することもできない――などがその要素である。
恒久的中立を確立するにはどうすればいいのだろうか。ウェラーは七つの方法を紹介している。第一は、国際的体制で、多くの主要国家間のより広範な世界体制の一部として、中立国を堅持する場合である。例としては、1815年のウィーン会議における中立国スイス、1839年のロンドン会議におけるベルギーなどがある。
第二は、少数の国家間の条約によって確立される場合である。その場合、その条約は、当該国家の中立的な地位を明確にするために、また、その地位を保証するために特別に締結された可能性が高い。やや異なる文脈ではあるが、1960年にキプロス、ギリシャ、トルコ、英国の間で締結されたキプロスに関する4カ国間条約がその例である。この条約は、キプロスが(ギリシャに加盟するのではなく)独立国家としての地位を保証することを目的としていた。
第三の方法は地位の承認である。当該国家は、その将来の地位に関する宣言を行う。 その後、他の国家によって恒久的中立国として承認され、中立国が負う義務が確認される。この承認は、たとえば、トルクメニスタンが国連に加盟した際に採択された総会決議のような集団的行為の形態を取ることができる。
第四は、安全保障理事会による固定化だ。ウクライナの中立の地位は、国連安全保障理事会の拘束力のある第7章決議によって固定化することができる。このような規定は、その後は常任理事国であるロシア連邦の賛成票によってのみ変更することができる。しかし、このような解決策の例は存在しない。むしろ、「おそらくは、和解合意全体が安全保障理事会によって承認されることになるだろう」、とウェラーは指摘している。
第五は、憲法上の規定である。中立は、国家憲法に規定することができる。モルドバのように、国家憲法自体に永世中立の規定を盛り込むことも可能である。あるいは、1955年のオーストリア国家条約に基づきソ連軍が領土から撤退した直後にオーストリアがとったように、憲法上の地位を議会が宣言するという形を取ることもできる。オーストリアの場合、この宣言は明らかにソ連軍の撤退完了と関連していたが、「自発的な永世中立」として発表された。
第六の方法は、一方的な宣言である。中立維持の義務は、大統領または政府首脳が全世界に向けて厳粛に宣言することによって法的拘束力をもつ(1834年のスウェーデン)。国際法上、このような宣言は「万人に対して拘束力を持つ」ものであり、他のすべての国家は合法的にその宣言に依拠することができる。一方的な地位宣言のより最近の例としては、2008年のコソボ独立宣言がある。中立を義務づけるものではないが、この宣言は、コソボが国連のコソボ包括的解決案の条件に完全に準拠することを法的に拘束力のある形で約束するものである。
第七は、非公式な政策だ。国家は、法的拘束力のある義務を負うことなく、自国が中立であると宣言することができる。宣言は、特定の政策の表明であり、国際法上の義務の表明ではない(フィンランド)。
このように、永世中立の確立には、複数の方法がある。それらを組み合わせることで、より堅固な永世中立の実現につなげることもできる。加えて、恒久化のために、憲法において、恒久的中立が憲法に明記されている場合、関連規定の改正または削除には、憲法改正に必要な多数決が必要となるから、それだけ恒久化へと近づくことにつながる。憲法における恒久条項を設けるという方法もある。憲法の特定の条項を改正または削除する選択肢を排除する恒久条項を設けるのだ(ドイツ憲法の場合と同様)。このように保護された規定を覆す唯一の方法は、現行の憲法を完全に廃止するような革命的な変化を通じてのみ可能となる。
(2)NATO非加盟の特定義務
恒久的中立は、あらゆる防衛的取り決めへの加盟を排除するが、別の選択肢は、より限定的な制約について交渉することである。すなわち、ウクライナを完全に中立国とすることなく、NATO加盟を排除するものということになる。この制約は、NATOだけに焦点を当てることもできるし、東西のいくつかの指定された軍事同盟との提携をカバーすることもできる。
①NATOによる排除:第一の選択肢は、NATOがウクライナの加盟を認めないという決定を下すというものである。これは、2008年のブカレスト・サミットで下された決定を覆すことになる。NATOが「門戸開放」政策を維持するということを繰り返し確認していることを考えると、この選択肢は非常に考えにくい。しかし、ウクライナ自身がNATO加盟を求めないことを宣言した場合、NATOはこれを理解していることを記録することができる。
②NATO加盟国による保証:主要なNATO加盟国が、ウクライナがNATOに加盟しないことを保証する可能性がある。これは、たとえば、ウクライナがまずNATO加盟を求めないことを宣言した上で、米国が和解合意に別紙を添付する形で実現する可能性がある。
③自己制限:ウクライナ自身がNATO加盟を排除する可能性もある。その場合、この公約をどのように担保するかという問題が生じる。中立性と同様に、特定の同盟に加盟しないという誓約は、ウクライナの法律や憲法、国際協定、あるいは法的拘束力のある一方的な宣言によって確立される可能性がある。おそらくは、これらを組み合わせた形になるだろう。NATO加盟を否定する場合は、12年間の期限付きの誓約とするか、それとも恒久的なものとするかが問題となる。
(3)非同盟の立場
三つの選択肢は、非同盟の立場と非同盟運動への参加を約束するというものだ。非同盟運動のメンバーは、主要な同盟に参加しないことを誓約している。しかし、非同盟運動には正式な憲法はなく、関連する義務は基本的に政治的なものであり、新しい経済秩序、人種差別の撤廃、一方的な制裁措置への反対など、さまざまな問題に関する進歩的政策の追求にも関連している。したがって、非同盟は、交渉当事者間で議論されている法的拘束力のある義務というよりも、むしろ国家の政策優先事項を表明するものである可能性が高い。
(4)EU
EU加盟と中立性を両立させるという選択肢である。ロシアは、ウクライナの中立性追求にはEUへの加盟をしないという確約が必要だと主張する可能性がある。一方で、欧州議会や一部のEU加盟国は、ウクライナのEU加盟プロセスを加速するよう強く求めている。実際、ウクライナが恒久的中立を誓ったとしても、加盟が除外されるわけではない。
アイルランドのEC/EU加盟が示したように、またそれ以降も中立政策を掲げる他の加盟国が加わっているように、共通外交・安全保障政策におけるEUの役割がますます強まっているにもかかわらず、この事実を考慮して加盟に際してEUへの参加形態を変更することは可能である。
しかし、EU加盟には加盟国の領土保全に対する義務が含まれる。欧州連合条約第42条(7)項によると、「加盟国が自国の領土において武力攻撃の犠牲となった場合、他の加盟国は、国連憲章第51条に従い、自国の能力の及ぶあらゆる手段により、当該加盟国に対して援助および支援を行う義務を負う」とされている。最終的にウクライナがEU加盟条約を締結した場合、この規定の適用は遅れる可能性がある。一方、安全保障保証に関する選択肢のペーパーで指摘されているように、この規定がウクライナの安全保障保証の問題に実際に役立つ可能性もある。
ウェラーの結論
ウクライナが譲歩できるもっとも限定的な条件は、「永世中立を受け入れずに、NATO加盟を明確に排除することである」というのがウェラーの結論である。これは、NATO加盟国(米国)から、ウクライナを一定期間、あるいは永久にNATOに加盟させる見込みはないという側面保証を得ることで裏づけられる可能性があるという。
もし中立が合意される場合には、多くの問題を明確にする必要がある。第一に、中立政策は二面性を持つ。すなわち、NATO加盟を排除するだけでなく、将来的にウクライナで政治的変化が起こった場合、東方諸国との同盟関係も排除することになる。第二に、永世中立を宣言するのか、また、そうであるならば、その永世中立をどのように確立するのか。中立の確立は、おそらく二重、三重に担保される必要がある。和平合意に盛り込まれ、安全保障が確約される場合には保証文書にその旨が明記され、場合によっては安全保障理事会決議で承認されることになるだろう。また、国内法や憲法に定めることも考えられる。
中立の場合、中立国として効果的な防衛を準備する権利、そして実際にはその義務をウクライナが明確に確認する必要もある。これには、その目的のために自らが選択する国家や組織から兵器を調達する際に支援を受ける権利も含まれる。この(軍事的)中立の解釈に従えば、兵器制限はロシア連邦の奥深くまで到達可能な大量破壊兵器や長距離兵器のみに適用されるべきであるということになる。
恒久的中立を維持するには、ウクライナが領土保全を防衛できることを他国に保証できる相当な実効的な軍事力が必要である。通常兵器に関するより厳しい制限は、効果的な国際安全保障保証によってバランスを取る必要がある。このとき、すでにのべたように、将来的なEU加盟でさえも、完全な中立性と一致させることができる。
いまウクライナで起きている問題
中立性の確保が課題になっているウクライナはいま、難問に直面している。憲法第157条の規定により、「ウクライナ憲法は、戒厳令や非常事態の下では改正されない」から、最初に紹介した第85条5項の「内政・外交政策の原則を決定し、ウクライナの欧州連合(EU)および北大西洋条約機構(NATO)への正式加盟を目指す戦略的方針を実施する」を削除しようとしても、5月9日までつづくことになっている戒厳令下では、憲法改正ができないのだ。
もちろん、憲法改正の手続きもハードルが高い。議会構成員の3分の2以上の賛成票が必要になる。ところが4月に入って、元国会議員のヴィクトル・ウコロフが、憲法からNATOに関する記述を迅速かつ簡単に削除する計画を突然示した。彼によれば、政府は憲法裁判所の決定によって2019年の憲法改正を違憲と認める準備を進めているというのだ。これには前例がある。ヴィクトル・ヤヌコヴィッチ大統領は2010年、2004年の憲法改正の違憲性に関する憲法裁判所の判決によって大統領権限を拡大した「実績」がある。同じことをすればいいというわけだ。
ウコロフが説明したスキームは、もちろんウォロディミル・ゼレンスキー大統領に政治的な意志があれば、かなり実行可能である。憲法裁判所は比較的短期間に判断を下すことができる。戒厳令の最中であっても、2019年の改正の取り消しを「憲法の変更」ではなく、「以前の表現に戻す」と解釈して、それを行うことができるのだ。
さらに、非同盟の地位については、ヤヌコヴィッチ政権時代の2010年に「内政および外交政策の基本について」という法律によって明記された。ペトロ・ポロシェンコ政権下の2014年12月、議会はこの法律を改正し、非同盟国としての地位に関する記述を削除し、NATOとの協力関係の深化を追加した。こちらは、法律だから、改正すれば、非同盟化を宣言できる。
いずれにしても、ゼレンスキーが本当に戦争を停止し、ウクライナに和平をもたらしたいのであれば、できることはまだまだたくさんあるように思われる。大切なのは、ゼレンスキーの決意だ。しかし、残念ながら、ゼレンスキーの意志は依然として戦争継続に向かっているようにみえる。
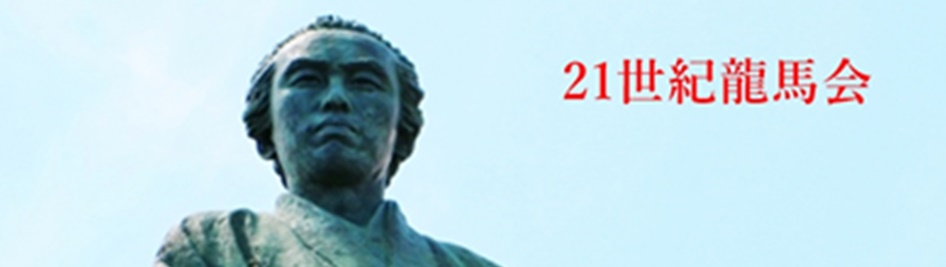







最近のコメント