講演会の準備に寄せて:柄谷行人と加藤周一の思い出
2月2日、杉並区梅里にある区民集会所で行う講演会に向けて、最後の準備をしている。といっても、毎日の仕事があるため、大した準備はできてないが、28日に朝日新聞の元役員に会って話したことで、頭の整理に役立った。
柄谷行人の思い出
彼は、朝日の学芸部時代、やがて奥さんになった人物と柄谷に会ったりした経験があるらしい。法政大学での柄谷の授業にも参加していた。
この私は、日本経済新聞社にいたときに柄谷とインタビューしたことが一度だけある。法政大学の教員控室でのことだ。インタビューの最後に、当時まだ存在していたソ連経済を大学院で学ぶつもりだという話をすると、「ソ連を理解するには軍事からみなければならない」と教えてくれたのが柄谷であった。その後、2003年に私が『ロシアの軍需産業』という岩波新書を書いたのも、このときの柄谷のアドバイスがあったからであった。
恐れられるということ
こんな思い出話から、やはり面と向かって取材する重要性を思い起こした次第である。近年、新聞記者からの取材要請がめっきり減った。きわめて残念なのは、2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞したにもかかわらず、取材申し込みがまったくないことである。
その話を彼にすると、朝日の学芸部でも、柄谷は恐れられており、美術担当だった彼が「上」からの命令で柄谷の話を聞くように取材に行かされたという経験を開陳してくれた。大学時代から「幽霊学生」として柄谷の授業に出ていたからというのがその理由だったという。
それほど、柄谷は恐れられていたという話を聞いて、意外な気がした。少なくとも、私が柄谷に会ったときには、とても親切に話してくれた。
しっかり準備しろ
私は、ロシアに取材旅行に出向く際、取材する人物の本や論文を徹底的に読み込んで、詳細な、あるいは、重箱の隅をつつくような質問をするように心がけていた。そうすると、多くの場合、取材先は親切に説明してくれるのが常であったと思う。そう、それが短時間の出会いで、効率的に話を聞く極意であると心得ている。
そんな私は、私の本を読んだこともないような輩が取材したいと求めたら、100%断る。取材を受ける場合、30冊を超す私の本をすべて読めとは言わないが、せめて最近書いた本を3冊、論考を10本くらい読んでおくのは必須だと思っている。要するに、問いがきちんとできない輩からは、真っ当な答えは導けないのだ。
こんなことを書いておくと、ますます、取材申し込みが減るかもしれない。そんな悩みをもつ人がいるのであれば、今回の講演を隅っこで聞いてみるといいかもしれない。
加藤周一の講演
私の68年間の人生において、講演会に出向いたのは一度だけだ。岩波文化講演会というのが昔あった。九段会館で、加藤周一ともう一人の講演があった。唯一、深く記憶に刻まれていることがある。それは、加藤が情報操作(マニピュレーション)について熱心に論じていたということだ。生まれてはじめて、manipulationなる単語に出合い、その大切さを知った。
私がdisinformationの研究について、少なくとも日本一であると自負しているのは、このときの経験による。
まあ、どうでもいい話だが、しばらく忙しいので、講演前に雑感を書いておくことにした。
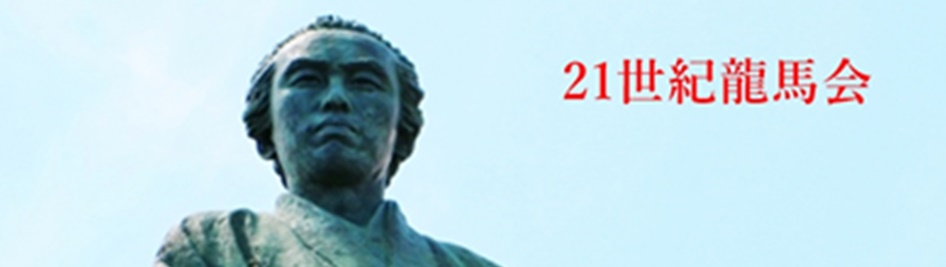




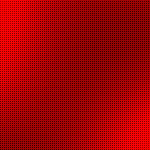



最近のコメント