講演「プーチン3.0」メモ
4月25日に刊行になる電子版の『プーチン3.0』(社会評論社)に呼応して、近く講演をすることになっています。その内容をいま、いろいろと考えている最中です。そこで、講演内容をよりたしかなものにするために、ここにメモ書きとして、ウクライナ戦争が主権国家の矛盾をわかりやすいかたちで教えてくれていることについて説明したいと思います。
主権国家の矛盾
今回のウクライナ戦争に際してわたしが強く思うのは、近代化が生み出した主権国家の矛盾です。『プーチン3.0』では、「近代制度は、主権国家同士による相互承認(国家主権の承認)を前提とするなかで、「河一つ」を国境とみなす視線(領土主権の承認)を明確化すると同時に、ネーション(国民)なるイメージを育んできた」と書いておきましたが、この制度に支えられている国際連合はまったく機能していません。
マリウポリのいまの状況にしても、絶望的な状況に置かれた「一般市民」なる人が多数いるのであれば、なぜ戦争を停止して彼らを救い出せないのでしょうか。その昔、沖縄において、投降したくてもさせてもらえずに死んでいった多数の「市民」がいたことを思い浮かべると、いま、マリウポリの製鉄所にも、投降したくてもさせてもらえない多くの住民がいるのではないかと危惧されます。
国連は、こうした人々を救出するためにだけでもいいからなぜ国連軍のようなものを急派できないのか。マリウポリの事態は、主権国家に翻弄されている「国民」の苦難そのものをよく示しているように思われます。
『プーチン3.0』にも書きましたが、ウクライナ政府が2月24日夜、18歳から60歳の男性の出国を禁止したことはまさに主権国家による横暴です。なぜ戦争から逃れてはならないのか。なぜ男性だけ禁止するのか。この禁止を正当化する法的根拠は何か。主権国家自体が国民の人権を踏みにじっているのです。そんなことが許されるのでしょうか。
1789年の人権宣言に含まれる両義性
主権国家の矛盾は、1789年のフランスの「人権宣言」を読むと、よくわかります。それを教えてくれたのは、大澤真幸著『〈世界史〉の哲学 近代篇 2 資本主義の父殺し』です。彼はつぎのように書いています。
「人権宣言の正式の名称は、La déclaration des droits de l’homme et du citoyen(人間と市民の権利の宣言)」である。とすると、ここで謳われているのは、人間hommeの権利なのか、それとも市民citoyen――フランス市民として資格づけられた者――の権利なのか。「人間」と「市民」。両者は異なる実体として名指しされているが、同時に、一緒になってひとつのまとまりをなすかのように見なされてもいる。人間と市民の関係ははっきりしない。」
「まず、第一条で全面に出ているのは、「人間」の方である。ここで人間(自然的な生)の権利における自由と平等が謳われる。第二条では、人間の権利が、政治的な「市民」の中に吸収される。すべての政治的結社の目的が、人間の権利の保存にあるとされるからだ。そして、第三条で、両者を総合する契機として「国民Nation」が登場する。主権の原理はもっぱら国民に存する、というわけだ。アガンベンの見立てでは、この国民という形式こそ、「むき出しの生」が近代の政治の中でとった姿である。実際、“nation”という語は、語源的には、(人間の)生まれnascereに由来している。ここでわれわれが確保しておきたいポイントは、主権国家を有するネーションと、「人間」の名のもとで要求される権利との本質的な結びつきである。」
ここでいう「主権」(sovereignty)という概念はきわめてわかりにくいものです。わたしはかつて拙著『官僚の世界史』のなかで主権についていろいろと考察したことがあります。それをここで繰り返すことはしませんが、少しだけわかりやすそうな記述を紹介しておきましょう。
「「主権」は「ある国家自身ないし別の国家を統治するための国家の権限」とでも訳すべき意味をもつ言葉である。フランスのジャン・ボダン(Jean Bodin)は『国家論6巻』(1576年)の冒頭において、「国家とは、多くの家族、およびそれらの家族に共通に属しているものの、一個の主権的権力(puissance souveraine)による統治である」と指摘した。彼は「国家」と「主権」という新しい秩序観念を発見したのである(Schmitt, 1941=1972, pp. 134-135)。ボダン自身は「自分が主権を発見した」と自慢したと言われているが、これも完全な間違いというわけではない。彼によれば、主権の存在は国家を他のあらゆる種類の人間的結合から区別するものである。家族はどんなに大きなものであろうと決して国家にならないが、国家はいかに小さくとも主権的であるかぎりはいつまでも国家である。この主権は永久性と絶対性という本質的な特徴をもっている。これは主権が国家を土台としている以上、国家が永続的であるのと同じように主権も永続的であり、また、主権は法によって拘束されず、絶対的であることを意味している。重要なことはアレクサンダー・ダントレーヴが指摘するように、永久性も絶対性も、権力が最高あるいは究極的でなければならないこと、つまり、それより上位にあるなんらかの権力から派生したものではあってはならないという条件を満たしていなければならない点である(d’Entrèves, 1967=2002, p. 123)。こうした条件が徐々に満たされ、主権概念が見出されたのだが、それはstateを国家とみなすようになる時期に対応している。主権がなくてはstateという国家は存在しなかったのである。ゆえにジョセフ・ストライヤーは「われわれが主権と呼ぶ権力の集中は国家の存在にとって絶対必要であった」と的確に指摘している(Strayer, 1970, p. 108)。こうした大きな変革を準備したのが中世であった。ローマ人は、法が立法者の意志に根差しており、慣習に対する成文法の優位を主張していたのに、中世になると、立法行為はある共同体において暗黙裡に受けいれられている規則の編纂、つまり慣習の認知にすぎなくなってしまう。法は「見出されるもの」であって、「造られるもの」ではないという見方が支配的になることで法の「非人格化」が進む。しかも支配者は単に法の執行官にすぎないとして、支配者の行使する権力は制限される。だがローマ法の研究を通じて、共同体のどこかに国民か君主か、それとも君主と国民が一体になったものか、いずれにしても国家の精髄たる権力があるとみなす考え方の存在が知られるようになる。法はこの最高の権力、至高の意志を背景に、共同体の変化に応じて行使される道具として統制されるのであれば、有効な諸規則とみなすことができるというのだ。この至高の意志はそれが最高であるがゆえに、自己以外の何物にも責任を負わないという理由によって法を超越する意志であり、それはそれより上位にあるなんらかの権力から派生したものではあってはならないという条件を満たすことで永久性と絶対性という主権の特徴を担保することになる。ここに主権が成立する。主権国家の生成をめぐっては、山影進(編著)(2012)が参考になる。同書にあるように、15世紀のイタリアで主権国家体系が準備されたと考えるべきであろう。」
主権国家は、人間の権利たる人権を保護することを義務として課されています。しかし、その対象は人間全般ではなく、ある領域、すなわち特定の領土内の市民に限定されてしまっています。その限定された市民が国民(ネーション)として人権保障義務を果たすための仕組こそ、主権国家ということになるわけです。おそらく最大の問題は、このネーションという概念がゲゼルシャフトをめざしながらゲマインシャフトに回帰したところにしか生じないというところにあります。それを利用して、つまり、ナショナリズムを煽動してゲマインシャフトという古い時代への逆行が可能になるという点が大問題を引き起こします。
主権国家への批判
わたしは主権国家を『官僚の世界史』のなかで、つぎのように批判しておきました。
「主権国家に自由意志があるかのように振る舞わせるのは危険であるし、そもそも間違っている。第一に、社会契約論は誤りである。「私」にだけ自由意志を認め、その結果として社会契約の主体として「私」だけを想定するのはおかしい。実際に行動するのは「自分」であるのは事実だが、その行動は意識をもった「私」だけの自由意志に基づくのでは決してなく、あくまで無意識や身体を含めた「自分」なのだ。社会契約を結ぶのは「私」である。だが、「私」が行使できるのは無意識から湧き上がってくる欲求などへの拒否権でしかない。ときどき意識される「私」が主体として振る舞ったことと、無意識の「自分」が感じていることが一致するわけではない。その証拠に「私」の自由意志は頻繁に変化する。ときどき顔を出すだけの意識である「私」はいつも「自分」全体のことを意識しているわけでもないから、無意識や身体といった「自分」の変化に応じて頻繁に「私」自身も変わらざるをえない。ある時点で社会契約の主体として振る舞ったとしても、主体はすぐに変化してしまうから、その契約自体に有効性を見出すことはできない。しかもホッブズの社会契約は人々のために神と話ができるというモーセと盟約を結んだ人々がモーセによって語られるすべてを神の言葉として受けいれるのと同じ盟約を前提にしているのであって、そんな盟約を結んだと実感できる人はいないはずだ。
第二に、主権国家はまさに「想像の共同体」にすぎず、国家が主権者として自由意志をもっているかのように振る舞うことを認めるのは危険極まりない。国家という主権者がもつ権力を行使するのは結局、人間であって、その人間は主権国家の代理人にすぎない。その人物本来の自由意志を行使するところまでは認められていない。だが、例外状態において、主権国家の代理人たる人物はその自由意志によって決断をくだすことが認められている。人間を抹殺することもできる。ここに、国家の主権化の虚構性が隠されている。主権国家は人間ではないから、主権国家に国民の自由意志を集約的に反映することなど、そもそもできないである。
第三に、技術進歩によって人間は機械に伴う事故や災害に出くわす「リスク」にさらされるようになる。このとき、事故や災害は主体の責任ある行為によって回避されるわけではない。むしろ、人間は生まれながらにそのような危険を負った存在とみなさなければならない。こうなると、責任を問われるのは自らの自由意志に基づく行為だけであるという古典的な法思想の前提が揺らぐことになる(大竹, 2015)。事故の帰責可能な人格の罪と責任を問うよりも、産業技術社会に否応なく組み込まれた構成要素として、人間がアプリオリに負っている責任を前提に事故による損害負担の配分が検討されなければならなくなる。そこに、リスクに応じた保険による事故防止が可能となる。保険制度を支えるのはリスク計算であり、統計学上の確率が重要になる。このとき、主権国家を支える法秩序も統計的現象として把握されるようになる。個人の主体化と国家の主権化は技術の発展によってその結びつきを弱めているのだ。そればかりではない。科学が核分裂や遺伝子操作まで至った結果、自然を観察するところから実験し自然に働きかける過程を経て自然のなかへと人間が行為するようになったことで、いま現在、近代化後の国家や個人を位置づける枠組み自体が揺らいでいる。
主体化および主権化に伴う誤謬を糺さなければ、その結果として生じる腐敗問題にかかわる「捻れ」ないし「歪み」を解消することはできない。そのためには、意識をもつ「私」だけに「自分」を代表させてはならない。同時に、主権国家に国民を代表させてはならない。それは、主体を疑うことを意味し、主権国家を解体させることにつながらなければならないことを意味している。」
問題は主権国家をどう改めるか
主権国家への批判はどう主権国家に代わる「新しいグルーバル・ガバナンス」を構築するかという問題を惹起します。残念ながら、この問いへの答えはそう簡単には見つかりません。『プーチン3.0』でもそう書いておきました。ただ、より多くの人々が主権国家の「嘘」に気づき、同時に、主権国家と結託したマスメディアの「嘘」によく気づいて、そうした情報操作に惑わされずに自分の人生をしっかりと生き抜くことが最低限必要なことだと思われます。そのためには、一人ひとりが「品格」、「志」、「矜持」のようなものを大切にしてほしいと願っています。さらに、それらを鍛えるためには、とにもかくにも勉強することが求められていると強調しておきたいと考えます。


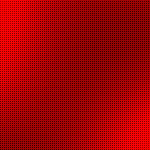





最近のコメント