「生き甲斐」と「死に甲斐」の「はざま」:バランスを崩していないか
いま、日本人のなかで「生き甲斐」について考える人はいても、「死に甲斐」について問う人は少ないのではないか。国中が戦争に巻き込まれていた時代には、死が身近に感じられたから、戦死することに価値や意味を見出すために「死に甲斐」について思考することに迫られた人が多かったに違いない。「犬死に」ではなく、意味のあるかたちでの死を望んだのは死者だけでなく、生き残った親族も同じだろう。
図式的に言えば、近代国家としての大日本帝国は国民に「死に甲斐」を強いたが、敗戦後の日本は「生き甲斐」を喧伝するようになる。戦争を通じて国家に騙されてきたにもかかわらず、多くの国民は「生き甲斐」を見出すなかで戦後復興を成し遂げる。その結果、国家としての日本は復活し、いまでは「死に甲斐」という発想自体が消え去ってしまったかにみえる。だが、国家が生き残るためには、国民に「生き甲斐」を称揚するだけではすまない。国家には、再び「死に甲斐」を喧伝することで国家を守ろうとする勢力がいるからだ。
「死に甲斐」への傾斜の復活
戦争が国家と国家による武力衝突であるとみなすと、その戦争に兵士を駆り立てるには、たとえ戦死してもそれが意味のあることだと兵士に信じさせる必要がある。そのため、国家は教育を通じて、「鬼畜米英」といったスローガンで洗脳し、敵は鬼だから殺しても罪にならないと説得する。神国ニッポンを守るために死ぬのであれば、そのこと自体に意味があると教え込むわけだ。そして、兵士に「死に甲斐」を自覚させて、国家に奉仕させるのである。
ある意味で、戦前の日本政府はこうした「死に甲斐」をより多くの国民に植えつけることに成功した。だが、戦後70年以上経ったいま、「国のために死ぬ」ことに「死に甲斐」を見出せる人がどれだけいることか。家族のために死を賭して戦う人はたくさんいるだろうが、自分の選挙区の有権者に飲み食いさせても、公文書を改竄しても、罪に問われない政治家や官僚が牛耳っている日本国のために死のうとする者は皆無ではないか。
ゆえに、戦争を具体的に想定する人のなかには、愛国心の育成の必要性を声高に叫ぶ者もいる。そのための第一歩として、オリンピック招致を国威発揚に利用しようと目論む人も少なからずいるだろう。
オリンピックの怖さ
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックのために、東京オリンピック・パラリンピックは当然、中止になると思っていた。だが、何が何でも開催しようとする人々がいる。「アスリート」と呼ばれるスポーツをビジネス化している人の「生き甲斐」を大切にしつつ、彼らの「パフォーマンス」を観察する人々に、「日本国民」としての意識を呼びさまし、可能であれば「国のために死ぬ」といった「死に甲斐」の側に観客を傾けようとしているのではないか。
心配なのは、オリンピックを政治利用して、「死に甲斐」の復権をねらう勢力が厳然と存在することだ。問題の所在も意識しないまま、「がんばれ、ニッポン」と叫ぶ若者が多いだろうが、それでは歴史の教訓に学んだことにはならない。大切なのは、「死に甲斐」に目をつむることではない。「死に甲斐」と「生き甲斐」という二つの価値観に揺れ動いた日本国民の歴史を教え、この二つの価値観の「はざま」でどうすべきなのかをできるだけ多くの国民に意識化させることなのである。
戦争体験を語ろう
筆者は人生で三度、「戦争保険」に入ったことがある。この戦争保険は、普通期間保険では保険金の支払いの対象とならない地域、すなわち、戦争、内乱、海賊、テロなどの高い戦争危険が予想される地域での損害を補償する保険を意味している。筆者は朝日新聞のモスクワ特派員時代、チェチェンに二度、その隣のダゲスタン共和国に一度、出張した。この三度の訪問時、それらの地域は戦争状態に近い状況に置かれていたので、会社は筆者を戦争保険に加入させ、出張させたのである。
拙著『核なき世界論』のなかで、つぎのように書いたことがある。
「たとえば、筆者は朝日新聞社のモスクワ特派員時代、チェチェンを二度取材に訪れたことがある。一度はまだ停戦合意ができる前の1996年のことだった。チェチェンの都グロズヌイに出向く1週間ほど前に、先遣隊として送り出したロシア人がグロズヌイで雇った白タクの運転手は、筆者らが到着する三日前に、市庁舎近くに停車中、爆弾テロで死亡した。筆者が現地で確認すると、地面に深さ3メートル、直径10mほどの穴がぽっかりと開いたままだった。グロズヌイ近くの油田に取材に行くときには、両脇を機関銃で武装したボディガードが付き添い、遠くには砲弾が響き渡る状況であった。夜に民家に宿泊すると、銃声がときどき聞こえた。」
こんな疑似戦争体験のなかで出会ったチェチェンの人々の多くは、おそらく「生き甲斐」を見出すのが難しかったに違いない。生き残った者として、死者に「死に甲斐」を見出すにしても、独立のための死にどこまで価値を見出しえたのか、筆者にはわからない。
強く印象に残ったのは、老婆にしか見えない女性が「他人の親切が身に染みている」と語ったことだ。家族を失って途方にくれながらも、支えてくれる他人がいるから何とか生きていけるという現実が彼女の「生」を保たせていたのだ。「戦争が人を優しくする」という逆説がそこにはあったような気がする。そこには、自分だけで「生」や「死」を求めるという発想がもはや存在しない。
想像力の重要性
こんな話をすると、ジョン・レノンとオノ・ヨーコの共作とされるようになっている「イマジン」を想い出さずにはいられない。第二番の部分が心に染みる。
Imagine there’s no countries,
It isn’t hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too.
Imagine all the people
Living life in peace. Yu Huh.
大切なことは、国がなかったり、宗教がなかったりする世界を積極的に想像させる教育だと思う。それによって、想像が現実と異なるのはなぜかを考えさせるのである。殺したり死んだりするためのものがなければ、「死に甲斐」を考える必要はないのかもしれない。それに対して、生きることに理由はあるのか。だが、「生」に理由を見出そうとするのは、「目的論」につながり、目的と手段という安易な指向につながりかねない。「生き甲斐」という目的にだけ力点を置くのはまずい。
要するに、「死」や「生」に目的を見出し、そこに価値を見出そうとする「死に甲斐」とか「生き甲斐」とかいうのも自体に問題があるのではないか。「生」や「死」を目的にせずに、バランスよく生きて死ぬことにこそ意味を見出せせるのではないか。
だが、残念ながら、日本の教育は目的論に立脚している。あるいは、教育の基本理念のところで、深く考えていないのだ。その結果、安倍晋三前首相のような国家主義者が偉そうにしていられるのではないか。
目的論批判
まず、目的論は物質が自ら運動するとみる自然哲学を否定する見方を端緒としているという柄谷行人の指摘(『哲学の起源』)から紹介したい。量子力学を知っている現代人にとっては、この見方は決しておかしな主張とは思えない。クォンタム(量子)は粒子(質量)であると同時に波動(運動)であり、静止して見える物の内部では量子が幾重にも飛び交っているのである。ゆえに、物質は自ら運動していると言えるわけだが、そんな量子学を知らなかった古代人はついつい、物質は何か理由があるから動くと考えるようになる。それが目的論につながっているというのだ。
物質の自己運動を否定すると、運動を引き起こす淵源としてなにかを想定せざるをえなくなる。たとえばプラトンは神を想定した。アリストテレスはプラトンと異なり、物質の自己運動性を認めたが、その運動(生成)は物質に内在する原因によって生じると考えた。その原因は、質量因と始動因、目的因と外相因であるとしたうえで、運動が目的(終り)をもつと考えた。それが目的因のことである。ただし、この見方は事物が生成したのちに初めて見出されるものであり、事後的観点から説明するという姿勢を意味している。事後の勝者が自らに有利な歴史を捏造できることになる。
国家による歴史教育は「政府の失敗」
国家は歴史の勝者として国民にその歴史観を押しつける。その結果、個人より国家の利益を優先させる見方を教育で植えつけることで、全体主義への道に引きずり込むこともできる。これは政府の永続性に資するようにみえる努力だが、その実、政府を構成する国民を盲目化させるだけであり、結局、戦争による政府の死を早めるだけかもしれない。だからこそ、こうした国家による歴史教育は「政府の失敗」と呼べる、と筆者は考えている。
ヨーロッパの場合、義務教育は宗教教育を通じて行われた義務教育を国家が教会や領主から簒奪して担うものであった。もともとは、ギリシャ時代のスパルタでの教育は一種の義務教育であったと言えるし、802年にはカール大帝が貴族の子弟に限定されない義務教育令を発した。こうした事例は認められるものの、歴史のなかで忘却される。広く民衆に教育を施すという考え方が広範囲に政策に採用されるようになったのは、民衆が聖書を読めるようにするという宗教改革の精神を自領地内で実践しようとする為政者が現れたためである。いわゆるゴータ公国を治めていた、ルター派のエルンスト一世は1642年、ゴータ教育令を発し、12歳までの義務教育制度を整備した。文字を読めるようになることに力を入れ、一人一人が聖書と向き合うことを可能にした。1763年に、プロイセンのフリードリヒ二世は「一般地方学時通則」を発令し、王に対する忠誠心と愛国心を養うとともにキリスト教道徳を教え込むための初等教育制度をスタートさせた。1872年になると「学校監督法」ができ、公教育において宗教が分離されることになった。
カトリック教会が支配的であったフランスでは、教会の力が強く、国家による宗教への干渉が警戒された。この結果、フランスでの義務教育導入は1882年のことだ。同時に、義務教育における非宗教性・政教分離の原則(「ライシテ」, laïcité)が導入された。国家が宗教に直接、関与しないことを条件に義務教育化がようやく認められるようになったのだ。
国家による歴史教育
国家=政府が義務教育を通じて教え込もうとしたなかには、「歴史」がある。もともと歴史は可死の人間を不死にとどめるという面をもっている。その意味では、永続的な統治をもくろむ国家=政府がその支配の正統性を国民に教え込むために歴史を活用するのは合理的と言えるかもしれない。
「国民主権」をもとに民主主義を奨励し、民主主義を金科玉条のように祭り上げて主権国家の正統性を確保するために、民主主義を過度に礼賛する視角から歴史を語り、それに立脚した国家=政府の正統性を教え込み、国家=政府の継続につなげるという方法が世界中に蔓延している。そのために政府が支払っている資金は莫大だ。それだけのコストを払って、政府を守ろうとしてきたともみなせる。まさに、全体主義に向けて、国家が積極的に活動していることになる。だからこそ、イサベル・パターソンは「税金によって支援された義務教育制度は全体主義国家の完全なモデルである」と記したのである(Paterson, 1943, p. 258)。
こうして、世界中の国々で、国家にとって都合のいい歴史が無理やり教え込まれている。いまのところ、「死に甲斐」教育は日本では行われていないようにみえる。だが、いつ「死に甲斐」を説くようになるかは国家次第だ。大切なのは各人がこの問題に向き合うことであり、国家や家族のような自分以外の外部の他者からの圧力に屈しないことだ。
「生き甲斐」と「死に甲斐」の「はざま」で、バランスを考えることの重要性をつくづくと想う2020年の暮れである。

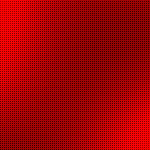






最近のコメント