『ドクトル・ジヴァゴ』を読みましたか:いまの時代と似ていませんか
2020年4月、ラーラ・プレスコット著『あの本は読まれているか』が刊行されました。ここでいう「あの本」とは、ボリス・パステルナークの『ドクトル・ジヴァゴ』です。この本の出版をめぐるサスペンスをフィクションとして書いたのがこの本です。ごく最近、この本を読み終えました。この本自体は別にお勧めしようとは思いませんが、ノーベル文学賞に輝いた『ドクトル・ジヴァゴ』は必読の書です。
わたしは、拙著『ロシア革命100年の教訓』のなかで、この『ドクトル・ジヴァゴ』について紹介したことがあります。恋愛小説として十分読めるこの小説がなぜソ連で発禁になったのかについて論じたのでした。ここでは、そこでの分析を紹介しながら、いまの時代との類似点について考えてみたいと思います。
ロシア革命の本質を探るために
まず、『ロシア革命100年の教訓』での記述を紹介しましょう。縦書きの書式を単に横に直したものを示します。
****************************************
ロシア革命の本質に近づくためには、ロシア革命の本質を隠そうとしたソ連政府のやり口に迫ればいい。その際、歴史として紡ぎ出される事実を知るという方法もあるが、ここではソ連が発行禁止にした小説を取り上げて、いったい、なにを隠そうとしたのかを考えたい。
なぜ発禁された藝術作品に目を向けるのかというと、「感情は、「伝達可能」であるかぎりにおいて、公的であるかぎりにおいて感情として受け止めることが可能」となるからである(清水, 2014, p. 242)。発禁処分となった藝術作品は伝達可能性を奪われて、人々の感情を刺激する道を奪ってしまう。それほどまでに公的権力が怖れる感情とはなにか。そこに、ロシア革命の本質をみることができるのではないか。
フィクションである小説を取り上げてみても、それはトロツキーの有名な言葉、「歴史の屑の山」のひとかけらにリアリティをもたせただけのものかもしれない。だが、そこにこそ勝者の歴史ではない、本当の過去の姿が垣間見えるのではないか。たとえフィクションであっても、そこにはその時代を生きた人々の苦悩や罰の悩みがはっきりと感じられるはずだ。だからこそ、ソ連政府が発禁にした藝術作品を読み解く価値があるのである。
ここで取り上げるのは、ボリス・パステルナーク著『ドクトル・ジヴァゴ』である。一九七〇年にノーベル文学賞を受賞したアレクサンドル・ソルジェニーツィンは、ソ連の暗部を描いた『イワン・デニーソヴィチの一日』や『収容所群島』で知られており、後者の公表がソ連国内ではできなかったのは頷ける。ソ連の恥部を描いた作品はソ連国内の人々に読まれてはならなかった。彼らの感情を揺さぶるからである。
ここで取り上げたいのは、叙情詩などが評価されて一九五八年のノーベル文学賞の受賞決定者となりながら、ソ連政府の圧力で辞退に追い込まれたパステルナークのほうである。ソ連当局は彼の書いた『ドクトル・ジヴァゴ』を発禁処分とし、同書は結局、イタリアで刊行されるに至る。この作品はロシア革命前後を生きた人々の苦悩を描いた小説であるため、ソ連当局としてはロシア革命後の暗部を描いたとして発禁としたのであろう。しかし、一読したかぎりでは、恋愛小説と言えなくもない。ロシア革命そのものに直接かかわるような記述があるわけではないのだ。
「マルクス主義ほど自閉的で事実より程遠い思潮を知りません」
だからこそ、この小説の内部に立ち入って検討することで、ソ連当局がなにを怖れていたかを明らかにしてみたい。それがロシア革命の本質をいぶりだす一助になるのではないかと思われる。ここでは、工藤正廣訳『ドクトル・ジヴァゴ』(Pasternak, 1955=2013)をもとに考察してみたい。
まず、医者である主人公、ドクトル・ジヴァゴのつぎに発言は、おそらくソ連当局を怒らせたであろう。ただし、その内容は本書そのものの主張とぴったりと一致している。
「マルクス主義と科学? 未知らない人間とこの議論をするのは少なくとも軽率です。しかし、まあいいでしょう。科学はもっと均整のとれたものです。マルクス主義と客観性ですか? わたしは、マルクス主義ほど自閉的で事実より程遠い思潮を知りません。誰もが自分の経験を点検することに憂慮しますが、権力の人々は自分の無謬性の神話のために全力を傾けて真実からそっぽを向いています。政治はわたしにも何も語ってくれません。わたしは真理に無関心な人々は嫌いです」(Pasternak, 1955=2013, pp. 345-346)。
この引用は明らかにマルクス主義への批判であり、同主義に基づく権力者への非難を含んでいる。とくに、「権力の人々は自分の無謬性の神話のために全力を傾けて真実からそっぽを向いています」という表現は厳しい批判であり、的を射ているだけに看過できない部分であろう。
さらに、ドクトルは別のところで、つぎのように吐露する。
「先ず第一に、十月革命以来持ちあがったような、全体の完全化という理念はわたしを奮い立たせないのです。第二に、それはすべてまだ実現からほど遠く、ところがこのことについてのまだ相変わらず同じ見解のために、かくも厖大な血が流されたのですよ、とても目的が手段を正当化するとは言われないでしょう。第三に、これが肝心なことですが、生活の改造、と聞いただけで、わたしは自制心を失い、絶望的な気持ちになるのです」(Pasternak, 1955=2013, p. 446)。
このように、主人公であるドクトル・ジヴァゴが反マルクス主義者であることは自明だ。それがソ連当局の苛立ちにつながっている。
こんなジヴァゴだが、一九一七年夏には、まだ社会主義に希望をもっていた。彼はヒロインであるラーラ、すなわちラリーサ・フョードロヴナにつぎのように語っている。
「その半分は戦争がやって、残りの半分は革命がなしとげたのです。戦争は生の人工的な中断だったのです、あたかもしばらくのあいだ寿命が延ばせるとでもいうように(まったくばかげたことだ!)。革命は、余りにも長いあいだ抑えていたため息のように、意志に反してほとばしり出たのです。一人一人が生き返り、生まれ変わり、みんなが変化し、変革があったのです。こう言ってもいいでしょう。一人一人が二つの革命をこうむった。一つは自分の個人的な革命、もう一つはみんなの革命です。ぼくは思うのですが、社会主義――それは、こうした自分たちの個々の革命が小川になって注ぐべき海、生の海、自立の海なのです。生の海、とぼくは言いましたが、そう、その生というのは、天才的な生の光景に見ることができるような生、創造的に豊かにされた生なのです。しかしいま人々はそれを書物ではなく自分の身で、抽象的ではなく実践で体験する決心をしたのです」(Pasternak, 1955=2013, pp. 193-194)。
「マルクス主義は世紀の強大な勢力になった」
他方で、パステルナークは小説のなかで、ヒロイン、ラーラの夫(アンチーポフ・パーヴェル)でありながら、赤軍の将軍となったストレーリニコフにつぎのように語らせている。
「街、夜の街、世紀の夜の街、駿馬や鹿毛馬たちはどこにでもあった。時代を一つにしたのは何だったでしょうか。何が十九世紀を一つの歴史的仕切りにしたのでしょうか? 社会主義思想の出現なのです。革命が起き、献身的な若者たちがバリケードに上った。社会政治評論家たちは、金銭の動物的な恥知らずをいかにして抑え、そして貧民の人間的価値を高め、守り抜くか、頭を悩ませた。マルクス主義者が現われた。マルクス主義は、悪の根が何にあるか、どこにその治療の方法があるか、喝破した。マルクス主義は世紀の強大な勢力になった。これはみな世紀のトヴェルスキエ・ヤムスキーエ御者街だったのです。不潔も、聖なるものの輝きも、放蕩も、労働者地区も、政治ビラ、そしてバリケードも」(Pasternak, 1955=2013, p. 606)。
饒舌なストレーリニコフはつぎのようにも語る。
「ところで、お分かりですか、この十九世紀全体とそのすべてのパリの革命家たち、ゲルツェンから始まるロシアの亡命者の幾世代、不発に終わりまた成就されたすべての考え抜かれたツァーリ暗殺、世界のすべての労働運動、議会やヨーロッパの諸大学におけるすべてのマルクス主義、思想体系のすべての新しさ、諸々(もろもろ)の結論の革新とスピード、憐みの名において仕上げられた呵責なき方法、こうしたすべてを、自分の中に吸収して総合的に表現したのが他ならぬレーニンであり、それはすべてそれまでなされたものに対する復讐の権化となって旧世界に襲いかかるためだったのです。
彼のそばには、巨大なロシア像が打ち消しがたいくらいに立ち上がり、全世界の眼前に突如としてその像が人類のすべての不幸と災難を救済する蝋燭となって燃えあがったのです」(Pasternak, 1955=2013, p. 607)。
もちろん、こうしたソ連当局の喜びそうな記述は赤軍の将軍によって発せられたのであり、小説全体にリアリティをもたせるための手法にすぎない。
欺瞞的なネップ期
おそらく「彼(ジヴァゴ)がモスクワに着いたのは、ソヴィエト体制の時期でもっとも二重的で欺瞞的なネップ期[一九二一年、ロシア共産党第一〇回大会で採択された新経済政策]の初めのことだった」(Pasternak, 1955=2013, p. 612)という記述もソ連当局を怒らせたに違いない。筆者は長くネップ期について、一時的な市場容認策と理解してきたが、その実情を必ずしも知らなかった。だが、つぎの記述を読んで、そのひどさに驚愕した。
「個人の商いが解禁され、厳しい枠内ではあったが自由な商売が許されていた。市場で古物に限って取引が行なわれていた。こうした取引がなされていた非常に小さい規模がかえって投機的な闇商売を助長させ、それが不法行為をもたらしていた。闇屋たちの微々たる活動は市中の荒廃にたいして何ら新しいものも、実質的なものももたらさなかった。無益な転売がくりかえされて十倍もの利益が手に入っていた」(Pasternak, 1955=2013, p. 622)。
実際にこの時代を生きたパステルナークの指摘は実に重い。筆者としては、ロシアの経済政策を大学院で専攻したとはいえ、その現実を知る努力を怠っていたことに忸怩たる思いを禁じ得ない。加えてネップ時代にあっても、ボリシェヴィキ政権は大企業、外国貿易、銀行、輸送などを手元に残していたことを忘れてはならない(Radzinsky, 1996=1996, 上, p. 275)。蛇足ながら、この第十回党大会で、党内の一切の分派活動や会派を禁止する決議が採択されたことを注意喚起しておきたい。この決議は非民主主義そのものであったから、秘密とされたのだが、のちにスターリンによって粛清の理由に使われることになる。なにしろ、スターリンは一九二二年に共産党書記長という新設ポストに推挙され、このポストを利用して地歩を固めたのだ。党大会の実務的な運営を担うための「技術的ポスト」にすぎなかった書記長ポストを絶大な権力にまで強大化させたのである。
「コミッサール」の正体
もう一カ所、筆者にとって重大な関心事となったのはつぎの部分である。
「いたるところ、所有家屋、役所、職場、住人のサーヴィス機関で、幹部の改選が行なわれていた。そのメンバーは入れ替わった。すべての機関に無制限の権限をもったコミッサールが任命され始めた。彼らは威嚇の諸手段とナガン銃で武装し、めったに髭を剃るひまもない不眠不休の、黒いコートを着た鉄の意志の持ち主だった」(Pasternak, 1955=2013, p. 258)。
これは十月革命後、「企業も団体もつぎつぎにボリシェヴィキ化していった」過程で実際に起こったことを示している。ここでのコミッサール(委員)は治安維持のための「民警長」のような人物であったとみられる。
「人民コミッサール」と言えば、「大臣」のような高位の責任者で、「人民コミッサールソヴィエト」と言えば、十月革命で誕生した「内閣」のような存在にあたる。フランス革命かぶれのトロツキーが大臣をコミッサール(人民委員と訳されることが多い)と呼ぶことを提案し、レーニンがこれを気に入ったのだという(Radzinsky, 1996=1996, 上, p. 188)。なお、初の人民コミッサールソヴィエトの議長はレーニンであり、スターリンは当時、民族問題担当の人民コミッサールになる。レーニンはトロツキーを議長に推挙したのだが、トロツキーが辞退したため、自ら議長に就いたのである。トロツキーは外交問題担当や軍のコミッサールになる。
ほかにも、コミッサールと言えば、ありとあらゆる旧組織に送り込まれて、既存の組織内秩序を共産党のもとに一元的に再構築しようとした人物という意味もある。ロシア共産党(ロシアで社会民主労働党を主導していたレーニンが選んだのが「社会」や「労働」と看板を異にする「共産」であった)がそれまでのロシア帝国軍をソ連の国防軍に再編する過程で、軍を監視するために送り込んだ「政治将校」や「政治委員」を意味することが多い。これは軍を担当していたトロツキーが発明した制度である。
人民コミッサールと「チェーカー」の関係
実は、この人民コミッサールはロシア革命後の権力保持のための暴力装置であった「チェーカー」と呼ばれた秘密警察組織に深く関係している。というのは、一九一七年十二月、人民コミッサールソヴィエトが反ボリシェヴィキのストライキやサボタージュに対抗するために「反革命・サボタージュとの闘争に関する人民コミッサールソヴィエト付属全ロシア非常委員会」(その後何度も名称変更するのだが、「チェーカー」と総称された。これは一種の秘密組織であり、日本で言えば、特別高等警察[特高]のようなものであった)が創設されたのである。このきっかけとなったのは、十一月十五日に武装解除に応じた反革命派の大半が数週間のうちに反革命派に復帰してしまったという事件であった(薬師院, 2011, p. 209)。
注意喚起すべきことは、「国家権力と党機構がそのなかで合体するように見え、そしてまさにそれが故に全体主義支配機構の権力中枢として正体をあらわす唯一の機関は、秘密警察である」と、アーレントが指摘している点だ(Arendt, 1951=2014, p. 194)。軍は暴力的な潜在力はもつが、秘密警察は内外の問題についてともに権力中枢に利用される(軍は主に対外的に活動するだけだ)。心に留めるべきことは、自国のなか、ないし外国領土を征服した場合、軍は一貫して警察機構に籍をおく官僚の命令権下におかれ、国防軍に所属する者は警察が配置した精鋭組織の風下に立たされることである(同, p. 195)。さらに、全体主義的支配形態が出現するまでは、秘密警察は他のすべての政府機関に対する優位を与えられる、つまり、「客観的な敵」がだれであるかを決定する権利を留保しているが、全体主義が確立すると、最高指導者にすべての権利が奪われ、犯罪を摘発する任務さえ失う(同, p. 206)。いかなる犯罪が行なわれ、だれが犯人であるかを決めるのは最高指導者ということになる。
ここで登場する「人民コミッサールソヴィエト」は一九一七年十月二十七日、第二回全ロソヴィエト大会および全ロ中央執行委員会の決定によって設立されたものであり、国家の個別分野の管理を担う機関としてロシアだけでなく、他の共和国でも同じような人民コミッサールソヴィエトが創設された。
こうした結果を受けて、『ドクトル・ジヴァゴ』では、前述したように「すべての機関に無制限の権限をもったコミッサールが任命され始めた。彼らは威嚇の諸手段とナガン銃で武装し」という状況が現われるようになったわけである。だからこそ、その付属機関として「チェーカー」が生まれ、その後、暴力背景に共産党の支配を確固たるものにするのだ。なにしろ、人民コミッサールソヴィエトは「内閣」のような機関にすぎず、その実権は党が握ることになったのだ。
とくに、穀物の徴収をめぐっては「チェーカー」が厳しい取り締まりを行っていたことについては、『ドクトル・ジヴァゴ』では、「ふたたび市中ではガイダの叛乱前[一九一八年五月末、ロシア領内で捕虜になったチェコスロヴァキア軍団の武装解除に際して叛乱、そのリーダーがラドラ・ガイダ大尉。一九一九年一月から七月までコルチャークのシベリア軍を指揮]のように不満の声があがり、この不満のあらわれに対してまたしてもチェーカーの取り締まりが猛威を振るっている」(Pasternak, 1955=2013, p. 521)と記している。
このチェーカーこそ、KGB(ソ連国家保安委員会)として有名になる機関の前身であり、ソ連という国家の安全保障を考えるうえできわめて重要な組織なのである。「革命の懲罰の剣」の役割を担って誕生した機関だが、やがてスターリンという独裁者の権力基盤となる。筆者は、いま現在もKGBの後継機関であるFSB(連邦保安局)の職員が官庁、国営企業、大規模企業・銀行に出向やOBとして職を得て「内部化」している現実に驚きを隠せないでいる。この特徴はロシア独自のものであり、現在のロシアに深刻な影響を与えているからだ。この問題については、拙著『ネオKGB帝国』や『プーチン露大統領とその仲間たち』に詳しいが、こうした事態の淵源には安全保障を最優先とすることでボルシェヴォキ政権を守ろうとした頭目らの利害があるとにらんでいる。この問題は第2章で詳しく考察する。
このようにみてくると、『ドクトル・ジヴァゴ』がソ連で発禁となった理由が頷けるかもしれない。実際に起きた事実を歴史としてながめるよりも、ずっとリアリティのある「現実」として感じられるのではないか。だからこそ、人々の感情に訴えるだけの力をもつ。ゆえに、この本がソ連で刊行されていれば、暴力に基づくソ連共産党支配への人々の嫌悪感を呼び起こすことにつながったかもしれないのである。ここに、ロシア革命の本質の一端を垣間見ることができるのではないか。
****************************************
『ドクトル・ジヴァゴ』に描かれた時代といまは類似点があるように思えます。いわば、「全体主義」の足音が迫っているように思うのです。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックのなかで、各国政府がいろいろと国民に干渉し、とんでもないことになっています。日本で言えば、わけのわからない「専門家」と呼ばれる人々が食事のときにさえマスクをしろとバカげた話をしています。国民はガキではないのですから、そんなことよりもPCR検査の拡充にもっともっと本腰を入れろと言いたくなります。
新自由主義と国家重視
今週、ロシア語雑誌「エクスペルト」に社会学者のスティーヴ・フラーのインタビュー記事が掲載されています。なかなか読み応えのあるいい記事です。そのなかで、フラーはつぎのように指摘しています。
「つまり、新自由主義の下では、国家の主な任務は、人々が自由に能力を開発できるようにすることである。しかし、この仕事ができるのは国家だけであることが強調されている。この考え方は、20世紀初頭のアメリカの進歩主義者にも、イギリスのファシズムにも近いものがあった。そして、ソ連の台頭以前には、これらの運動はいずれも社会主義を名乗っていた。しかし、ロシア革命後、彼らは次第にこのような新自由主義の感覚に向かって漂流していった。
しかし、ここで重要なのは、新自由主義者たちは決して強大な国家という考えを捨てたわけではないということである。いずれにしても、ある国家が他の国家を自由にするために何ができるかを理解することで、彼らはより勇敢になったのである。そして、だからこそ、地政学的な観点から見ても、新自由主義の中にある市場の「自発性」についてのハイエクの話は、混乱を招くだけなのである。」
新自由主義の台頭するいまでも、国家がでしゃばる状況はむしろ悪化しているのです。ゆえに、『ドクトル・ジヴァゴ』に描かれている時代と現代とはどこか類似性があると感じるわけです。
フンボルトに学べ
紹介したフラーのインタビューには、カール・ヴィルヘルム・フォン・フンボルトが登場します。フラーは、「フンボルトによれば、公務員には、人々の意志を理解できることと、その意志を行使できることという二つの条件が同時に求められている。同時に、フンボルトは、他の啓蒙思想家と同様に、国家が耐え忍んだすべての失敗は、結局のところ、人々の意志を正しく理解することも、それを実行することもできない官僚の無能さに起因するものであると考えていた」と書いています。だからこそ、人工知能(AI)が人の意志を実現するための最適な方法を見つけ出すという、新しい「国家」、すなわち、「国家2.0」が想定できるような時代を迎えつつあります。
ただし、フラーはつぎのように指摘しています。
「フンボルトは、人々がより多くの教育を受けるようになれば、「自分たちで法律を作る」ことができると信じていた(彼の師であるカントから取った概念である)。そして、この場合、国民を「代表」する「プロの政治家」のクラスは必要ない。
この場合、人々の集合的な意志を実行に移すことができる献身的な公務員が非常に必要となる。ここでフンボルトは、政治における目標と手段の明確な区分を念頭に置いていた:人々が集団的に目標を定義し、公務員は最良の手段を用いてその目標に向かって動く。したがって、将来の最良の状態では、まさに、個人的な利益のために公共の利益を戦略的に歪める政治家は、消滅しなければならないだろう。」
つまり、国家や公務員はなくならないにしても、政治家はいらないのです。これは、目からうろこの発見でした。
さっそく、フンボルトの著書『政治活動の限界』を購入することにしました。機会があれば、このサイトか「論座」において、その内容を紹介したいと思っています。



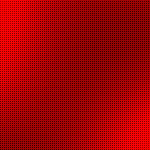





最近のコメント