『抽象の力:近代芸術の解析』への所感
『抽象の力:近代芸術の解析』への所感
塩原 俊彦
わたしの手元には、『国家アート論』という拙稿がある。2005年に執筆したものだ。「ここでは行政を、公的サービスや政府の詳細な職務をデザインし形づくるという、いわば「国家のアート」(art of the state)と考えているといえなくもない」として、このタイトルをつけたのである。この拙稿には、つぎのような魅力的な指摘がある。
「アートは本来、コードを差異化するという「脱コード化」を特徴としているのだから、行政に文字通りアートを持ち込めば、地球規模で広がるコード化、領土化による「排除」の蔓延に対抗できるのではないか、NPMというイデオロギーには、「行政をアートせよ」という単純明快な標語で抵抗できるのではないか。」
「アートは繰り返し挑むものであって、決して完成形を求めるものではない。だから、繰り返しトライしつづければいいのだ。アートを固定すれば、そこにコード化による「排除」が生まれてしまう。」
こうした発想は、Christopher HoodのThe Art of the State, Oxford University Press, 1998を読んで生まれたものであった。
なにがいいたいかというと、国家にかかわる問題を考察することは、「アート」の問題でもあるということだ。ゆえに、岡崎乾二郎著『抽象の力:近代芸術の解析』は決して芸術という狭い範囲だけを射程にとらえているわけではないのである。アートの問題は政治や経済の問題でもあるのだ。
164頁に芸術に対する岡崎の想いがのべられているから紹介しよう。
「彼女(ヴァネッサ・ベル)は平面的な模様に見えたものが運動(すなわち移行)し、視点が誘導され奥行き、空間を作り出すこと、その動的な過程こそが美的感動を与える、芸術的経験なのだといっているのです。つまり芸術は視覚的対象ではない。対象とそれに対する人間の変化それ自体なのです。重要なのは対象として焦点が合わされる以前です。焦点が合わされていなくても人はそこから何かを察知し、能動的な運動が引き起こされる。それはしたがって芸術作品として焦点を合わされる以前である。その作品の枠にいまだ収まらないところにすでにあるもの、それが環境であり、装飾なのです」
「対象とそれに対する人間の変化それ自体」が芸術たるアートであるとみなせば、岡崎の著作はさまざまな射程をとらえているように思えるのだ。
気になる指摘
ここではいくつかの気になる指摘を紹介するところからはじめたい。
56頁に、「ヘルムホルツ、ポアンカレの科学思考が与えられた広い影響に代表されるように、統計力学的、確率的な思考は日本の若い芸術家たちに確実に浸透しはじめていた」という記述がある。アンリ・ポアンカレの『科学と仮説』(La Science et l’hypothè se, 1902)は1909年に『科学と憶測』(林鶴一訳)として刊行されており、夏目漱石や寺田寅彦らに影響をあたえた。画家、熊谷守一にも影響をおよぼし、「重要なのは守一が、色彩が視覚的現象としてではなく、その背景にある視覚的に定位できない光のスペクトルの確率的偏差が引き起こす現象だと理解していたことにあろう」と、岡崎は書いている。
ここでの問題は、いま現在の最先端の問題、すなわち人工知能(AI)をアルゴリズムの正当性の問題に直結している。ちょうど2019年になって、佐藤俊樹は『社会科学と因果分析:ウェーバーの方法論からの知の現在へ』という本を上梓したのだが、その問題意識は岡崎が指摘した夏目、寺田、熊谷らの問題意識に通底している。だからこそ、きわめて興味深いのである。
そう思うと、148頁にあるつぎの指摘は実に興味深い。
「すなわち、知覚とは外部入力された感覚データとそれを認識、解読する構造の対応関係である。データは構造によっていったんエレメントに分析、解体され、頭の中で再合成される。三原色は人間がすべての色をいったん三つの色(波長)の組み合わせとして分析=解体し、頭の中で再合成して認識するという原理を示しています。それは音の知覚においても同じである」
さらに、149頁には「いずれにしても、われわれが直接的に感受していると思っていた感覚は、いったん入力された情報が分解され、再合成された結果なのです。いわば情報の圧縮と解凍。この原理は暗号の原理にも通底します」とある。ここまでくれば、夏目、寺田、熊谷らの問題意識が実に現代的で最先端の問題であることがわかるだろう。これにガイ・ドイッチャーの書、Deutscher, Guy (2010) Through the Language Glass: Why the World Looks Different in Other Languages, Metropolitan Books, Henry Holt and Companyを加えて読めば、色と言語の問題が認識論につながりながら、いまなおアポリアとして屹立していることがわかるだろう。
加えて、234頁にも気になる記述がある。
「制限された要素とその分布、濃度(ポテンシー)によって、さまざまな概念の移行、連合を扱おうとする集合論の発展は、当然、19世紀の産業革命と並行している。不均質な分布は均質な状態へと向かう(そして向かうべきだとされる)。不均質な偏差が、異なる概念(あるいは実際の事物の性格)の差異、衝突、闘争として現象する。それこそが力、権力が生じる源でもあった。こうした力学(統計力学)が19世紀以降のテクノロジー、政治を支配することになったのは周知の事実である。形態学はこうして政治的な力学へも接続され展開する」
というわけで、もはや岡崎の著作を狭い意味の芸術論にとどめることはできない。
科学への問い
つぎに、科学への重い問いかけについて紹介しよう。岡崎はつぎのようにのべている(397-398頁)。
「科学者の専門集団に参加する初学者は、まずその集団のドグマとして扱われている教科書(その例文)に示された範例、例文をマスターし、それを共有された雛型として、それを言い換えていくことによって論理を組み立て、記述を行う。つまり集団が組織されるあり方として、ほかの社会的な集団、生産組織と変わらない。いかなる生産であろうと、それを規定するモデル、模範となるのは、そこで生産される生産物それ自体である。模範としての事物は、抽象的な図式に決して還元できるようなものではない具体性をもっている。コンクリート・ミュージックについてシェフェールが述べたように、それは集団で共有された、一つの道具である」
社会科学者の端くれかもしれないわたしは、こうした構造に埋没するなかで、「歴史上の理論の推移とは人間集団におけるヘゲモニーの推移にほかならない。ゆえに、クーン以降、芸術も科学も理論上の論証も破綻し、すべては世俗的政治の場(それを論じる社会学的な議論)に還元されてしまう危険にも瀕することになった」という岡崎の指摘に首肯せざるをえない。もっと明確にいえば、つぎの岡崎の指摘(405-406頁)は、美術だけでなく、科学にもあてはまっていると思われる。
「残ったのは、市場(経済あるいは世論=言説的秩序)の中のテリトリー争い、その支配/排除、被支配をめぐるヘゲモニー争いである。である限り、その評価は生産物そのものではなく、それを産出した場所、あるいは受容される場所の、政治的な位置づけ、あるいは地政学的位置づけにこそ対応させられる。あるいは作家を含めた、供給(販売)、配給という経済的な人間関係に還元されてしまうだろう。1962年以降、いわゆる現代美術の大勢は、こうした人間主義的な活動そして身振りに還元されてしまうのである」
その結果、分析能力のない、あるいはオリジナリティのない、横文字を翻訳しただけの無意味と思えるような研究が評価され、官僚と結びつきながら学術集団におけるヘゲモニー秩序を維持している。いわゆる御用学者が多すぎる日本では、創造性に富んだ研究は潰されるだけという事態がいまでもつづいている。
美術の場合、海外で評価されて日本で再評価されるという事態がときどき起きる。花鳥画の名手、小原古邨こそその典型かもしれない。美術でこうした「逆転」が起きるのは、「事物による語り」としての美術が目に見えるかたちで多くの人々の鑑賞の対象となりうるからだろう。ところが、学術論文の場合には、なかなかこうした現象は起きない。そこに嘘がはびこり、バカでありながら御用学者として君臨できる仕組みができあがってしまっている。
とくに、わたしの研究対象であったロシアのような地域では、マルクス主義経済といった、わけのわからない主張に憑かれたような者がたくさんおり、ソ連崩壊後も猛省なしに鉄面皮をさらしている。こうした状況を改めなくては、日本の少なくとも社会科学は衰退の一途をたどることになるだろう。
「21世紀龍馬」には、こうした懸念すべき日本の現状を知ってもらいたい。そのうえで、外国の優れた研究に接してほしい。




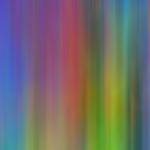



最近のコメント