無知という罪
無知という罪
塩原俊彦
8月5日、「そこまで言って委員会NP」という読売テレビが制作する番組を見る機会があった。「記録的な猛暑&豪雨&台風「災害大国」日本をどうする?」といった内容で、地球温暖化が話題になっていた。しかし、出演者全員が「地球温暖化」という問題について、無知であるという印象を受けた。
気象予報士が3人いるなかで、「地球温暖化」の原因が「ヒートアイランド」現象と気候の温暖化にあるというような議論が展開された。しかし、一方で、厳冬の到来についてうまく説明できないといった程度の話に終始した。
痛切に感じたのは、世界の常識として、問題は「地球温暖化」ではなく「気候変動」にあることを知らない出演者全員のバカさ加減である。この程度の知識しかない者がテレビに出演し、くだらぬ情報を垂れ流していることに愕然とした。
日本では、「地球温暖化」を前提に、温暖化ガスを削減するのは当然と思っている。マスメディアが安易に同調することでこうしたコンセンサスを形成している。しかし、ちょっと考えればわかるように、ヒートアイランド現象は温暖化の議論に直結するにしても、気候変動には直結しない。問題は、気候変動に人間の人為的な働きかけ、すなわち、二酸化炭素のような温暖化ガスの人為的排出量増加が本当に気温の大幅な変化をもたらしているかどうかにかかっているのだ。
この命題は、ニュートンの万有引力の正しさと同じように、科学的に証明された真理なのか。もちろん、そうではない。いまなお、議論が展開されている。この命題を信じる人々が圧倒的に多いから、地球温暖化防止のために合意したパリ協定からの離脱を表明したドナルド・トランプ米大統領は世界中から批判されたが、ニュートンの万有引力の法則のような絶対的な法則を否定したわけではないから、かれへの非難はどこかおかしい。
それこそ、共産主義や社会主義が科学的で優れた将来像であると信じて疑わなかった人々が多数を占めていた時代に、共産主義や社会主義を批判する者が強烈なバッシングを受けたのによく似ているように思われる。共産主義や社会主義の理念が間違っていたと多くの人々が気づくようになると、今度は共産主義や社会主義を唱える者が批判の標的になる。どうやら、人類の歴史は「村八分」の歴史であり、「多勢に無勢」、「長い物には巻かれよ」という生き方が穏当なのかもしれないとさえ思えてくる。
「地球温暖化は人間によるものである」という命題をもっともらしく主張してきた元凶は国連の下部機関、「気象変動に関する政府間パネル」(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)だ。1988年に国連の世界気象機関(World Meteorological Organization, WMO)と国連環境計画(United Nations Environment Programme, UNEP)によって設立されたもので、国連総会でも承認された。注意すべきことは、この機関は決して科学者によって設立されたものではないことである。ゆえに、IPCCは自ら調査を行うわけではなく、科学者などの調査報告に関する評価をくだす二次機関にすぎない。はっきり言えば、官僚が仕事にありつくための機関であり、地球温暖化による危機を喧伝すればするほど、自らの存在価値を高めることができるのだ。
このパネルは政府や国際機関によって承認された代表者から構成されている。つまり、単独者として、国家を信じない、独立した、大いに真っ当かもしれない科学者は排除されていることに留意しなければならない。こんな構造をもつ機関でありながら、IPCCは米国の政治家、アル・ゴアとともに2007年のノーベル平和賞を受賞したことで、地球温暖化問題の「権威者」であるかのような立場を固めるようになる。同年の第四回評価報告書には、「過去50年にわたる地球の平均気温上昇のほとんどは人間の活動にためである可能性がきわめて高い(専門家の判断に基づくと90%以上)」と書いてある。
しかし、これはまったくの推測であって、ニュートンの万有引力の法則と比べると、その科学的根拠は乏しいと指摘せざるをえない。もちろん、わたしはこの問題の専門家ではない。ただ、学者として社会科学という、自然科学に比べてかなりいかがわしい学問で飯を食っている者として言えば、この報告書はわたしの書く、いかがわしさの残る論文の域を出ていないのではないかと思える。それを教えてくれるのがMike Hulme著Why We Disagree About Climate Change: Understanding Controversy, Inaction and Opportunityという本だ。「コンセンサス」の形成によって、それが科学的であるかのように信じさせるIPCCのやり口を批判している。2001年に公表された第三回報告書で、2100年までに上昇する地球の海面が9~88センチから、2007年の第四回報告の18~59センチに修正されたのは、本当に気象変化に対する理解が深まったからなのだろうか。
地球温暖化が人為的なものであるとすれば、将来の地球温暖化は人口予測に大いにかかわっていることになる。たとえば、2000年のIPCC特別報告では、2050年の人口を、87億人、93億人、113億人の三つのケースを想定している(2000年の世界人口は約68億人)。最大差は26億人になる。これだけ大きな差を前提にしてしまうと、それだけで気温差に大きな影響をおよぼしてしまうのではないか。2017年6月、国連経済社会局は世界人口が現在の76億人から2050年に98億人に、2100年に112億人に達するとの予測を公表した。人為による気候への影響を認めるのであれば、人口数そのものに手をつける議論をなぜしないのか。「バース・コントロール」が人権侵害だというのであれば、他方で人為による気候変動は人間の自然権とでもいうのだろうか。
科学的とは言えないような根拠であっても、環境問題がクローズアップされ、地球規模で環境保護を重視する合意が形成されたのは「いいことだ」と考える人々がいるかもしれない。しかし、この合意形成を誘導した勢力がいて不当な利益を得ているとすれば、そう単純にパリ協定を首肯することはできないのではないか。それではだれがその合意形成で得をするのか。
その答えは核発電所(nuclear power plant)の推進論者だ(以下、原子力発電所という誤訳は使用しない)。核発電は直接的には二酸化炭素のような温暖化ガスを発生させない。ゆえに、パリ協定は核発電推進論者にとってはこのうえのない決定ということになる。しかも、パリは核発電を世界でもっとも推進してきたフランスの首都であり、パリ協定の背後に核発電推進論者の影がちらついていると論じても、真っ向からこの議論を否定できる者はいないだろう。
このように、真摯に気候変動問題を考えてみると、トランプ大統領のパリ協定離脱という決断は決して荒唐無稽なものではないことがわかる。むしろ、合意形成に潜む陥穽に気づかせてくれるという意味で、称賛に値する英断であったということも可能だ。問題なのは合意形成に潜む罠について言及しないマスメディアの「合意のでっち上げ」にあるのだ。日本では、とくに「合意」部分が重視されるために「でっち上げ」部分への警戒が足らないと、わたしには思われる。
バカがテレビに登場し、バカげた議論をしているようでは、まったく話にならない。





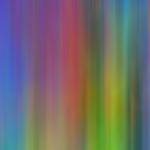


最近のコメント